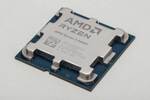インテルは26日、都内にて記者説明会を開催し、薄型軽量ノート「Ultrabook」を構成する主要技術について説明した。基本的には9月13~16日に米国で開催された「IDF San Francisco 2011」での発表を元にしているので、こちらの記事も合わせてご覧いただきたい。
Ivy Bridgeで導入される
消費電力削減の機能とは?
Ultrabookとは、インテルが定義する新しいモバイルノートのカテゴリーである。厚さ2cm程度の薄さと軽さに、インテルの超低電圧版CPUを搭載。さらに長時間のバッテリー駆動や、スリープ・休止からの復帰の速さ、セキュリティーの強化といった要素を盛り込んだモバイルノートである。Windows PCではないが、MacBook Airをイメージするとわかりやすいだろう。
Ultrabookに属する製品は、現行の第2世代Coreプロセッサー(Sandy Bridge)から登場する。だがインテルが本腰を入れているのは、第3世代Coreプロセッサーとなる「Ivy Bridge」で作るUltrabookだ。Ivy Bridgeは22nmプロセスを採用する新CPUで、基本的にはSandy Bridge世代の微細化&アップデート版であるが、Ultrabookに適した省電力化の機能がいくつか導入されている。
その代表格が、「Configurable TDP」と呼ばれる機能だ。現在Ultrabookに使われている超低電圧版のCore i5/i3などは、パソコンの熱設計の基準となる「TDP」が17Wとされている。これは基本的に、CPUに高負荷がかかった状態での消費電力である。ノートパソコンの開発では、このTDP時の放熱量を前提に冷却機構や筐体を設計するのがセオリーとなっている。
しかし、実際にモバイルノートが使われる際に、17Wのフルパワーで持続的に動作することはほとんどない。そこでインテルでは、Ultrabook設計の際には17WのTDPを目標にするのではなく、一般的な使用時の消費電力(8~12W程度)を目標に設計することで、薄型軽量化が可能になるという。それを実現する技術がConfigurable TDPである。
Configurable TDPを実現する鍵は、ターボ・ブースト・テクノロジーの存在である。Configurable TDP対応のCPUでUltrabookを作る際には、通常時のCPU動作周波数や電圧の上限を、消費電力8~12W程度に収まるように低く設定する。これだけでは単にCPUを遅く動作させただけだが、高い処理能力を要求するアプリケーションが動作した場合には、ターボ・ブーストによって一時的にCPUを高周波数で動作させれば、ユーザーの使用感を損なわないですむ。ただし、放熱も増えるターボ・ブースト状態での長時間動作はできないので、放熱の許容範囲を超えるとパソコン側が判断すれば、自動で動作周波数は下がる。
一方で、例えば放熱機構付きドッキングステーションと組み合わせたような放熱に余裕のある環境では、消費電力を定格通りの17W程度に設定する。つまり同じノートパソコンでも、環境に応じてTDPを切り替えられるのがConfigurable TDPのポイントである。
ただし、Ultrabookでは必ずTDPが低く設定されるというわけではない。もし薄型筐体でも充実した放熱機構を組み込める技術のあるメーカーであれば、優れた放熱機構とIvy Bridgeを組み合わせることで、モバイル使用時でも定格通りの処理性能を提供することが可能になる。つまり、同じCPUを使うUltrabookカテゴリーの製品でも、製品コンセプトや実装技術によって異なる性能や方向性のUltrabookを実現できるので、製品の差別化につながるというわけだ。