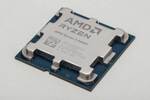今回は半年振りに、インテルチップセットのロードマップアップデートをお届けしよう。とはいっても、半年前の連載152回からはあまり大きな変更はない。
Intel Q77の機能は、
実はZ77で実装されていた
2012年6月、ビジネス向けとなる「Intel Q77」チップセットと、このサブセットである「Intel Q75」チップセットの2つが発売された。
Q77はCPU側のPCI Expressレーンのサポートが「x16」のみ(x8+x8のデュアルGPUはサポートしない)とされた一方で、PCIバスが追加されている。実のところ、先に登場した「Intel Z77」にもPCIは搭載されており、それが無効化されていたというのが正確だ。Q77はこれを有効にしたわけだ。
またセキュリティー機能の「vPro」や、セキュリティーや運用管理を支援する機能「Intel Small Business Advantage」なども有効になっているが、これもQ77で新たに追加されたわけでなく、すでにZ77に搭載されていたものの無効化されて機能を、有効化したにすぎない。
Q77/75の機能は、一般コンシューマーにはほとんど無関係であるが、唯一関係しそうなのは仮想化支援機能「VT-d」(Virtualization Technology for Directed I/O)のサポート。これはOS上で仮想マシンを動かすときに、I/Oの仮想化アクセラレーターを有効にする機能であるが、Z77では無効になっているこの機能が、Q77では有効になっている。VT-dは仮想化システム「Hyper-V」などを使って、仮想OSを使うときの性能に大きく影響する。こうした使い方をするユーザーはそう多くはないだろうとは思うが、仮想化環境を必要とするユーザーには、Qシリーズは非常にいい選択肢である。
Q75はQ77のサブセットで、SATA 6Gbpsのポートがひとつ減らされたり、SSDキャッシュを使ってHDDを高速化する機能「Intel SRT」(Smart Response Technology)が省かれたりといった違いがある。また、vProや管理機能「AMT」(Active Management Technology)、VT-dといった、Q77で有効化された機能がほとんど無効化されている。つまり「Intel H77」のさらに下位、といった位置づけになる。
そんな製品が「Intel H75」ではなくQ75になったのは、インテルがビジネスPC向けに行なっている「SIPP」(Stable Image Platform Program)という取り組みでサポートされているという、ただ一点と言ってもいいだろう。SIPPはインテルが2003年頃から行なっている取り組みで、ビジネス用途に安定したドライバー類をまとめて提供し、これの長期サポートを保障するというものである。
ちなみに152回の記事では、「ひょっとするとH71の可能性はまだあるかも」と説明したが、結局出ないまま終わってしまった。昨今の状況を考えれると、H71を出す意味はほとんどなかっただろう。

この連載の記事
-
第833回
PC
RibbonFETの限界とCFETの賭け インテルは次の10年を超えられるか -
第832回
PC
Intel 18AでSRAMは進化したか? Synopsysが挑む最適化技術とWrite Assistの新アプローチ -
第831回
PC
Intel 18AはTSMCに対抗できるか? RibbonFET/PowerVIAの可能性と限界 インテル CPUロードマップ -
第830回
デジタル
HPCからAI向けに用途を変えたInstinct MI350X/400X AMD GPUロードマップ -
第829回
デジタル
2026年にInstinct MI400シリーズを投入し、サーバー向けGPUのシェア拡大を狙うAMD AMD GPUロードマップ -
第828回
PC
TOP500の4位に躍り出たJUPITER Boosterは効率と性能/消費電力比が驚嘆に値する -
第827回
PC
オーディオとモデムを普及させるのに一役買ったAMRとACR 消え去ったI/F史 -
第826回
PC
PCIeリリース直前に登場しわずか1年の短命に終わったCSA 消え去ったI/F史 -
第825回
PC
バッファがあふれると性能が低下する爆弾を抱えるもライセンスが無料で広く普及したAGP 消え去ったI/F史 -
第824回
PC
AT互換機が普及するきっかけとなったPCIは、MCAの失敗から生まれた 消え去ったI/F史 -
第823回
PC
Intel 18AはIntel 3と比較して性能/消費電力比が15%向上 インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ