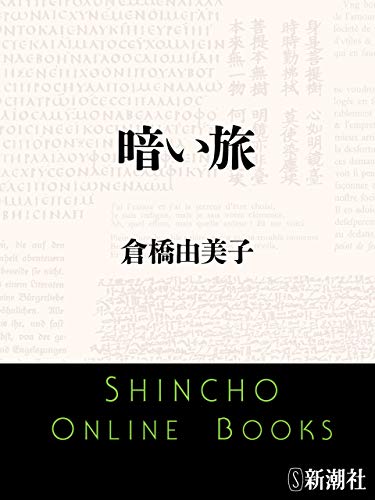Kindle版もあります。
小説は、読まれてはじめて完成する。
だから、たくさんの人に読んでほしいと思うのは、小説家の性。
でも、いいことばかりではありません。
誤読されたり、批判されたり、神様みたいに言われたり。
そんなとき、誠実に応え、自分の心を守って書き続けるための、《読まれ方入門》。「小説を一生懸命書いて、誰かに読まれたいと願って、それなのにいざ読まれるとなると、辛いことも起こります。矛盾しているかもしれませんね。
わたしは、小説家という仕事には〝読まれることそのものの痛み〞がつきものなんじゃないかと思っています。
解釈されることは、傷を受けることだからです。」(「はじめに」より)
「読まれる覚悟」とか言っても、ほとんどの文章は、覚悟が必要なほど読まれない。
炎上しようと思っても、無名の人がちょっと過激なことを言ったり書いたりしたくらいでは見向きもされないんだよな、というのが僕の実感ではあるのです。
「覚悟」が必要なのは、この本の著者の桜庭一樹さんのようなごくひと握りの人気がある作家やブロガー、YouTuberくらいで、「あの人があんなことを言っている」という「あの人」になることそのものが難しく、その難易度も年々上がってきています。
僕自身は、長年こうしてネットで書き続けており、「炎上」というか、批判のブックマークコメントが並び、絶望的な気分になったり顔を真っ赤にしながら反論したりもしましたが、最近は比較的心穏やかに書けるようになりました。というか、書くモチベーションが下がり、日々機嫌よく過ごすことにシフトしてきている、という感じです。これが「飯のタネ」じゃないというのは、かなり大きいのではないかと。
著者の桜庭一樹さん、僕は『GOSICK -ゴシック-』で知ったのです。
ライトノベルで脚光を浴び、文芸小説でも高く評価され、映画化もされた『私の男』では、直木賞を受賞されています。
個人的にはいちばん好きなのは『赤朽葉家の伝説』です。僕はこういう「代替わりしながら綴られる、一族の記録」の小説が大好きで、この作品は、そのなかでも素晴らしいと思っています。
fujipon.hatenadiary.com
fujipon.hatenadiary.com
この本のタイトルは『読まれる覚悟』です。あなたはこれをどういう意味だと思って手に取ってくれたでしょうか?
わたしはというと、「小説を出版したからには、誰にどんな感想を言われても仕方ない」「それを我慢できないのは、プロとしての覚悟が足りないせいだ」という意味ではないと思っています。でも「作者は自分なんだから、誰にも何も言わせないぞ」ということでもないと。
この本では、あなたが将来小説家になったとき、心をなるべく平穏に保ちながら、読まれる立場に身を置き続ける方法についてお話しします。
小説家による「小説の書き方入門」はありますが、「小説の読まれ方入門」はなかなかなかったのではないかなと思っています。一章では、小説が出版されたときに起こること。
二章では、一般的な読者の方にどう読んでもらうか。
三章では、批評家や書評家の方と共存する方法。
四章では、ファンダムがある作品の原作者になること。この順番で(ときどき話が脱線しながらも)書いていきたいと思います。
「読まれる覚悟」なんて、実際にしなきゃいけない人は少数派だろうに、と思いながらこの本を手に取ったのは、桜庭さんが書かれた本だから、というのが大きかったのです。
桜庭さんは、長年『読書日記』を連載されていて、いち読者として本を読むのが好きでたまらない人で、桜庭さんがこれまで読んできた過去の名作や海外ミステリなどの話は、本好きとしてはすごく楽しくて、自分が次に読む本を選ぶきっかけにもなっていました。
桜庭さんは、作家であるのと同時に、読書家・書評家としても知られており、ある意味「読む側、あるいはファンの気持ちもよく理解している人」ですし、このテーマで新書を書くのであれば、確かに適任だなあ、と思うのです。
桜庭さんは、小説家として商業的にデビューしてからすぐに売れっ子になったわけではなく、デビューから約4年後に『GOSICK』がヒットするまでは、作品が売れずに辛い時期かあったことも書かれています。
誰かが読んでくれないと、書いた人は、苦しいです。
多くの小説家さんがデビュー後に最初に受ける洗礼は、意外とこの”無”かもしれません。
これは小説に限らず、ブログやYouTubeなどの動画でもそうなのだと思います。
「書く」「つくる」側にとっては、完成するまでのハードルはかなり高いし、「こんなに頑張ったのだから」と、自分の作品を贔屓目にみてしまう。
でも、コンテンツを選ぶ側からすれば、「まだ文章も拙く内容にも乏しく、3回分しか書かれていないブログや動画」とすでに大人気の有名人ブログやHIKAKINさんの動画を比較して、どちらを読む(観る)か選ぶことになります。「消費するのには同じくらいの時間がかかる」のだから。
「読まれる覚悟」よりも「読まれる方法」を教えてくれよ、ですよね実際。
考えてみれば、「4年間売れなかった」小説家でも、ひとつのヒット作がきっかけで人気作家としてコンスタントに売れるようになるのですから、創作の世界というのは不思議なものではあります。技術的な向上が理由だったのか、「売れるコツ」みたいなものを掴めたのか。
Mr.Childrenの桜井和寿さんが『Cross Road』が大ヒットしたときに「ミリオン(100万枚)を売るコツがわかった」と仰っていたそうなのですが(実際にその後、Mr.Childrenはミリオンセラーをたて続けに出しています)、世の中には「一発屋」もたくさんいるんですよね。僕もこの年齢まで生きてみると、一発があっただけでもすごいな、とも思うのですけど。
書いたものが世に出たら、読者がそれをどう読むかには「解釈の自由」があるのか? 「誤読」も読者の権利として受け入れるべきなのか?
作者が「わたしはこういう意味で書いた」と宣言すれば、読者はそれに従わなければならないのか?
僕くらいの規模のブログであっても、「そんなこと書いてないのに……」という解釈をして、抗議や批判をしてくる人がそれなりにいるのです。
うまく伝わるように書かれていないからだ、というのは否定できませんが、最初からまともに読む気がないのでは、と言いたくなることもあります。
ネットでの反応って、応援2割、沈黙7割、批判1割くらい、というのが実感なのですが、書いている側からすると、1割の批判にばかり目が向いて、反応してしまいがちで、応援してくれる人たちには申し訳ない。でも、そういう負の感情みたいなものをうまく乗りこなすのはとても難しい。
星野源さんが、エッセイで「つねに注目されている自分」に疲弊していたことを書いておられます。
「売れない」のはつらいけれど、「売れすぎる」と、別の悩みが出てくるようなのです。
桜庭さんがこの本の中で書かれていることのなかで、僕は「作家にとっての批評」についての話が、とくに印象に残りました。
わたしは去年、嬉しくて、興奮して、大きな発見もできる批評をみつけました。そのお話もさせてください。
1960年に25歳でデビューした小説家の倉橋由美子さんについての批評です。
倉橋さんはデビュー翌年に書いた初の長編小説『暗い旅』を、男性の批評家や翻訳家たちに厳しく批判されたことでも知られています。「暗い旅論争」と呼ばれ、文壇の負の歴史として残っています。
内容を読むと、正直よくわからない理屈が、若い女性である作者本人を置いてきぼりに男性の間で飛び交っていて、それこそファーストネームにちゃん付けで呼ばれていたりしていて、何の話なのかわかりません。現代の感覚でいう、いわゆる炎上状態に近いのかもしれない。関係ない話にずれながらどんどん燃え広がる。話題に入ってくる人が差別意識まるだしで侮辱する。いったいなんだ、これは……?
2023年に出版された小平麻衣子さんの『なぞること、切り裂くこと──虚構のジェンダー』を読んで、ようやく理解できました。くわしくは同書か『掌の読書会──桜庭一樹と読む倉橋由美子』(中公文庫)所収の小平さんの解説「あなたはだんだん倉橋が読みたくなる──『暗い旅』のまやかし」をぜひ読んでみてください。
著名な批評家が、『暗い旅』はある海外文学と手法が似ているが、その作品のよさが『暗い旅』にはない、だめな模倣だ、と批判したことがはじまりなのですが、批評家や翻訳家などの男性間で、作者を未熟な女の子のように揶揄う(からかう)軽口も続いて、いま読むと阿鼻叫喚で、どんどんわけがわからない論争になっていきます。それが小平さんの批評によって、手法がうまく使われていないと男性の批評家に最初に批判された部分こそが、じつは作品の主題である女性性の表現であること、その批評家はそこに理解が及ばなかった、作品の意味を汲むことができていなかったということが、論理で証明されています。
作品の発表と謎の論争のはじまりから62年もの時を経た2023年、当時26歳だった作者も29歳だった批評家もこの世にいない今、作品の理解、作者の名誉挽回が女性の批評家によって行われた、鮮やかで感動的な最高の批評でした。
作品の内容よりも、「若いから、女性だから、人生経験が足りないから、新人だから、外国人だから」というような作家の属性について揶揄し、「文壇」の内部で嘲笑するような行為が「批評」なのか?
ただ、僕自身も、この手の「本の感想」を書いたことがありますし、こういう「揉め事」的なものがウケる、読まれやすい、というのは62年前も現在も似たようなものではあります。
そして、商業出版やお金を稼ぎたいブログや動画の場合、現在でも、注目を集めるために「作家の属性」を利用していることが多いのです。
若い女性作家の顔写真が帯に大きく掲載されていたり、書かれているセンセーショナルなことが、作家自身の経験を反映していると読者に思わせたり(逆に、読者から、登場人物の思想はすべて作家の思想を反映しているという誤解をされて困ることもあるそうです)。
読まれなければ”無”である。
でも、読んでもらうためには、なんらかの「内容プラスアルファのテコ入れ」が不可欠になっている。
読む側としても「どんな人がこれを書いているのか」は、やはり気になりますよね。
作品を、純粋にその内容だけで評価する、べきなのか、「誰が、どんな人が書いているのか」まで含めての「作品」なのか。
桜庭さんは、この本のなかで、作家として、「批評との向き合いかた」をあらためて表明されているのです。
もう一つ。
批評について、わたしからお伝えしたいことがあります。
「少女を埋める」「キメラ」について、2021年の終わりから2022年のはじめにかけて、若手の批評家の方々から指摘された問題点が二つありました。
第一に、ベテランの小説家は自分の特権性については無自覚で、新人のころの弱いままの自分像があるが、年齢やキャリアが進んでからは自分の加害性についてこそ書くべきだというご指摘です。
第二に、実在の人物について小説内で書くことの暴力性に無自覚ではないか、というご指摘です。
第一はTwitterのスペースでの詩人との対談。第二は文芸誌の批評でした。
どちらも、わたしの価値観に残る古い部分をピックアップしたうえで、加害性をこそ問題視したものとして受けとりました。
これらのご指摘について、直接コメントすることはしておらず、いまこのページで初めて言及するのですが、わたしは非常に正直にいうと、最初はプライドを傷つけられて腹を立てました。それから、理解できるまで考えました。そして約一年後の2023年3月から雑誌連載を始めた小説『名探偵の有害性』では、自分および自分の世代が持つ加害性をテーマに選びました。
単行本化された際、書評家の瀧井朝世さんのインタビューを受けました。記事のタイトルは「アップデートとは、自分が間違っていたと理解すること」です。──読みながら、成長って、新たに何かを獲得するのでなく、自分の過去を検証することもできるんだな、とつくづく思いました。
桜庭:そうですね。最近、アップデートって、「新しいものをインストールする」というよりも、「自分が間違っていたと理解する」ことなのかな、と思うんです。過去の自分の加害性を理解して、自分を変える努力をしないと、アップデートにはならないな、と。今回は名探偵と一緒に、私自身もアップデートしたいなと思いました。
(「アップデートとは、自分が間違っていたと理解すること──桜庭一樹『名探偵の有害性』ロングインタビュー」『別冊文藝春秋』(作家の書き出しVol.32)
私は(この新書の)三章で、批評家は小説家の教育者になりうると書きましたが、それはベテラン批評家が新人小説家にとって、という意味だけではありません。
わたしの例をとっていえば、新人の批評家たちは、きっと言いづらいなかできわめて慎重に言葉を選び、伝えるべきことを伝えてくれたのだと想像します。
『読まれる覚悟』というタイトルの新書なのですが、僕は桜庭さんの「歳を重ね、ベテランとして時代や若い人たちに向き合っていく覚悟」が書かれていると感じました。
僕自身にも、長年やってきて、職場でもネットでも、「同じようなこと、あるいは、もっとひどいことを言っている人はたくさんいるのに、比較的読まれているから、影響力が(少しは)あるから、という理由で、量刑が重くなり、叩かれるのは理不尽ではないか」と思ってきたのです。
そこらへんの人が不倫をしていてもスルーされるだけなのに、有名人がやると、なぜあんなに炎上するのか?
同じことをやっているのに不公平ではないのか?
(僕はしてませんけど、と書いておかないと勘繰られるのが今のネット社会というやつです)
でも、立場が変われば、責任の重さも変わるし、他人からの見られかたも変わる。それはもう、どうしようもないことで、それも引き受けて、年を重ねていかなければならない。
「あの頃はそれが当たり前だったのだから」と開き直るのではなく、つねに「現在の価値観」を意識しないと、あっという間に「単なる老害」になってしまう。
本当に、言うは易し、行うは難し、なんですけどね……