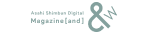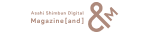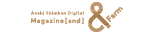ファクトチェック廃止とデジタルの虚実 正しさが生身に回帰する日
経済季評 慶応大学教授・坂井豊貴さん
真実は何か。どうすれば判定できるのか。管見の及ぶ限り、こうした問いを最初に厳密に考察したのは、人民主権論を打ち立てたジャンジャック・ルソーである。フランス革命前の時代の話だ。
ルソーは、提出された法案が皆の共通の利益にかなうか否か、判定する方法を考えた。結論は投票だ。ただし、ただの投票ではない。人々が私的利益を脇に置いて、その法案が皆の共通の利益にかなうかを熟慮したうえでの投票だ。
むろん人々は私的利益を完全に脇に置けるわけではないから、少しずつ間違いはする。だが人数が多いと、互いの間違いが打ち消し合う。その結果、多数派の意見の中に真実が見えてくる。大まかに言うと、これがルソーの考えだ。
やがてこの考えは、ルソーの影響を受けたコンドルセによって、統計学の手法で定式化された。両者のこうした議論は、多数派を決していたずらに礼賛するわけではなく、いかなる条件下で多数派の意見を採用してよいかを問うものだ。
コンドルセによる定式化を陪審定理という。その成立条件で特に重要なのが、判断の独立性だ。それは各人が他者の意見に追従したり、空気に流されたりするのではなく、熟慮の上で判断することだ。
コンドルセの議論から約2世紀半。今月7日、フェイスブックとインスタグラムを運営する米メタ社は、投稿内容の真実性を調べる、独立したファクトチェッカーの廃止を発表した。
表向きの理由は「表現の自由…
- 【視点】
清水幾太郎の古典『流言蜚語』によれば、情報の真偽をその内実によって判断することはそもそも不可能であり、われわれはその出所を信頼しているかどうかで判断しているにすぎない、とのことです。これまでのおよそ1世紀は、とりわけマスメディアが信頼を独占
…続きを読む