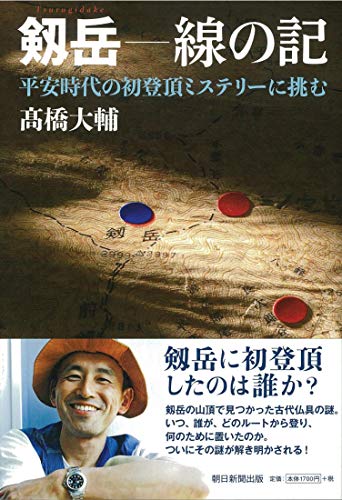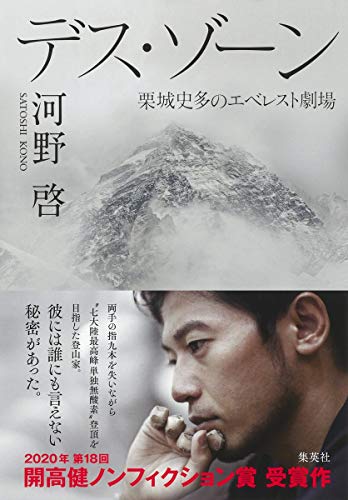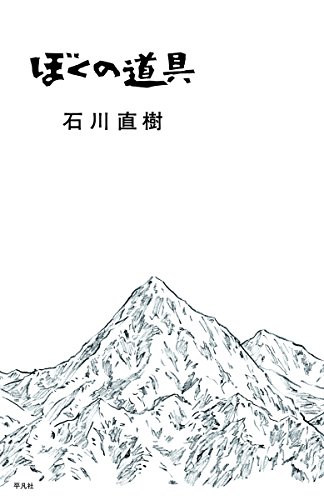書評
『剱岳 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む』(朝日新聞出版)
先人への敬意と気迫を胸に千年前の頂の謎に迫る
探検家、髙橋大輔が四年を費やし、日本の山に秘められた歴史的ミステリーに挑んだ。かつて実在したロビンソン・クルーソーの住居跡を発見、画期的な探検実績をもつ著者は、あらたな挑戦の場として、日本でもっとも登頂が困難とされる北アルプスの剱岳(つるぎだけ)(標高2999メートル)を選ぶ。一歩ずつ、難場を越えて謎解きに迫る展開が、緊迫感のある読み応えをもたらす。
本書の題名『剱岳-線の記』は、もちろん新田次郎の小説『劒岳・点の記』に呼応している。明治40年、測量のために剱岳登頂に成功した日本陸軍参謀本部陸地測量部・柴崎芳太郎は、山頂でおよそ千年前の仏具を発見する。つまり、遙か昔、何者かが剱岳登頂を果たしていたという事実。新田次郎は小説を執筆するさい、この事実に関する推論を語ると、勉強不足だと諫められたり、感情的に否定されたりもする。不可解な反応を訝しんだ新田次郎は、こう書いた。
「劒岳は死の山であり針の山であって、登ってはならない山であった」
急峻(きゅうしゅん)さゆえ、山岳信仰の対象として畏怖され、崇められてきた剱岳。江戸期は入山が禁じられていた。では、いつ、誰が、どのようにして、なぜ山頂に仏具を奉納したのか。明治期、国策としておこなわれた三角測量地点を巡る「点」の物語は新田次郎によって描かれたが、いっぽう、千年の歴史を繋ぐ「線」の物語に挑んだ者はいない。
中心人物はふたりいる。ひとりは剱岳のファーストクライマー、もうひとりは著者。読者は、謎の人物を追いかけるためにみずから剱岳に登攀(とうはん)する著者の一挙手一投足から目が離せない。カニのよこばいと呼ばれる垂直の岸壁でともに肝を冷やし、冷たい沢の水に胸まで浸かりながら登る苦労を共有する。あるいは、柴崎隊によって百年以上前に設置された「三等三角点」の標石そのものに著者が指で触れるとき、私たちはナマの歴史と対面する温(ぬく)もりを体感する。山行の現場で詳細に綴られる見聞に加え、迷いや期待、興奮をともないながら押し進められる推理の道すじが、リアルな読書体験を醸成してゆく。
現在、剱岳の登攀には三つのルートがあるという。しかし、これらの地理的条件から判断すれば、現代の登山装備でなければ登頂は困難だ。複数の登攀を重ねて調査をおこなったのち、著者は、かつて山伏は古道をふくむルートを使ったのではと推理し、立山川近隣のハゲマンザイを見つけ出す。
いよいよハゲマンザイのルートによって始まる謎解きの過程には、カタルシスがある。古代人が剱岳を登攀した理由。ふたつの仏具、錫杖頭(しゃくじょうとう)と鉄剣の意味。山岳信仰や修験道との関わり。ハゲマンザイという地名に隠されたもの……次々に明らかにしながら、著者は、現代の登山からは想像もつかない、千年前におこなわれた命がけの登攀の意味にたどり着く。
おびただしい史料や文献の渉猟、各地に関係者を訪ねる取材を駆使しつつ、登山という心身の思考運動に挑む著者の姿は、探検家のそれでもあるが、ときに山伏を彷彿させもする。現代と過去の時空をさまよいながら、謎解きを超え、山と人間との根源的な関係に踏み込んでゆくさまに胸打たれた。