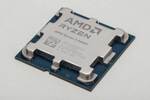先日、出版科学研究所から2010年の雑誌・書籍販売金額が発表され、雑誌は13年連続、書籍も4年連続の減少であることが明らかになった。電子書籍は集計外だったため、電子書籍元年と言われた2010年の売れ行きは判然としないままだが、少なくとも紙の雑誌・書籍の縮小傾向が続いていることは間違いない。
ここまで4回にわたって電子書籍のサービスやハードを利便性の面から紹介してきた。第5回となる今日は、電子書籍の発展を左右する出版社、書店、そして個人出版界隈の状況について解説したい。
電子書籍は再販制で守られない
電子書籍を巡る議論で忘れてはならないのは、再販制(再販売価格維持制度)の問題だ。
これまで書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトは、メーカーが流通事業者に対して、価格を提示し、それを守らせることが例外的に認められてきた。
もちろん、いったん消費者の手に渡った商品はその権利が消尽(しょうじん)するので、そこからの転売、それによる価格の変化が生じることは問題ない。しかし、そこに至るまでは、原則として定価は維持され、出版社は発行部数に応じた利益をある程度織り込んで事業を展開することができた。
ところが、昨年末、公正取引委員会はこの再販制度に電子書籍は含まれないという見解を示した。電子書籍はモノではなく情報であるというのがその根拠だ。これまで再販制度を前提に紙というパッケージを、書き手、出版社、印刷会社、取次、書店から成る輪が回していたが、これがデジタルに変わることによって、そのモデルは大きく転換を迫られることになる。
なぜなら、出版社はこれまで書籍や雑誌を作ったあとは、価格を決め、取次業者にそれを委ねることでビジネスが成立していた。ところが電子書籍の領域では、自ら流通経路を選択し、需要を見ながら価格を変化させ、なおかつ周到なマーケティングを仕掛けることが求められる。
「BOOK☆WALKER」を運営する角川コンテンツゲートの安本洋一取締役によれば、書店やコンビニエンスストアなど生活動線に配置される従来の書籍とは異なり、電子書籍は、出版社自らが仕掛けを作り、読者を誘導していく必要があるからだという。電子書籍ストア任せでは、動かないカタログの一品に過ぎないわけだ(関連記事)。
これを危機と見るか機会と見るかで、プレイヤー(著者、書店、出版社)の戦略は大きく異なるだろうが、筆者がこれまで取材を重ねてきた限りでは、既存プレイヤーに抵抗はなく、なんとかこの変化を機会に変えようと試行錯誤を重ねている最中だ(関連記事)。
出版社の役割は著者育成と広告宣伝にシフト
2010年は作家自らが電子書籍を販売したり、そのための会社を設立するなどして注目を集めた。「電子書籍=出版社を介さずに書き手が書籍を販売できる」という意見が盛んに語られもした。
実際、Amazonは「Kindle DTP」という仕組みを新たに備え、Wordの原稿からでもKindle Storeでの電子書籍販売を可能にしている。
ここで問われたのは出版社の存在意義だ。前述の通り、単に原稿をとりまとめてパッケージングした商品を取次に卸すだけでは、その立ち位置に価値は薄くなる。
しかし、出版社が果たしていた機能はその部分だけではない。
漫画における週刊誌・月刊誌、そして小説の分野における文芸誌の存在は、書き手の発掘と、その育成という意味において重要だ。プロの編集者が才能ある書き手を見つけ出し、毎週・毎月決められたスパンで書き手と共に原稿を練り上げていくことで、新たな「本」と「作家」を生み出すわけだ。
また、小説や漫画は映像化、商品化といった権利ビジネスの源泉でもある。タイミングを逃さずに広く展開するためには、やはり人手や費用を掛けなければならないのも事実だ。
キャラクターライセンス管理を担うべく2008年に誕生した小学館集英社プロダクションはその代表例と言えるし、角川グループは、自ら垂直統合型の電子書籍プラットフォーム「BOOK☆WALKER」の運営に乗り出している(関連記事)。
電子出版のプラットフォームが整ったからといって、即書き手による直販に雪崩を打って移行するとは考えにくい。
むしろ、再販制度の枠外におかれる電子書籍は、これまで以上にマーケティングのスキルとリソースが求められるというのが現実的な見方だろう。
テレビアニメを起点とするメディアミックスは、書き手だけでは実現できない取り組みであるし、電子書籍ストアに商品を並べるだけでなく、価格を変動させたり、一定期間が過ぎれば商品をいったん引き上げ、商品の希少性を確保する、といった仕掛けも必要になってくるからだ。
同人の電子書籍化――権利者の黙認はいつまで続く?
書き手主導の戦略を考えていくと避けて通れないのが、同人カテゴリーの動きだ。年2回のコミックマーケット、また各地で開催されるジャンルごとの販売会は、ライブイベントにも似て需要と供給が一時期に極大化する。
書き手が決めた価格で、読者に手渡しで販売する――本来の「直販」の姿を煮詰めたような光景がそこにはある。一方、それらのイベント以外の日常では、委託販売が行なわれてきたのも一面の事実だ。
ネット通販では、株式会社エイシス(現在は株式会社ゲオの子会社)が運営する「DLSite.com」が2000年代からダウンロード型販売サイトを手がけており、また昨年末には業界大手のとらのあながストリーミング型のサービスをプレオープンした。
一定以上の人気がある同人作家の場合、コミックマーケットのような直販の場だけでは需要を賄うことができないため、とらのあなに代表される「同人誌を委託販売する店舗」がその活動を支えてきた部分がある。
一方で、同人誌の販売はイベント会場や同人誌販売店といった「閉じた場」に限られていたが故に、著作者に許諾を得ずに制作されるパロディー作品なども黙認されてきた一面があることも否定できない。
そのため、電子書籍ブームに合わせて同人誌販売がネットにその軸足を移したとき、際限なく複製可能になった「電子同人誌」を出版社がどう判断するかは不透明だ。
どちらにせよ、権利ビジネスの拡大に伴って、作品の二次利用は重要性が増す一方であることに違いはない。コミケでの二次創作は読者の裾野を広げ、またクリエイターが育成・発掘される場でもあったが、ネットでそれらの作品が常に手に入る状態で広く流通したとき、ポジティブな側面だけでは語れなくなる可能性は高い。
パロディなどの扱いについて昨今議論が交わされている日本型フェアユースとの関係も今後問われることになるだろう。

この連載の記事
-
第6回
トピックス
電子書籍、電子コミックはここで買え! -
第4回
トピックス
実は重要! よくわかる電子書籍フォーマット規格!! -
第3回
トピックス
主要携帯キャリア動向—主戦場はスマートフォンと専用端末へ -
第2回
トピックス
特徴は?値段は?電子ブックリーダー選びのコツ! -
第1回
PC
これだけは知っておけ!日本の電子書籍事情 -
トピックス
電子書籍を選ぶ前に知っておきたい5つのこと - この連載の一覧へ