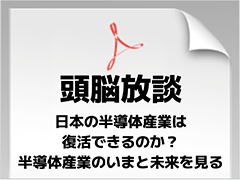「ローカル5G」は5Gと何が違うのか?:Tech Basics/Keyword
ローカル5Gの免許申請が開始され、東京都などが申請を行ったというニュースが流れている。このローカル5Gについて、第5世代移動通信システム「5G」と同じ点、異なる点を解説する。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
ローカル5GとWi-Fi 6は違う?
「ローカル5G(ローカルファイブジー)」とは、5Gネットワークを自分で運営することだ。技術的には5Gそのもので、条件を満たして免許を受ければ、誰でも自分専用の5Gネットワークを構築できる。ただし、現時点では、自身が所有する土地や建物での利用に限定され、地域で周波数の割り当てを受ける必要があるため、無制限に開局できるわけではない。
また、そもそも5Gは、通信事業者が利用するための技術であり、その価格は決して安いわけではなく、Amazonなどで機材を買ってきて設置というわけにはいかない。
世間では、「ローカル5G」と「Wi-Fi 6」のどちらがいいかといった議論もあるようだ。しかし、そもそも一般消費者でも購入が可能なWi-Fiと、MNO(Mobile Network Operator:ドコモなどの通信事業者のこと)が設置する場合に安くても1000万円、場合によっては億の単位になるといわれている基地局やネットワーク設備とはあまりにも違い過ぎる。例えれば、自転車と新幹線(の切符ではなくて新幹線そのもの)のどっちを買うかを比べるようなものだ。5GもWi-Fi 6のどちらもデータ通信を可能にする技術とはいえ、比較のしようもない。
スマートフォンでも4G、5Gとネットワークが高速化しても無線LANの需要はなくならず、むしろ公衆無線LANサービスが可能な場所が増えているように、5GとWi-Fi 6のような無線LANは共存するものである。目的も利用方法も、そしてコストも違うものだ。
なお、この記事では、両者を区別するため、通信事業者が行う携帯電話ネットワークサービスを「5Gサービス」と表記して「ローカル5G」と区別する。単に「5G」と表記した場合には、5G技術全体を指し、運営方法などを含まないことに注意されたい。
5Gの技術的な解説については、Tech Basics/Keyword「第5世代移動通信システム『5G』とは」を参照していただきたい。
ローカル5Gとは
ローカル5Gの本質的な部分は、法令の改正である。技術的には、ローカル5Gは、5Gそのもので、通信パラメーターなどの細かい部分を除けば、2020年春にも国内で提供開始が予定されている5Gサービスと何も変わらない。簡単にいえば、5Gサービスの開始に合わせ、自営の5Gネットワーク(つまりローカル5G)を、MNO以外でも開局できるように法令が変わるということだ。
ローカル5Gは、5Gの「高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)」「低遅延(URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)」「大量同時接続(mMTC:massive Machine Type Communications)」といった特徴を生かして、工場内でロボットやセンサーをワイヤレスネットワークに接続する、といった利用が考えられる。これにより、生産ラインを変更する際においてもネットワークケーブルの再敷設などが不要になり、フレキシブルな生産ライン構築が可能になるだろう。
ただし、注意が必要なのは、5Gは、高速通信、低遅延、大量同時接続を全て同時に満たす技術ではないことだ。つまり、このうちのどれを優先するのかをネットワークの構築時に選択する必要がある。
他にも空港やスタジアム、病院など、高速、大容量の専用ネットワークやセキュリティを確保した通信などが求められる場所での利用が想定できる。
ローカル5Gは基本的に土地の所有者がネットワークを構築する
日本でのローカル5Gは、土地の所有者(またはその委託を受けた者)が自身の土地で「自己土地利用」として、5G技術を使ってネットワークを構築するものを指す。例外として、自己の土地でないところ(他者土地)に基地局を配置することも可能なものの、さまざまな制限がある。基本的にはローカル5Gとは、自分の所有する土地内に基地局を配置し、自分の土地だけをサービスエリアとするものと考えていいだろう。
また、原則、土地の所有者がローカル5Gの免許を受ける「免許人」となる。ただし、業者にネットワークの構築、運営を委託する場合、その業者を免許人とすることもできる。
ローカル5Gのサービスエリアを他者の土地に設置して、免許を受けることも可能だ。ただし、この場合、端末は移動できない固定端末としなければならない。これにより、例えばローカル5Gを工場などの自己土地で利用しつつ、近隣のマンションなどの一定地域へワイヤレスインターネットサービスを提供するといったこともできる。ただし、ローカル5Gでは自己土地利用が他社土地利用よりも優先されるため、すでに自己土地利用が行われているエリアに他者土地利用のローカル5Gサービスエリアを設置することはできない。
法的な部分で重要となるのは、周波数割り当てや実施可能な地域、そして課せられる規制や今後の方向性だろう。
2019年末の時点では、28GHz帯のうち100MHz分が早期割り当ての対象として申請の受付が開始された。28GHz帯でローカル5Gに割り当て可能なのは、28.2〜29.1GHzである。このうち、先頭部分の100MHz分(28.2〜28.3GHz)だけが先行して免許申請が可能になっている。
 ローカル5Gが使用する周波数と導入スケジュール
ローカル5Gが使用する周波数と導入スケジュールローカル5G用には、4.5GHz帯の200MHz、28GHz帯の900MHzの割り当てが決まっている。ただし、これらの周波数帯は既存の無線局との調整が必要だ。そのためか、共用条件のはっきりしている28.2〜28.3GHzのみ、先行して免許申請を受け付けることになった(総務省 総合通信基盤局 移動通信課「省令等改正案の概要」[PDF]から引用)。
| 周波数帯 | 700MHz | 800MHz | 900MHz | 1.5GHz | 1.7GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| バンド番号 | 28 | 18/19 | 8 | 11/21 | 3 |
| NTTドコモ | 20MHz | 30MHz | 30MHz | 40MHz | |
| KDDI | 20MHz | 30MHz | 20MHz | 40MHz | |
| ソフトバンク | 20MHz | 30MHz | 20MHz | 30MHz | |
| 楽天 | 40MHz | ||||
| UQコミュニケーションズ | |||||
| WCP | |||||
| 地域/自営BWA | |||||
| ローカル5G | |||||
| 総割り当て帯域 | 60MHz | 60MHz | 30MHz | 70MHz | 150MHz |
| 3.9G(LTE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5G | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |
| ローカル5GとMNOなどへの周波数割り当て(1) | |||||
| 周波数帯 | 2GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 4.5GHz | 28GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンド番号 | 1 | 41 | 42 | 42 | n77 | n79 | n257 |
| NTTドコモ | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 100MHz | 100MHz | 400MHz | |
| KDDI | 40MHz | 40MHz | 200MHz | 400MHz | |||
| ソフトバンク | 40MHz | 40MHz | 40MHz | 100MHz | 400MHz | ||
| 楽天 | 100MHz | 400MHz | |||||
| UQコミュニケーションズ | 50MHz | ||||||
| WCP | 30MHz | ||||||
| 地域/自営BWA | 20MHz | ||||||
| ローカル5G | 200MHz | 900MHz | |||||
| 総割り当て帯域 | 120MHz | 100MHz | 80MHz | 120MHz | 500MHz | 300MHz | 2500MHz |
| 3.9G(LTE) | ○ | WiMAX/XGP | |||||
| 4G | ○ | TDD-LTE | ○ | ○ | |||
| 5G | 3G終了後 | 予定 | 予定 | ○ | ○ | ○ | |
| ローカル5GとMNOなどへの周波数割り当て(2) | |||||||
すでにNECや富士通、東日本電信電話(NTT東日本)、ジュピターテレコム、秋田ケーブルテレビ、東京都などがローカル5Gの免許申請を行っている。
また、セルラーシステムであるため、隣接するセル(サービスエリア)とは、異なる周波数を使う必要がある。しかし、ローカル5Gで利用できる周波数帯域が限られるため、一定地域内に開局できるローカル5Gの数には上限がある。
今後は、28GHz帯の残りの部分と、4.5GHz帯も割り当てが開始される予定だ。ただし、4.6〜4.8GHzは屋内専用となる可能性が高いとされている。無線LANでも利用されている5GHzに近い、この周波数帯は衛星通信で利用されており、影響を最小にする必要があるからだ。
ノンスタンドアロン構成とは
現状、5Gのコアネットワーク(制御装置や交換機などを含む基幹のネットワーク)は、MNOも構築できていないため、ローカル5Gを2020年にスタートさせる場合、既存4Gネットワークを利用する「ノンスタンドアロン」(NSA:Non Stand Alone)構成を取る必要がある。
 ノンスタンドアロン(NSA)によるローカル5Gネットワークの構築
ノンスタンドアロン(NSA)によるローカル5Gネットワークの構築5Gのノンスタンドアロン構成とは、ネットワークの制御を既存4Gネットワークに任せ、5G基地局は、端末とのデータ通信のみを行わせる構成方法だ。5Gのネットワークが完成していない現時点では、ローカル5Gを開局するにはノンスタンドアロン構成を取るしかない。
NSAでは、端末の位置登録や制御などは4Gサービス側で行い、端末とのデータ通信のみ5G基地局が行う。
NSAで、コアネットワークを提供する4Gネットワークを「アンカー」と呼ぶ。アンカーには、既存のMNOのネットワークやすでに地域で運用されている4Gの「地域BWA(Broadband Wireless Access:広帯域移動無線アクセス)」が利用できる。さらにローカル5Gの免許人が4Gネットワークを「自営BWA」として開局し、アンカーとすることもできる。
つまり、ローカル5GをNSAで運用する場合、アンカーは、「自営BWAの4Gネットワーク」「地域BWAの4Gネットワーク」「携帯電話事業者(MNO)の4Gネットワーク」が利用可能だ。
全国で携帯電話サービスを運用するMNOと全国BWA事業者は、ローカル5Gの周波数割り当てを受けることもできず、自身のネットワークを利するためにローカル5Gを利用することもできない(ただし子会社は自己土地利用のローカル5G申請が可能)。
また、自営BWAの免許(周波数割り当て)も子会社を含め取得できない。ローカル5G、自営BWAともに周波数の割り当てがあり、すでに多くの周波数割り当てを受けている企業がさらに周波数割り当てを受けるには大きな制限がある。しかし、他者に対して、アンカーとして4Gネットワーク機能を提供することは可能だ。現時点で5Gネットワークやアンカーの構築経験を持っている企業はMNOしかない。
ローカル5Gが普及すれば携帯電話料金が安くなる?
ローカル5Gは、設備に多大な金額がかかることもあり、当初は、大企業の工場など、多量のIoT機器が集まるような場所での利用となるだろう。しかし、これが5Gの想定する用途の1つなのである。
例えば、工場にローカル5Gを導入することで、ロボットや大量のセンサーなどをケーブルレスで接続可能になり、ラインの変更などが容易になるなどのメリットがあるとされている。また病院などでも、外部のネットワークと接続せずに情報のやりとりが可能になることから、セキュリティの高いネットワーク構築が可能になる。スタジアムなどではローカル5Gを利用した情報提供を行うといったユースケースも想定されている。
先進国などを見れば、すでに携帯電話サービスの契約数は人口を超えており、これ以上、大きく成長するためには、IoTなどでの利用を拡大するしかない。ローカル5Gは、こうした「携帯電話」以外の用途を拡大するための1つの方策であり、5G普及の原動力の1つともなるものだ。このため政府が早期に法令整備を行い、2019年末から申請を受け付けている。
一般ユーザーにとってローカル5Gは直接関係するものではない。だが、ローカル5Gが普及することで、これまでMNOしか購入しなかった携帯電話設備機器がその他の法人などにも販売され、出荷台数も増え、量産効果によってコストが下がりやすくなることが見込める。これにより、MNOとしては5Gの設備投資額が減るので、より早く5Gを普及させやすい。さらに、一般ユーザーが5Gサービスに支払う料金も下がるかもしれない。期待したいところだ。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.
 ローカル5Gで大量のIoTデバイスを接続
ローカル5Gで大量のIoTデバイスを接続