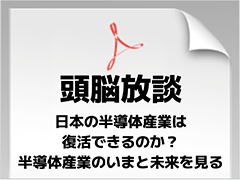第279回 欧米の半導体業界大手5社がRISC-V推進で新会社、どうするどうなる?:頭脳放談
欧米のそうそうたる大企業5社が共同でRISC-Vを担ぐ新会社の設立に向けて動き始めた。当面のターゲットは「車載」になるようだ。その背景や勝算、この企てに参加していない半導体ベンダーについて、筆者が想像を踏まえて解説する。
この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。
 欧米の半導体業界5社が共同でRISC-Vを推進する会社を設立
欧米の半導体業界5社が共同でRISC-Vを推進する会社を設立Qualcomm Technologiesのプレスリリース「Leading Semiconductor Industry Players Join Forces to Accelerate RISC-V」。欧米のそうそうたる大企業5社が共同でRISC-Vを担ぐ新会社の設立に向けて動き始めた。その背景を探る。
「Bosch」「Infineon Technologies」「Nordic Semiconductor」「NXP Semiconductors」、そして「Qualcomm Technologies」という世界的大企業5社が共同で新会社を設立するというリリースが流れてきた(Qualcomm Technologiesのプレスリリース「Leading Semiconductor Industry Players Join Forces to Accelerate RISC-V」)。ドイツ発のニュースである。
会社は正式に設立されたわけではないので会社の名称や本社所在地(ドイツということは確定らしい)、社長名、資本金といったもろもろは、発表には含まれていない。何せメンバーが大物ぞろいなので、各国の規制当局の承認待ちということである。
新会社の目的はRISC-Vコアの商用化の促進だ。このメンバーでドイツ拠点と聞いただけで、主となるターゲットは想像がつく。車載だ。実際にプレスリリースを読んでみると、最初にフォーカスするのは自動車になるだろうと書いてある。その後、モバイル分野やIoTといった分野に拡張するかも、といった方向性のようだ。
会社のビジネス形態は既に話し合っているのだろうが、今回のプレスリリースからはハッキリしない。ArmのようにIPベンダー的な行き方で各社にRISC-Vコアを供給することになるのか、それともエンド製品まで手掛けるメーカー的な行き方になるのか。ただ、各社の既存ビジネスとの整合性を考えれば、IPベンダー的な形態の方が穏当だと思うがどうだろうか。
RISC-Vを担ぐ新会社のターゲットはクルマ?
この大手5社が設立する新会社に対して、まずはメインターゲットである自動車メーカーが期待できるのかできないのか、勝手なことを考えていきたい。
ただし、筆者の車載デバイスの経験は浅い。民生品ばかりやっていたが、かなり昔に車載向けチップの担当者をやらなければならないことがあった。「常在車載」な経験者ならば呼吸のように身についているはずなのだが、そこは車載素人、各種の車載向け規格やら何やらの大量なドキュメント作成と会議に監査、正直「メンドクセー」と思ったことを告白しておく。
通例では、半導体ベンダーが付き合う相手は、自動車メーカーの本体ではなく、自動車向け電子装置を製造している部品メーカーだ。その中でも半導体の設計から絡むのは「Tier1」と呼ばれるような大手の部品メーカーであることが多い。
研究開発レベルでは自動車メーカー本体が介入することもあるが、実際に半導体を購入するのは部品メーカーであるからだ。車載業界の人々が半導体に何を期待しそうなのかホンワカ想像しながら書いてみたい。勝手な妄想かもしれないが……。
自動車メーカーは「車載ファースト」を求める?
自動車メーカーに対して「わがまま」というのは語弊もあるが、「自主独立」を求める割に、業界に共通する安全性、信頼性などの各種の規格は守らないわけにはいかず、リスクは最小化したい、でも最後はコストだ、という印象がある。その心は、矛盾しているというより、全方位ガンバレということなのかもしれない。まずはそういう観点で設立されるだろう新会社を考えてみよう。
自主独立というのは、対半導体会社相手の場合、自動車会社の開発戦略、製造戦略が半導体屋の都合やらロードマップなどに左右されたくない、とまとめられるだろう。
ロードマップを押し付けてくるような会社は、多分嫌われる。ましてやコロナ禍の半導体不足で痛い目にあった後である。自動車各社とも半導体メーカーとの付き合い方についてはいろいろ考えているだろう。
そこを考慮に入れるとき、「Bosch」「Infineon Technologies」「NXP Semiconductors」という欧州の車載向け電子部品、半導体の最大手が集っているのは安心感があるのではないか。特に欧州においては。談合して値段をつり上げるようなことにはなりそうにない(そもそも規制当局が審査しているので)。会社ができたならば、「車載ファーストで方針決めてくれるだろう」という期待を持たれるに違いない。
RISC-Vコアで車載業界標準ができる?
一方、少なくとも欧州や日本の自動車業界は、安全性、信頼性といった業界の「コモンセンス(常識)」な部分では、競争ではなく各社協調して各種規格を決めてくるのを通例としている。一人よがりな基準で突っ走ると後のリスクが怖い、ということもあるのかもしれない。
それら規格やらお作法やらの制定において欧州は、その策源地でもある。また近年、自動車におけるソフトウェアの比重が増えているのはご存じの通りだ。
新会社が開発するRISC-Vコアについても、各種のプラットフォーム、開発ツールその他、安全、信頼性から各種の情報伝達標準、ソフト作成のお作法に至るまで標準化に対応していることが求められるだろう。
そういう切り口で考えると、新たにできるRISC-Vコアというのは差別化の手段ではなく、車載業界の標準になるべきと考えられるだろう。このコアを採用すれば、必要なものが高いレベルで即座にそろい、それが異なるベンダー間でも相互運用できるという期待だ。そこまで標準化できると、導入できないと車載から振り落とされることになるかもしれないが。
チリも積もればロイアルティもかさむ
しかし、最後はコストなのである。昔、高級車で有名な自動車メーカーの人と会ったことがあった。高級車だからチップも高くて良いなんてことはサラサラなく、非常にコストを気にしていた印象だった。
車の末端価格に占める割合からしたら、個々の半導体の価格など微々たるものなんだが……。非常に多くの部品を組み立てる、つまりコストはそれら積算となるのが自動車だ。
半導体だけズブズブとはいかないのだ。確かに個々の半導体は微々たるものでも、1台当たりの半導体使用数量はどんどん増えている。クルマ1台当たりの半導体の数は何百、いや何千か(?)、いまや半導体コストは相当効いているに違いない。
そう考えるとArmに対するRISC-Vの優位性がちょっと見える気がする。Armの場合、製品1個1個にロイアルティが載ってくる。個別のライセンス契約によっては個々の金額はかなり抑えられているかもしれない。だが、あそこに1つ、ここにも1つと1台のクルマに相当数のArmマイコンが使われるとすると、ロイアルティだけでもかなりな金額になりそうだ。
自動車メーカーにしたら直接支払っているわけではないので、いったいロイアルティの合計がいくらになるのか計算もできないはず。部品メーカーから半導体メーカーへと流れるお金の一部が、最終的にArmに集約されるわけだ。
実際、1台当たりいくら位になるのだろう? 一方、RISC-Vであれば、今回設立されるであろう会社のビジネス方針によっては、ロイアルティを全然気にしなくてよくなる可能性もあると想像する。そういうビジネスの構図が描ければ、Armに対する新会社の優位性は決定的だと思うが。妄想だろうか。
新会社に参加していないベンダーはどうする?
この「来たる」新会社に対して関して、他社がどう反応するつもりなのか非常に興味がある。敵か味方か?
欧州半導体ベンダーで今回のリリースから抜けている会社、例えば「ST Microelectronics」はどうするのだろうか。
車載命という点では人後に落ちない日本の「ルネサス エレクトロニクス」はどうするのか。ルネサス エレクトロニクスもArmマイコンを欧州でも売っているし、RISC-Vコアのマイコンも手掛けているのだし、何もしないということはあり得ないだろう。
今回、米国勢からはQualcomm Technologies(およびNXP傘下には米国の元Freescale Semiconductorが含まれている)が名を連ねている。しかし、米国の他の半導体ベンダーはどう対応するのか。特に現在RISC-Vの輪の中心にいる感のある「SiFive」は新会社とは無関係でいるのか? (SiFiveについては頭脳放談「第254回 IntelがRISC-Vに急接近、でも組み込み向けは失敗の歴史?」参照)。
だいたいQualcomm Technologies自体、RISC-Vの車載向け応用にどのように関わる気なのだろうか。そして、Qualcomm Technologiesは、スマートフォン向けのRISC-Vプロセッサを出してくるのかも気になるところだ。
米国のマイコンの雄「Microchip Technology」は、新会社のRISC-Vプロセッサの攻勢にどう立ち向かうつもりなのか。また、Bluetooth分野の大手Nordic Semiconductorの現行機は、Armコアだと思う。だが、今回の企てにNordic Semiconductorが乗ることで、RISC-Vに乗り換えてしまうのかも気になる。
RISC-Vの商用化という点で先行している中国勢は、欧州でのRISC-V分野の大団結に対して、合従するのか、連衡するのか。台湾勢はファウンドリで関わるだけなのだろうか。でも、RISC-VのIP(回路設計データ)を売ってる会社が、台湾にいたはず。確かルネサス エレクトロニクスも買っていたと思う。
そして最強のIPベンタであるArmはどう対処するつもりなのか? 何も手を打たないということはないだろう……。
さらにIntelは、新会社のRISC-VコアをIntel Foundry Service(Intelのファウンドリ事業)で受けるのだろうか。
新会社が設立された暁には、何か発表される度に世界中で波乱が起きそうな雲行きだ。次の展開が気になる。規制当局の素早い判断を期待したい。
筆者紹介
Massa POP Izumida
日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部などを経て、現在は某半導体メーカーでヘテロジニアス マルチコアプロセッサを中心とした開発を行っている。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.