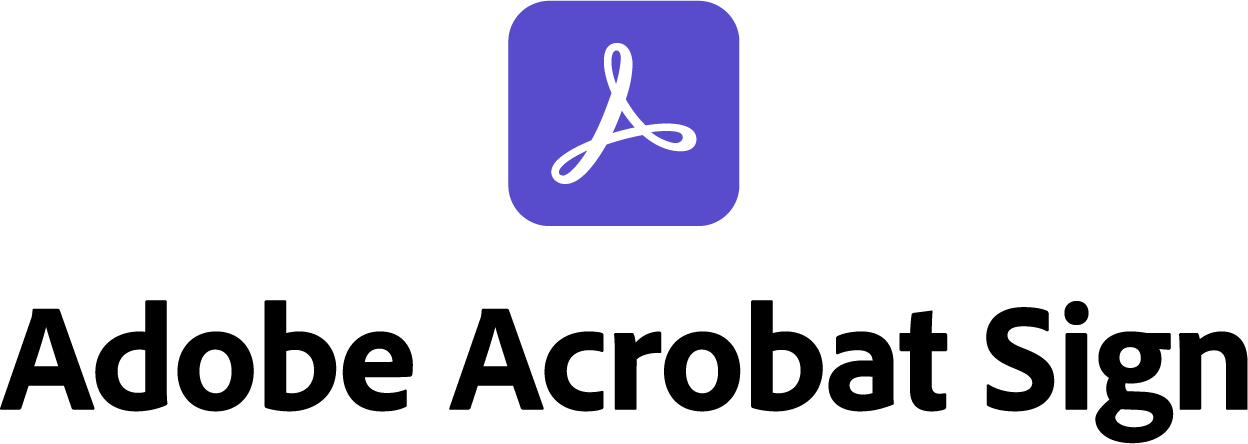電子契約が進まない理由とは?普及率やメリット・デメリット

目次を閉じる
- 電子契約の利用状況や普及割合
- 従業員数2人以上の国内企業における電子契約の普及率は約74%
- 業種業態によっては約44%が電子契約を導入していない
- 電子契約の普及が進まない理由やデメリット
- 取引先から理解を得ることが難しい
- 社内調整にかかる時間と手間を捻出できない
- 混在する書面契約との管理コストが懸念される
- サイバー攻撃やなりすましのリスクを許容できない
- 契約日のバックデートに対応できない
- 法対応への不安があり導入に踏み切れない
- 書面を利用する契約が多い
- 電子契約を導入するメリット
- 契約業務や書類管理にかかるコストを削減できる
- 契約業務を効率化できる
- セキュリティを強化して契約情報を守れる
- 契約のリードタイムを短縮できる
- テレワークや在宅業務に対応できる
- 電子契約をスムーズに導入するための注意点
- 安心感や操作性に優れたシステムを検討する
- 取引先にも導入メリットがあることを説明する
- 電子契約を一部でも取り入れ導入実績を作る
- 取引先や社内に説明会を実施し理解を得る
- 電子契約が進まない理由を解消して契約業務を効率化しよう
電子契約の利用状況や普及割合
電子契約の利用状況や普及割合は次のとおりです。広く普及しつつあるとはいえ、まだまだ拡大の余地がある状況といえます。
- 従業員数2人以上の国内企業における電子契約の普及率は約74%
- 業種業態によっては約44%が電子契約を導入していない
従業員数2人以上の国内企業における電子契約の普及率は約74%
2023年に行われたJIPDECの調査によると、従業員数が2人以上の国内企業では電子契約の普及率は約74%と大きく拡大しています。前年の数値よりも4ポイントほど上昇し、電子契約の普及はますます広がっています。※
多くの事業者がリモートワークを実施したことから、電子契約の利用率は大きく上昇しました。とくに、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置のため、リモートワークを行う企業が多かった2020年から2021年にかけての利用率上昇は、非常に大きかったと見られます。
※出典:JIPDEC「-JIPDECとITRが『企業IT利活用動向調査2023』の速報結果を発表-」(2025年1月16日閲覧)
業種業態によっては約44%が電子契約を導入していない
電子契約の全体での普及率は74%との調査結果がありますが、業種・業態によっては約44%が電子契約を導入していないとの調査結果もあります。
2023年にデジタル庁が行った「電子契約の普及状況等について」の資料では、「導入している(=自社主導の契約の場合に相手方に用いることを求める)電子契約システムはありますか」の質問に対して約44%の企業が「導入していない」と回答しています。※
つまり、電子契約を自社主導で導入している企業はまだ56%ほどで、電子契約を求められれば対応はしても、自相手方に積極的に電子契約を求める動きはしていない企業が44%も存在していると考えられます。
このように、電子契約は社会全体では広がる動きを見せつつも、まだまだ企業内では普及しきったといえる状況ではなく、導入が進まない企業も多いといえるでしょう。
※出典:デジタル庁「電子契約の普及状況等について」(2025月1月16日閲覧)

電子契約の普及が進まない理由やデメリット
電子契約の普及が進まない理由や、企業が懸念する導入デメリットとして次のようなものがあります。
- 取引先から理解を得ることが難しい
- 社内調整にかかる時間と手間を捻出できない
- 混在する書面契約との管理コストが懸念される
- サイバー攻撃やなりすましのリスクを許容できない
- 契約日のバックデートに対応できない
- 法対応への不安があり導入に踏み切れない
- 書面を利用する契約が多い
取引先から理解を得ることが難しい
取引先から理解を得ることが難しいとの理由で、電子契約導入に踏み切れない企業は多いでしょう。とくに紙契約を好む中小企業との取引が多い事業者では、相手方の理解を得ることがより難しいため、なかなか導入に踏み切れないケースもあるはずです。
取引先が電子契約に同意しない理由としては、電子契約の導入で発生する契約フローの変更の手間や、費用負担増加の懸念があるためです。これらの負担増加を懸念する取引先に電子契約を断られるケースがあり、多くの企業で電子契約の導入が進みません。
電子契約を含むすべての契約においては、契約方式の変更は契約相手の同意を得ることが一般的です。そのため、自社が電子契約に切り替えたとしても相手方の同意がなければ契約の電子化はできません。よって、電子契約を導入したところでその後の活用が難しいことから、電子契約を導入しない企業は多いです。

社内調整にかかる時間と手間を捻出できない
社内調整にかかる時間と手間を捻出できないことも、電子契約の導入が進まない理由の1つです。リソースが常に不足している中小企業では、電子契約を導入したくとも導入にかかる時間と手間を避ける人員がいないため、電子化ができていないところも多いでしょう。
電子契約は導入すれば業務効率化し、コストカットができます。しかし、導入時には社内調整が必要で、場合によっては契約フローの変更も必要になるでしょう。また、電子契約に同意してもらうために、営業担当は取引先に説明の手間もかかります。そのため、一時的に社内の業務負担が増加することを懸念して、電子契約に踏み切れない企業は少なくありません。
混在する書面契約との管理コストが懸念される
電子契約を導入した際の書面契約との管理コストを懸念して電子契約を導入しない場合もあるでしょう。電子契約と書面契約が混在することで、保管や管理に二重に手間とコストがかかるため、手間とコストを一元化して最小に抑えるために紙のままの契約書を選択するケースが多いからです。
電子契約を導入したとしても、一定紙の契約書は残るケースが少なくありません。たとえば、法的に紙による書面の契約を義務付けられている場合や、取引先によって電子契約の導入に同意してもらえない場合などです。
よって、電子契約と紙の書面による契約の併存は避けられず、それぞれにコストをかけるよりは従来の紙のままの管理に統一しておきたいと考える事業者は多く、結果として電子契約の導入が進まない場合は多いでしょう。

サイバー攻撃やなりすましのリスクを許容できない
電子契約におけるサイバー攻撃やなりすましのリスクを許容できず、電子契約の導入ができないケースもよくあります。紙の契約書と異なり電子データで契約情報を取り扱うことから、そのセキュリティに不安感を覚えて電子契約が導入できないとの声も多いです。
電子データで情報のやり取りをすることに慣れていない事業者では、このような点に不安感や不信感を覚えて、電子契約は導入できないと考えていることがよくあります。
実際は、二段階認証・二要素認証や権限設定、当事者型署名などにより紙よりも強固なセキュリティで契約締結が可能です。
契約日のバックデートに対応できない
契約日のバックデートに対応できないため、電子契約の導入を進められない事業者も多いです。タイムスタンプが付与されることで明確に契約日がわかるため、過去に訴求して効力を発揮する契約が締結できないと懸念する事業者は多いでしょう。
電子契約では、電子帳簿保存法(電帳法)への対応やなりすまし・不正な改ざんといったリスクへの対応を目的として、タイムスタンプを使います。タイムスタンプとは、契約が行われたタイミングで付与される電子データで、タイムスタンプがあることで契約の同意や契約データの変更がいつ行われたかなどが明確にわかります。
ただし、電子契約ではバックデートができないとの認識は誤解です。書面と同様に、双方が同意した合理的な多少のラグは問題ないと判断されることも多いため、バックデートが懸念で電子契約を導入できていない事業者は、電子契約システムを提供する事業者に相談しましょう。

法対応への不安があり導入に踏み切れない
電子契約に関連する法対応への不安があり導入に踏み切れない事業者も多いです。法対応は、事業者のみで行うと大きな手間がかかるため、その負担を許容できない事業者が法対応への不安から紙の契約書を維持するケースも多いでしょう。
しかし、電子契約システムを導入すれば事業者側での対応は最小限に抑えられます。電帳法を含め対応に不安がある場合は、契約システムの導入を前向きに検討しましょう。

書面を利用する契約が多い
書面を利用する契約が多い場合には、電子契約の利用は難しい場合が多いです。法改正により多くの書面の電子化が可能になった現在でも、書面による契約が義務付けられているものもあるため、そのような契約が多い事業者では電子契約の導入は難しいです。
これは法改正による電子化解禁を待つしかないとの見方もありつつ、一方で書面での契約が義務付けられていないものから電子契約を進めておき、将来の電子化に備えることも検討するべきです。
電子化ができるようになってから電子化の準備を始めると、法改正の対応と同時に電子契約の導入を行わなければならないため業務負担の増加が大きくなります。そのような事態を避けるためにも、電子契約はできるところから少しずつ導入し、完全に電子化できるようになったタイミングで迅速に対応できる状態を整えておくことが望ましいでしょう。

電子契約を導入するメリット
電子契約にはデメリットだけではなく次のようなメリットもあります。
- 契約業務や書類管理にかかるコストを削減できる
- 契約業務を効率化できる
- セキュリティを強化して契約情報を守れる
- 契約のリードタイムを短縮できる
- テレワークや在宅業務に対応できる
契約業務や書類管理にかかるコストを削減できる
電子契約を導入すれば、紙の契約業務や書類管理でかかっていた次のようなコストを削減可能です。
- 契約書や請求書といった書類作成のための紙代やインク代
- 書類を取引先に郵送する際にかかる封筒代や切手代などの郵送費
- 書類を管理するために必要なスペースの確保にかかる賃料
電子契約なら書類作成は電子データで行えるため、紙やインク代が不要です。また、取引先への共有もオンライン上で行えるため、郵送にかかる費用も削減できます。
さらに、電子データは保存に場所を取らず、クラウドサービスを利用すれば保存のためのサーバーも用意しなくてよいため、保管のためのスペースも不要になるでしょう。このように、紙で契約業務や書類管理を行っていたときにかかる費用の多くを電子契約で削減可能です。
契約業務を効率化できる
契約業務を効率化できることも電子契約導入のメリットです。電子契約であれば、紙の契約書作成で起きる記載ミスがなくなるため作成し直しの手間が減り、郵送のための封入作業や切手の購入作業が不要になります。
また、連携やテンプレート機能、定期発行機能によりすでにある取引先データから自動で契約内容を入力して作成できるものもあります。そして、書類データの共有はオンライン上で簡単にできるため、封入や投函の手間も削減して業務を効率化できます。
これまで紙の書面の取り扱いにより多くの非効率な業務が発生していましたが、電子契約を導入すればそのような業務も大きく効率化できるでしょう。

セキュリティを強化して契約情報を守れる
電子契約を導入すれば、セキュリティを強化して契約情報を守れます。電子契約システムなら多くのセキュリティ関連機能を搭載しており、紙の契約書に比べて高度な方法で契約情報を守れるためです。電子契約システムなら必要な人物にしか契約内容を閲覧させない権限設定や、印刷・ダウンロードを制限する設定があります。
さらに、契約書に対して行った閲覧や編集の操作履歴を残せるものもあるため、万全のセキュリティで契約情報の保護が可能です。外部からのアクセスに対しても二段階認証や暗号化技術を用いることで対応できるため、紙の契約書よりも強固なセキュリティで契約データを守れます。
契約のリードタイムを短縮できる
契約のリードタイムを短縮して、よりスピーディーに契約ができる点も電子契約のメリットの1つです。電子契約なら契約書作成はテンプレートを使えば簡単で、すべてオンラインで完了するため時間がかかりません。承認や確認についても、システム上のワークフロー機能を行いて簡単に回覧・承認・修正依頼ができるため、紙の契約書に比べて締結フローを早く行えます。
契約に関するさまざまな手順を簡素化できて、リードタイムを短縮できることも電子契約のメリットです。
テレワークや在宅業務に対応できる
テレワークや在宅業務に対応できるようになることも電子契約のメリットといえるでしょう。電子契約を導入すれば自宅で書類業務ができるようになるため、テレワークや在宅ワーク中にも業務が滞りません。
電子契約システムが普及する前は、書類業務のためだけに出社しなければならない人と、業務をすべてテレワークで完結できる人の間で出社格差が問題になっていました。出社格差のせいで従業員満足度が低下し、離職リスクを抱えることになった事業所も多くありました。
しかし、電子契約を導入することで、多くの従業員がテレワークや在宅で書類業務ができるようになり、出社格差の是正と従業員満足度向上を実現しています。離職リスクは経営において大きな課題のため、電子契約の導入によって離職リスクを低下させられることは、メリットといえるでしょう。

電子契約をスムーズに導入するための注意点
電子契約を導入する際は、次のような注意点に気を付けることでスムーズに導入が進みます。
- 安心感や操作性に優れたシステムを検討する
- 取引先にも導入メリットがあることを説明する
- 一部でも電子契約を取り入れ導入実績を作る
- 取引先や社内に説明会を実施し理解を得る
- 関連法令に対応したシステムを導入する
安心感や操作性に優れたシステムを検討する
電子契約システム導入を検討する場合、安心感や操作性に優れたシステムを優先的に検討しましょう。なぜなら、電子契約を導入する場合、取引先の担当者も利用することが多いからです。
取引先の担当者が電子契約システムを操作して、不安感が残る場合や使いにくいと感じた場合、システムでの電子契約に同意してもらえない可能性が高まります。せっかく費用と手間をかけて導入しても、取引先の同意を得られなければ電子契約導入の意味がありません。安心感や操作性に優れたシステムを導入して、取引先の同意も得たうえで電子契約を進めましょう。
取引先にも導入メリットがあることを説明する
取引先にも導入メリットがあることを十分に説明したうえで、電子契約の導入を進めることが必要です。取引先がメリットをよく理解できず、電子契約はよくわからないから導入できないと判断されてしまうと、電子契約導入のメリットが薄れてしまうためです。
取引先の電子契約に対する不安を払拭して快く電子契約の導入に同意してもらえるように、先方にも大きなメリットがあることを丁寧に説明しましょう。
電子契約を一部でも取り入れ導入実績を作る
電子契約を一部でも取り入れて導入実績を作ることも、電子契約の全面導入のためには必要です。電子契約の成功事例ができれば、その後の社内説明や取引先説明にも便利に利用でき、電子契約の普及につながるためです。
電子契約はここ数年で大きく利用率が上昇した比較的新しい仕組みのため、まだまだ利用に不安を抱えている方は多いでしょう。社内外を問わず、紙の契約書の方が法的効力が強く信頼できると誤解している方も少なくないはずです。
そのような方にも電子契約の導入実績を示すことで、電子契約が安全に利用できること、利用をすることで大きなメリットがあることを理解してもらえます。導入のための説明をスムーズに行う意味でも、一部からでも電子契約を取り入れて、その後の電子契約普及の足がかりにしましょう。
取引先や社内に説明会を実施し理解を得る
取引先や社内に説明会を実施して電子契約に理解を得る動きも大切です。オフィシャルな説明会の場を設けることで、会社全体として電子契約を普及しようとしていることを従業員にも取引先にも伝えられるためです。
できるだけ多くの契約で電子契約を取り入れるためには、社内で利用を積極的に推進し、多くの取引先の同意を取得しなければなりません。営業担当が取引先に電子契約の導入を促すためには、社内での丁寧なメリットの説明が必要です。
また、営業担当からの個別説明だけではなく、企業からのオフィシャルな説明会の場を設けることで、企業全体の意識として電子契約を推進していることが取引先にも伝わりやすくなります。
電子契約は営業部門だけではなく、契約書や領収書などを扱うすべての部署において便利に利用できるもののため、会社全体として電子契約を進める意識で導入に向けて動きましょう。
電子契約が進まない理由を解消して契約業務を効率化しよう
電子契約の導入が進まない理由はさまざまありますが、原因を解消して電子契約を導入することで契約業務は大幅に効率化できます。
取引先が電子契約に乗り気ではないことや、電子契約そのものや法対応への不安など、導入の際はさまざまな問題が発生する可能性があります。しかし、それらの問題を乗り越えて電子契約を導入できれば、業務を効率化できたりコストを削減できたりと多くのメリットを感じられるはずです。
電子契約の導入が進まない理由の多くは、努力によって解決できます。電子契約を導入して契約業務や書類業務の効率化をしたい事業者は、電子契約システムを提供する事業者にも相談しつつ、導入課題を解決してスムーズにシステム導入を行いましょう。

おすすめ電子契約システムの資料を厳選。各サービスの料金プランや機能、特徴がまとまった資料を無料で資料請求可能です。資料請求特典の比較表では、価格や細かい機能、連携サービスなど、代表的な電子契約システムを含むサービスを徹底比較しています。ぜひ電子契約システムを比較する際や稟議を作成する際にご利用ください。