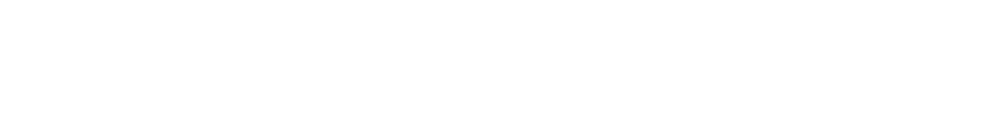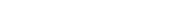食や健康、あるいはビューティー分野など複数の分野で、藻類の可能性に注目が集まっている。そうした中、藻類サプリメントや藻類調味料などユニークな藻類開発を進めている企業がある。2018年に創業した、東京大学発のバイオテックベンチャーである株式会社アルガルバイオだ。なぜ、藻類に対する期待が高いのか。代表取締役社長 CEOの木村周氏に話を聞くと、藻類の面白さ、そしてさまざまな課題解決のタネになる可能性が見えてきた。
研究者の肌感覚が生かされた藻類サプリ
――アルガルバイオが開発・販売している藻類サプリメントの「Moneru(モネル)」は、「CES 2023」でイノベーションアワード*を受賞しました。また今年(2023年)10月、新宿マルイ本館のポップアップストアでも一般にお披露目され、少しずつ消費者の目に触れられるようになってきました。藻類といえばクロレラが有名で、クロレラのサプリメントと言えば昔からいろいろとあります。そんな中で、Moneruを市場に投入した理由や狙いはどこにあるのでしょうか。
*米国ラスベガスでは、毎年1月に世界最大級のテクノロジーショーであるCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)が開催されている。このイノベーションアワードでは、デザインおよびエンジニアリングの面で特に優れている商品を表彰する。
木村氏(以下敬称略):Moneruの開発は、2016年ごろ、当社の創業者の竹下毅(現・同社取締役CSO=Chief Scientific Officer)が東京大学大学院時代に藻類の研究をする中で、「AL-0015」とナンバリングしているクロレラの株に注目したことがきっかけです。
といっても、当社はクロレラだけに注目しているわけではありません。もともと、竹下も在籍していた東京大学での20年以上にわたる微細藻類※に関する研究成果をもとに創業したバイオテックベンチャーですから、クロレラに限らずさまざまな藻類を研究しています。
その中でもAL-0015株は、他の藻類やクロレラの他の株に比べて非常によく生育するなど特徴を持っていて、竹下は「この株は何か違う」と研究者の肌感覚で感じていたようです。そこで医薬品やサプリメントの素材として機能性について調べてみたところ、他の藻類に比べて炎症を和らげるような特徴も持っているということが近年分かってきました。
*微細藻類:大きさ1ミリメートルから1マイクロメートルほどの生物。多くが光合成を行い、水中で植物プランクトンとして生活する。地球の大気に含まれる酸素の約半分を生成し、タンパク質や脂質、炭水化物、ビタミンなどさまざまな栄養素を作りだすことができるため、産業的な利用が期待されている

その一方で、ストレスや睡眠にまつわる悩みなど、現代ならではの健康課題に対して、睡眠薬以外に確固たるソリューションはまだ確立されていません。睡眠薬は即効性があるけれど、日中に服用すると眠気が出ることもよくあります。その点、藻類由来のサプリメントは食品ですから睡眠薬のような副作用の心配はありません。
こうした背景から、「良質な休息」に焦点を当てて開発したのが「Moneru」です。体感は人によってさまざまですが、アンケートにご協力いただいた方の中には、「朝までぐっすり休息できる日が増えてきた」「朝のスッキリ感が出た」というような感想も。具体的なメカニズムについて、われわれもまだ解明を続けている段階ですが、解明を進めるほどに微細藻類の新たな可能性を感じます。

――食の分野における、藻類に対する期待感はどんな雰囲気ですか。

木村:特に欧州では期待感が高まっています。いくつか理由はありますが、1つ目はサステナビリティの観点です。藻類は光合成を行う生物ですから、太陽光や水、二酸化炭素といった再生可能な資源から、われわれが必要とする栄養素などの有機物を合成して増殖します。化石燃料のように資源が枯渇する心配がなく、食料を生産することができます。
2つ目は健康の観点です。 特に欧州の人々は健康志向が強く、食品の加工や保存、栄養補給などに使われる素材に、人工化合物を避けて天然由来の素材を探しています。
3つ目はおいしさの観点。「Umami」という単語が、うま味を表す言葉として世界のスタンダードになっているように、天然由来の栄養素や味わいを食生活の中で重視していくライフスタイルの浸透がかなり進んでいます。例えば、フランスの「エシレ」という有名なバターブランドでは、普通のバターと減塩バター、海藻入りバターの3種が定番商品です。海藻バターで白身のお魚をソテーして食べると、海藻の旨みや風味が加わりよりおいしく食べられるので日常的に使われているのです。
こうした背景もあって、当社は創業から6年目に入った今年、国内事業の体制が整ってきたこともあり、海外事業に注力しはじめたところです。
微細藻類が持っている、食材の味を引き出す「何か」
――昆布やワカメといった大型藻類だけではなく、微細藻類もうま味成分を作ることができるのでしょうか。
木村:はい。海藻由来のうま味成分は、昆布から発見されたグルタミン酸と呼ばれるアミノ酸が有名です。同じように、微細藻類もうま味に関わるアミノ酸を作りだします。実は、当社では今まさに、クロレラが原料の天然のうま味調味料を開発中で、来年(2024年)に試験販売する予定です。
いろいろと研究開発を進めていくと、クロレラはうま味成分そのものと、「食材のうま味を引き出す効果のある何か」も持っているようなのです。どうしてこんなに曖昧な言い方になるかというと、官能評価で差が確認されており、調味料を共同開発するシェフも「明らかに味に立体感が出る」と仰いますが、うまみを引き出す要素が具体的に何なのかわれわれもまだ解明しきれていないので、研究を進めているところなのです。
実際に私自身もいろいろな食材で試してみましたが、一番違いがよくわかったのが冷や奴でした。お豆腐に市販の普通のお醤油を使うと、味の強いお醤油に負けてお豆腐そのものの味わいが飛びがちで、しょっぱく感じてしまいます。かといって減塩のお醤油を使うと、今度は奥行きのない平べったい味になってしまう。
でも、クロレラが原料の調味料を使うと、塩分を足しているわけではないのに、大豆の風味や甘みが引き立ちながら、うま味も感じるんです。まさしく味に立体感が出る。カキ醤油のように、天然素材の出汁を加えたお醤油で食べる、ああいう感じに近いのです。
微細藻類の商品化で求められていること
――微細藻類の産業利用について、食以外にはどんな分野で期待が高まっているのでしょうか。
木村:当社では「健康」「食」「環境」の3つの領域を軸に事業を展開していますが、健康や食にも近しい「美」の領域もニーズの高さを感じます。例えば、わかりやすい素材として、抗酸化物質として有名なカロテノイドの一種であるアスタキサンチン。これも微細藻類から作ることができます。当社では、カロテノイドを大量に微細藻類に蓄積させる特許製法のバイオ技術を持っているのですが、微細藻類が作ったカラフルな機能性素材を何かに使えないかということで、健康食品や化粧品などお客様の引き合いの中からいろいろとプロジェクトが始まりました。
あとは、環境もニーズの高い領域です。非常にわかりやすい素材でいえば、藻類由来のバイオプラスチックやバイオ燃料ですね。今まで石油や天然ガスから作ってきた素材を、藻類を含めたバイオ由来のものに置き換えていく。他には、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みとして、藻類にCO₂を吸収させるCCUS*技術もあります。あと、藻類は水の浄化機能を持っているので、排水の浄化というテーマでも引き合いが多いです。
*"Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage”の略で、二酸化炭素(CO₂)を回収・貯留して有効活用するための取り組み
ただし、結論から言うと、バイオ燃料の実用化への道のりは遠く、まだ20年、30年と技術開発が必要な領域です。バイオプラスチックや排水の浄化は、バイオ燃料に比べると実用化は近いはず。ただ、プロダクトとして実装できているかというと、まだまだこれからです。

――微細藻類をプロダクトにしていく上で、何か優先順位はあるのでしょうか。
木村:先にも触れましたが、当社では、「健康」「食」「環境」の3つの領域を軸に事業を展開しています。プロダクトとして実装できるスピード感を考えた時には、まず健康での開発が最優先になります。商品化するのに、微細藻類から作った素材1キログラムあたり、大体数万円のコストをかけられる領域だからです。Moneruのような商品もまさにそうですが、まずは少量かつ高付加価値な製品開発をしていく。
その次に食です。食にもいろいろありますが、大まかに1キロあたり千円単位で素材が作れなければ商品化は難しい領域です。創業当初の当社は、素材1キロあたり数十万円の生産コストをかけていましたが、技術の進化によって今は1キロあたり数千円単位で作れるようになりました。来年、クロレラの天然調味料を試験販売できるのもこのためです。
最後に環境です。環境に関する事業はインフラに近いので、1キロあたり数百円、数十円とさらにコストパフォーマンスが求められる領域です。つまり実装に時間がかかる。ですから時間軸を踏まえて、健康、食、環境の順にプロダクト化していく予定です。
藻類の可能性をもっと生かせる未来に必要なもの
――微細藻類をプロダクトにしていく上で、どんな課題がありますか。
木村:世界には数万、数十万という種類の微細藻類が存在します。一方で、産業的に利用されているものは数十種類にすぎません。その理由は大きく2つあります。1つは、実用化に向けた大量生産の技術が追いついていなかったこと。もう1つは、「いかに効率よく目的の生産物や商品を作っていくか」という点で、これまでのビジネス的なアプローチに偏りがあったことです。
――それぞれ、ご説明を伺います。まずは1つ目、実用化に向けた大量生産の技術が追いついていなかったということですが、アルガルバイオで取り組んでいる方向性について教えていただけますか。
木村:微細藻類を大量生産するには、製法自体をより良くしていくことと、 生産に使う株の生産性を良くしていくことの2点が重要です。
製法に関しては、技術の進化によって見通しは立ってきています。われわれの技術開発も次のステージに進んでいて、小さな試験管の中で培養するのではなく、大型のチューブ式培養装置を開発することで、1000リットル規模で微細藻類を培養できるようになりました。現在、装置は本社のある千葉県柏市から横浜市に移設していますが、それも研究開発体制をさらに拡充するため。素材1キロあたり数百円、数十円にしていくにはまだまだですが、いずれ解決できる問題です。
次の株の生産性については、大量生産に向く株の選抜が欠かせません。例えば、クロレラの同じ種であってもいろいろな株がありますが、他の株と比べて細胞分裂の速度が速いとか、細胞の径が大きいとか、生産した油脂やタンパク質を細胞内によりたくさん溜められるとか、そうした特徴の掛け算によって、株の生産性は2倍ほどの差が出てきます。ですから今後も、品種改良を目的とした育種に注力していきます。

――2つ目の理由は、微細藻類を使った生産物や商品を作るうえで、従来取られてきたビジネスでのアプローチには偏りがあった、とのご指摘でした。具体的には、どのような課題があったのでしょうか。
木村:藻類の産業化は70年ほどの歴史があります。ただし、バイオ産業を大きく捉えたとき、陸上植物は農業という形で、微生物は発酵産業という形でそれぞれ何千年もの歴史がありますよね。そういう意味では藻類の産業化はすごく遅れています。
藻類の産業化を牽引してきたのは主に米国、欧州、そして日本です。米国の場合は、国策としてバイオ燃料の開発に特化してきました。欧州では、もともとは微細藻類ではなく、昆布などの大型海藻の利用が産業化の始まりです。西海岸に打ちつけられる大量の大型藻類をうまく使えないかということで、化粧品や飼料などに利用してきました。日本では、戦後の食糧難の時代に、クロレラを栄養源として使ってみたらどうかというのが産業化の始まりです。
このように藻類は局地的に研究と開発が行われてきました。つまり、何十万種という藻類を横並びで比較して、それぞれどういう特徴を持っているのか、どういった分野の実用化に向いているのかという包括的な研究があまりなされてこなかったのです。
けれども、藻類の可能性を広げるという意味で、包括的な研究は欠かせません。当社では現在、遺伝子組み換えではない約70種500株の微細藻類のライブラリーを構築していますが、いずれも産業に利用できると判断し、選抜した藻類です。どのように使えるかまだ分からない研究段階の微細藻類は社内に数千株ありますが、今後も実用化という観点から、一つひとつの株が持つ可能性に目を向けていくことが重要だと考えています。

微細藻類から「おいしい素材」を求めて
――最後に、微細藻類によって可能になる近未来の食の姿を見いだすために、お伺いします。今後、食の分野で、微細藻類の可能性をどのように広げていきたいですか。
木村:大量生産に関しては、少しずつコストを下げながらクリアできてきているので、次の目標としては、「おいしい素材」を微細藻類から探すことですね。
例えば、肉の代替食品は大豆が原料の「大豆ミート」が有名ですが、藻類から採れるタンパク質を使って肉の代替食品を開発する取り組みも、世の中にはすでにいくつかあります。ただ、タンパク質をより多く細胞の中に溜められるという理由で、現在よく使われている「スピルリナ」という微細藻類は、正直なところおいしくない。苦みやえぐみが強い草を食べているような感じです。どんなにタンパク質の成分が多くても、やはりおいしくないと人は食べません。よりおいしい素材を求めて応用開発していくことが当面の目標ですね。そしてゆくゆくはお肉やお魚、乳製品を代替する食品素材の開発を進めていきたいです。
さらにその先で言えば、畜産や養殖に貢献できるエサの開発をしていきたいです。例えば、完全養殖*をするにも、魚に与えるエサは結局「生餌」と呼ばれる天然の魚を8割くらい使います。大豆などの植物性飼料を全面的に使うと、現状では養殖魚の味が落ちてしまうからです。
でも、本当の意味でサステナブルな「循環・共生型社会」へ転換していくには、再生可能な資源から作った飼料で、おいしい魚を育んでいく必要があります。環境への負荷が少ない形で、お肉やお魚を引き続きおいしく楽しめる未来のために、いずれプロダクトとして形にしていきたいですね。
*人工的に採卵・ふ化して育てた幼魚の一部を親に育て、採卵と稚魚の育成を行うことを「完全養殖」と呼ぶ