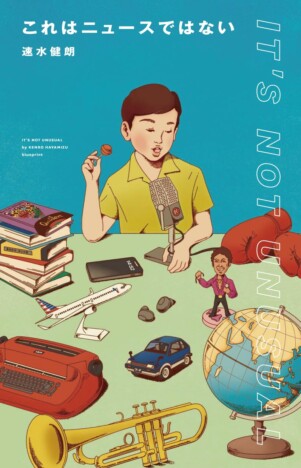『クレイヴン・ザ・ハンター』に湧いてくる無力感 フィクションを上回った現実の世知辛さ

裏社会の大物(ラッセル・クロウ)は、二人の息子を行き過ぎた“オンリー男らしさ教育”で育てていた。結果、兄のセルゲイ(アーロン・テイラー=ジョンソン/少年時代はリーヴァイ・ミラー)は父をクズ野郎だと強く自覚し、弟のディミトリ(フレッド・ヘッキンジャー/少年時代はビリー・バラット)は父に反発しつつ、同時に少しの憧れを持ち、なおかつ自分よりワイルドな兄にコンプレックスを抱く、厄介な青春期を送るはめに。しかし父のデリカシーはゼロ以下のマイナスで……。よりにもよって二人の母が精神を病んで自死したのに、父は二人をライオン狩りのためにアフリカへ連れ出す。そして案の定、セルゲイはライオンに襲われて重傷を負うのだった。三途の川を渡りかけるセルゲイだったが、たまたま通りかかった少女が魔法の薬をセルゲイに飲ませると……ライオンに受けた傷は癒え、それどころか身体能力が爆発的に向上する。かくして「力」を手にしてセルゲイは家出して、成長すると「クレイヴン」を名乗り、悪人を狩り殺すハンターとなる。しかし、運命は無情にも一家を地獄の再会へと導き……。
結論から書くと、本作『クレイヴン・ザ・ハンター』(2024年)は面白かった。映画史上に残るような特別な一本だとは言わないが、ヒーローの誕生ものとしては、しっかりと作られた映画である(※正確に言うとクレイヴンは『スパイダーマン』のヴィランなのだが)。何よりクレイヴンがちゃんとカッコいいのだ。高いところからピョンピョン飛び下りたり、ヘリコプターと真正面から綱引きしたり、獣のような人間という設定に合った絶妙なパワーとスピードが表現されていた。R-15ということで、情け無用の残酷ファイトが解禁されている点も好感度が高い。さらに身も蓋もないことを言うと、アーロン・テイラー=ジョンソンが単純にカッコいいのである。バキバキに仕上がった筋肉と、誰がどう見ても男前な顔面は、主人公の風格を漂わせている。本作は彼のスター力(ぢから)で持っている部分が大きい。
さらに、あらすじからも分かるように、本作はスーパーヒーロー映画でありながら、マフィア映画としての側面もある。圧倒的なカリスマを持つボスの父親、その下で育った正反対の道を選んだ兄弟と、一族を狙う新興勢力……。ロンドンの黒社会を舞台に、三者がそれぞれの思惑で戦いを繰り広げる。このマフィア映画的な切り口は面白いし、今回のメインヴィランとなるアレッサンドロ・ニヴォラの怪演も楽しい。
しかし一方で、盛り沢山すぎた感があるのも否めない。特に、クレイヴンのドラマをしっかりと描いているためか、アクションシーンの尺自体が少ないのが痛かった。中ボスの呆気ない退場や、ラスボス戦の一本調子感など、アクションの発想がいいだけに、あとはシチュエーションに工夫のある戦いが観たかったとは思う。父と兄弟の濃密なドラマに対し、ほぼ置き去りにされたヒロインのカリプソ(アリアナ・デボーズ)は、少し気の毒ですらあった。