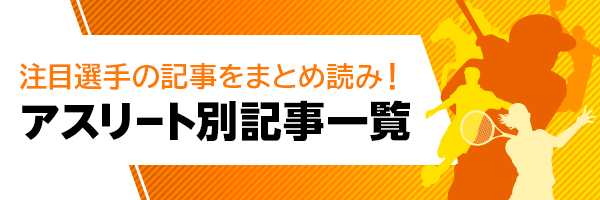なぜイチローは日常行動のほぼ全部をルーティーン化していたのか 50冊を超える取材ノートに書き留められたお宝発掘のヒント
51番を追いかけて〜記者が綴るイチロー取材の日々(後編)
休んでいる場合じゃない。そう痛感し、2009年以降のイチロー出場試合はすべて現場でカバーした。
きっかけは2008年終了後に読んだ某スポーツ雑誌の野茂英雄・引退特集号。そこでのインタビューで野茂が、「長い間、自分をずっと見てくれたメディアはいなかった」という意味の言葉を残していた。その発言に、自分がめぐり合った幸運にあらためて気づかされた。
 現役を引退した今もイチロー(写真中央)の取材を続けているという photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る
現役を引退した今もイチロー(写真中央)の取材を続けているという photo by Sankei Visualこの記事に関連する写真を見る
【イチローを取材できた幸運】
イチローはオリックスのドラフト4位から叩き上げでスーパースターへの階段を駆け上がり、日米で数々の記録とタイトルを打ち立てた。野茂の1995年ドジャース入り以降、米球界で活躍する日本人のほとんどがかつてドラフト1位の超有望株だった事実を考えると、彼のやってきたことは奇跡と言っていい。
そんな選手を取材できるなんて、自分にはそれ以上の奇跡じゃないか......。とにかくこのラッキーを最大限に生かし、彼の行動原理や思想をもっともっと知りたいと思った。シーズンオフには神戸や東京での自主トレに可能な限り顔を出した。少しでもそのすごさを感じてみようと神戸での自主トレ名物、「一段飛ばし階段ダッシュ」にも参加したりした。
ちゃんと数えたことはないが、イチローが日米で積み上げた4367安打のうち、その8割近くを現場で目撃したはずだ。練習を見つめた回数も、ほかのどのメディア関係者より多い。しかしその現役時代の最後まで、イチローが新たに取り組もうとしていたことを事前に見抜けなかった。
「あれっ? 去年と構えが違うよね」
毎年、キャンプのフリー打撃中やオープン戦の初め頃、何人かのメディア関係者がそんなふうにささやく。実際、イチローの打撃フォームは公式戦中も少しずつ変わっていく。だがそこで、それらの小さな変化が何を意味するのかを、そのたびに踏み込んで聞けるほどの度量、知識は自分にはなかった。
1 / 2
著者プロフィール
小西慶三 (こにし・けいぞう)
1966年大阪府生まれ。関西学院大学卒業後、1991年に共同通信社入社。1994年からオリックス・ブルーウェーブ(当時)を担当し、本格的に野球記者のキャリアをスタートする。その後、西武ライオンズ担当などを経て2000年12月、米ワシントン州シアトルに転勤。2001年に全米野球記者協会(BBWAA)初の日本人会員となる。イチロー氏の現役時代はオープン戦などを含め年間平均200試合近くを現場で取材。現在もシアトルを拠点にMLB取材を続けている