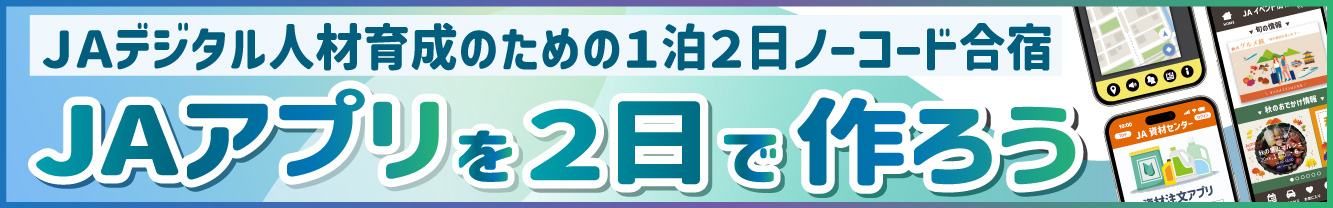[論説]能登半島地震から1年 国挙げて復興に全力を
幹線道路が背骨のように1本だけしかない能登は、地震による崩落や土砂崩れで道路が寸断し、集落は孤立した。いてつく寒さの中、断水や停電に加え、情報伝達の手段であるスマートフォンの電波が届かず、被災者の暮らしを直撃、被害の全容把握は難航した。畜産現場は、家畜の飲み水確保に長期間苦戦した。
奥能登で水稲の作付けができた面積は前年の6割、1800ヘクタールにとどまった。ため池や水路の応急復旧は県などが急ピッチで進めたが、業者が足りず、自力で修繕した農家らが大半だ。ただ、作付け後に見えない亀裂が見つかり、育たなかった稲もあった。
ローンを重ね、懸命に作った米だが、9月の豪雨が襲った。石川県珠洲市で米43ヘクタールを作付けする宮崎宜夫さん(78)は、投資や地震からの復旧で負債額が5000万円残る中、被災した。「むなしさしかない。もう逃げ出したくなる」。宮崎さんは吐露する。こうした現場の声に応えるのが政治の役目ではないか。災害に強い農業基盤の強化を含め、あらゆる手を尽くして能登農業の再開を支援したい。
行政も人手が足りず、被害調査や申請手続きなどが進まなかった。小さな農地や棚田が点在する能登では、自家消費用に米を作る小規模農家らが農地を耕し、里山の景観を守ってきた。草刈りや水路の掃除などを住民らが行っていた地域では、人口流出で管理作業もままならない。
過疎高齢化が進む中山間地域を襲った地震、豪雨災害は地域の“もろさ”を浮き彫りにした。だが、これで「農村をたためばいい」という論拠にはならないと指摘したい。
住民が減った能登では、ボランティアや二地域居住者らの「関係人口」が、復旧に欠かせない存在となった。千葉県在住で、定期的に能登を訪れて復興を支える小守幸恵さん(41)は「距離が遠くても応援したい気持ちを持つ人は多い。私が仲介役となり知人を連れていくことで支援の輪を広げられる」と話す。住んでいなくても、思いを寄せる人の存在が、復興の支えになる。県が復興計画の重点項目に「関係人口」を位置付けた初のケースになった。
全国に先駆けて過疎高齢化が進む能登は、農村の未来を先取りしている地域といえる。能登の復旧・復興は、国全体の問題として捉え、関わりを持ち続ける必要がある。
 Line
Line