とかく無味乾燥した暗い内容になりそうなテーマを、冒険小説を味わうような作品に仕上げている。著者の才能、翻訳者の力量はかなりのもの。単なるレポートにならず、深い内容になっているのは、著者のルーツ探しの旅を重ね合わせているからだろう。登場するひとりひとりが丁寧に描かれている。著者は傍観者ではなく当事者として、部外者ではなく関係者として、暖かい視線で見守っている。それは、登場人物のひとりの里帰りに、同行している事実からも明白である。先に刊行されたアレクサンドラ・ハーニーの「中国貧困絶望工場」とは、ひと味もふた味も違う文学作品である❣️
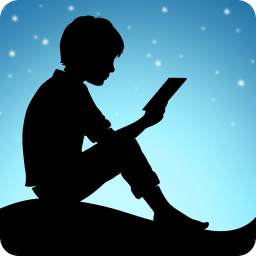
無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

現代中国女工哀史 単行本 – 2010/2/1
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
- 本の長さ459ページ
- 言語日本語
- 出版社白水社
- 発売日2010/2/1
- ISBN-104560080496
- ISBN-13978-4560080498
商品の説明
出版社からのコメント
《たくましく、したたかな出稼ぎ労働者たち》
本書は、「ウォールストリート・ジャーナル」の北京特派員だった著者が二〇〇四年から約三年間、空前の好況に沸く広東省中部の新興都市・東莞の巨大工場群で働く十代から二十代の女子工員たちに密着し、彼女たちの日常を克明に描いたノンフィクションである。
中国には、全就業人口の三割を占める、二億二五四二万人もの出稼ぎ労働者がいるという(二〇〇八年末現在)。ただし、出稼ぎとはいえ全員が故郷に帰るわけではない。そのまま都市に残り、定住する者も相当数にのぼる。このうち、本書に登場するのは、意地でも故郷に戻らない「定住組」の出稼ぎ女子工員たちだ。
劣悪な労働環境のなか、彼女たちはよりよい職場を求めて転職を繰り返す。長時間労働の合間に英語学校や自己啓発セミナーに通い、自らに磨きをかけることも忘れない。「たかが工員なんて言わせない」とばかり、少しでも上をめざして自分を叱咤し、どんな目に遭ってもめげず、ときには驚くほど大胆な行動に出る。
一方で、日中戦争、国共内戦、文化大革命で辛酸をなめた著者自身の一族の歴史についても語られる。三世代七十年に及ぶ激動の中国現代史である。国家への忠誠心ゆえに留学先の米国から帰国し、不慮の死を遂げた鉱山技師の祖父の姿と、東莞の出稼ぎ労働者の姿を重ね合わせ、改革開放を境に大きく変わったもの、変わらず残っているものを鮮やかに浮かび上がらせる。
本書は、「ウォールストリート・ジャーナル」の北京特派員だった著者が二〇〇四年から約三年間、空前の好況に沸く広東省中部の新興都市・東莞の巨大工場群で働く十代から二十代の女子工員たちに密着し、彼女たちの日常を克明に描いたノンフィクションである。
中国には、全就業人口の三割を占める、二億二五四二万人もの出稼ぎ労働者がいるという(二〇〇八年末現在)。ただし、出稼ぎとはいえ全員が故郷に帰るわけではない。そのまま都市に残り、定住する者も相当数にのぼる。このうち、本書に登場するのは、意地でも故郷に戻らない「定住組」の出稼ぎ女子工員たちだ。
劣悪な労働環境のなか、彼女たちはよりよい職場を求めて転職を繰り返す。長時間労働の合間に英語学校や自己啓発セミナーに通い、自らに磨きをかけることも忘れない。「たかが工員なんて言わせない」とばかり、少しでも上をめざして自分を叱咤し、どんな目に遭ってもめげず、ときには驚くほど大胆な行動に出る。
一方で、日中戦争、国共内戦、文化大革命で辛酸をなめた著者自身の一族の歴史についても語られる。三世代七十年に及ぶ激動の中国現代史である。国家への忠誠心ゆえに留学先の米国から帰国し、不慮の死を遂げた鉱山技師の祖父の姿と、東莞の出稼ぎ労働者の姿を重ね合わせ、改革開放を境に大きく変わったもの、変わらず残っているものを鮮やかに浮かび上がらせる。
登録情報
- 出版社 : 白水社 (2010/2/1)
- 発売日 : 2010/2/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 459ページ
- ISBN-10 : 4560080496
- ISBN-13 : 978-4560080498
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,064,307位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 136,836位社会・政治 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.7つ
5つのうち4.7つ
5グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ68%32%0%0%0%68%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ68%32%0%0%0%32%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ68%32%0%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ68%32%0%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ68%32%0%0%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
- 2014年6月30日に日本でレビュー済みAmazonで購入原題は「工場の少女たち、変わりつつある中国の村から都市へ」でした。
工場労働の描写はありません、村からでた少女たちのつく仕事もブルーカラーとホワイトカラーに分かれていき、後者が求られます。その一つの手段として「英語を学ぶ」があります。ブルーカラーから秘書や事務や教師などのホワイトカラーに変わろうとする少女たちの情熱は大きく、仕事後の学校通いに励みます。いったん都会にでた少女たちの意識変化は大きい。農村の父母を都会の目で見ます。彼女たちはもう農業体験すらありません。
そういう変化をよく追っていますし、それを取材する著者の中国アイデンティティ探索もそれなりに面白かった。しかしろくな教養も技術もないまま、夢を求めて職を転々とする少女たちの人生、若いがゆえに希望は見える。20年後にはどうなっているんだろう、とか思いました。
- 2010年4月15日に日本でレビュー済み中国語の勉強中で、興味があって読んでみた。
現在の中国広東省の工場で働く女性のノンフィクション、ドキュメンタリー。
とにかく上昇志向の強い彼女たちには「女工哀史」などとんでもない。
高い教育を受け、前に、前に進み、貪欲に上を目指し突き進む。
日本は経済大国からどんどん後進しつつある。
東アジアの中での不動の首位が、韓国や中国に抜かされようとしている。
恐らく、多くの日本人には彼女たちのような、非情なまでの個人主義はない。
だが、このたくましい強さが、人を国を高みへと導いていく。
この本を読んで、ただ圧倒されてしまうだけの自分。
情けないけれども、どうすることもできない。
- 2010年11月19日に日本でレビュー済み中国出身だが、アメリカで教育を受けた女性ジャーナリストが、華南地区の工場で働く出稼ぎ労働者の女性を通して、現代の中国女性の生き方や価値観を探るルポルタージュである。同時に、彼女にとっては自分や家族のルーツを探る旅でもある。邦題とは異なり、工場労働の現場の厳しさについての記述は少ない。そもそも工場の労働自体に関する記述が少ないし、表面的だ。
出稼ぎの少女たちには工場は明らかな通過点であり、関心は常に「これからどこに行くか」である。非常にたくましいというか、「信じられる物は自分だけ」という別の厳しい現実が描かれている。そして著者はそれぞれの生き方が、親の世代なら文化大革命による価値観の転換、現代では極端な商業主義と地域による貧富の差と、時代や設定は違うにせよ、中国人が出身や階級の違いに挑戦して、実力で生き延びていく点が同じであると理解するのだ。
日本でも「集団就職」という言葉が意味を持っていた時代は、同じような意欲があったと思う。現在でも、地方から東京に出てくる若者には見られるかも知れない。ただ日本では、そこそこの快適さが容易に手に入り、しかもそれで満足してしまうような「気持ちのぬるさ」がつきまとう。だから本書に出てくる少女たちの気持ちは理解できないかも知れない。どちらが幸せなのか、評価は将来決まる。
あくまで正業に生きる女性を継続的に追いかけているのが、やや不満ではある。実際には、安易な方向に流れていく人も多いはずなので、そういう例も取材をして欲しかった。同胞同性の目で綺麗なサクセス途上ストーリーにまとめられている気はする。






