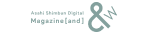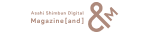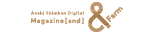「この戦、負けますね」 コロナ診る医師が描く医療崩壊
聞き手・熊井洋美
長野県で消化器内科医として働く作家の夏川草介さん(42)は、最前線で新型コロナウイルスに感染した患者の治療にあたってきた。その過酷な体験をもとに、小説「臨床の砦(とりで)」(小学館)を書き、4月に出版された。患者の死に防護服姿で泣き崩れる看護師、いつ濃厚接触者になるかわからない緊迫の日常――。著作に込めた思いを聞いた。
なつかわ・そうすけ 1978年大阪府生まれ。信州大学医学部を卒業後、長野県で地域医療に従事。小説家としては2009年、「神様のカルテ」でデビュー。同作は10年の本屋大賞で第2位に選ばれ、映画にもなった。
――本を書くきっかけは。
1月の中~下旬から2月初旬にかけて執筆したのですが、当時、病院には見たことがない風景が広がっていました。
修羅場というか。
「これは日本の医療なのだろうか」という景色をたくさんみているなかで、医者として正しいことをしているのか、という自分自身の壁にぶつかり、悩んでいることをまとめる、という作業を始めた次第です。
中等症の患者 みとる状況も
――病院の「修羅場」とは、どんな状況ですか。
ほかの病院で診察を断られた…