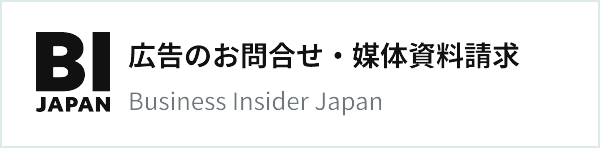※この記事は2022年7月22日初出です。
2022年7月21日、中国の電気自動車(EV)メーカー、BYDの日本法人BYDジャパンが、日本でEVの販売を開始することを発表しました。
また、7月14日には、リチウムイオン電池を開発するパナソニックエナジーが、アメリカのカンザス州に新たな車載用のリチウムイオン電池工場を新設する計画を発表。この工場は、アメリカのEV大手、テスラ用の電池製造工場だと見られています。
脱炭素化の流れの中で普及が加速するEV。そこで欠かすことができないのが「電池」です。
EVだけでなくパソコンやスマートフォンなど、いまやありとあらゆる電化製品に使用されている「リチウムイオン電池」。私たちの生活は、リチウムイオン電池なくしては成り立ちません。
その一方で、リチウムイオン電池には可燃性の材料が使われていることから、大容量の電池が必要とされる電気自動車用の電池として利用する上では、一定のリスクがあると言われています。こういった背景もあり、これから先、特に自動車業界では、リチウムイオン電池に代わる「新しい電池」が求められています。

その最有力候補と言えるのが「全固体電池」です。
2020年8月には、トヨタ自動車が全固体電池を搭載した自動車でナンバーを取得し、試験走行を実施しました。トヨタは、2020年代前半にも全固体電池を商用車に投入するとの方針を示しています。またこの4月には、日産自動車も全固体電池の試作生産設備を公開しています。日産自動車も、2028年に全固体電池の実用化を目指しています。
海外でも、フォルクスワーゲンやゼネラル・モーターズ(GM)、現代自動車など、多くの自動車メーカーが全固体電池の研究開発に力を注いでいます。
7月の「サイエンス思考」では、いま世界中が注目している「全固体電池」の基本と現在地について、全固体電池のブレークスルーに大きく貢献した東京工業大学の菅野了次特命教授に話を聞きました。
「リチウムイオン電池じゃ、だめなんですか?」

「全固体電池」が次世代電池の最有力候補であるとは言ったものの、正直なところ、私たちが日常生活を送る上で、リチウムイオン電池に対して大きな不便を感じることはあまりないようにも思います。
そもそも論にはなってしまいますが、本当に次世代電池は必要なのでしょうか。
菅野教授に尋ねてみると「身も蓋もない話ですが、リチウムイオン電池でこのまま進んでも、多分良いんでしょうね」と、驚きの返答がありました。
「ただ——」と菅野教授は話を続けます。
リチウムイオン電池が実用化されたのは1991年。それから約30年にわたって研究開発が進められてきたことで、いまではEVの電池としても利用できるほどになりました。今なお研究開発は続いていますし、これから先も性能が伸びる期待はあります。しかし、では既存の性能の10倍になったり、今までにない使い方ができるようになったりするかというと、そういった劇的な進歩は難しい状況です。
言い換えると、技術の「限界」がある程度見えてきたわけです。
例えば、EVの「航続距離を延ばす」という観点で言えば、リチウムイオン電池をたくさん搭載すれば課題を解決することは可能です。ただ、電池を大量に搭載する上でコストがかさんだり、車体が重く、大きくなったりするという問題も出てきてしまいます。
脱炭素を中心としたさまざまな課題からEVが注目されるようになってきた現代において、「果たして次世代自動車はそれで良いのだろうか……」という考えが頭をよぎるわけです。
「こういった背景の議論があり、リチウムイオン電池を超える次の電池の必要性が、社会に認識されるようになりました」(菅野教授)
全固体電池が克服する、リチウムイオン電池の「弱点」

リチウムイオン電池は、鉛蓄電池やニッケル水素電池など、それ以前に開発されてきた電池と比較して高い電圧を出すことができます。社会にここまで浸透できたのも、その高い電圧が「画期的」だったためです。
それを実現できた最大の理由は、電池の重要な構成要素である「電解質」と呼ばれるパーツにあります。
電池は、大雑把に言えばプラス側とマイナス側にそれぞれ存在する「電極」と、その間をつなぐ「電解質」でできています。リチウムイオン電池以前に使われていた充放電できる電池(二次電池)では、基本的に電解質は「水溶液」、つまり水でした(正確にはイオンが溶けている水)。
水は、ある程度高い電圧をかけることで、水素と酸素に分解されてしまいます。そのため、リチウム電池以前の電池は、水を分解しない程度の電圧までしか実現できませんでした。それに対してリチウムイオン電池は、電解質に水溶液ではなく「有機溶媒系」の液体を利用することで、電圧の限界を超えたのです。
しかしその代償として、リチウムイオン電池に使われる有機溶媒系の液体は「燃えやすい」という弱点を背負っています。電池として優秀な性質を持つ一方で、使用環境への制約や、安全上の懸念が生まれてしまったのです。実際、質の悪いリチウムイオン電池が発火するような事故はたびたび報じられています。
全固体電池は、リチウムイオン電池が持つ、こういった弱点を克服できる電池だと考えられています。
全固体電池は、その名の通り電解質を含めたすべてのパーツが「固体」でできていることが特徴です。
発火するリスクもなければ、高温になって液体が蒸発してしまうことも、逆に低温で凍ってしまう心配もありません。劣化しにくく、リチウムイオン電池では必須とされる「液体を密封する機構」も不要です。また、エネルギー密度の向上も見込まれています※。
「(電解質を)液体から固体に換えるだけで、かなり使い方が広がるというのは確かだと思います」(菅野教授)
こうして、他の次世代電池の候補とともに、その研究開発は進んでいきました。
※理論的なエネルギー密度は電極の組み合わせで決まるため、電解質が液体でも固体でも変わりません。しかし、全固体電池では、リチウムイオン電池で必要としたエネルギー密度に関係のないパーツを取り除くことができるため、総じてエネルギー密度は上がると考えられています。
全固体電池が10年で躍進した理由

話を聞いてみると、全固体電池は非常に優秀な次世代電池候補だと感じるかもしれません。
しかし、2000年代の初めごろまで、全固体電池の次世代電池候補としての地位はそこまで高くはなかったといいます。というのも、そもそも電池として、EVなどの産業に応用できるほどの能力がなかったからです。
菅野教授は、当時の研究現場の状況をこう話します。
「次世代電池として、いろいろな電池が候補として挙がっていました。ただ、全固体電池も含めて、どれも実用化できそうでなかなかできない、という難しい状況だったように思います」(菅野教授)
研究室で可能性が実証された材料が、実際に産業に応用されるまでの道のりは、思った以上に長いものです。
「電池として動くものを見つけて、さらに特性を上げて、あるところまで達した段階で産業にその技術を受け渡し、実際の商品にしていくわけです。ただ、(実験室で成功することと)産業側が製品として仕上げるレベルにまで達しているかどうかの間には、ものすごくギャップがあります」(菅野教授)
大学や研究所などで開発されたさまざまな電池が「次世代電池」として期待され、メディアを通じて注目を集める一方で、このギャップを超えられる電池はなかなか登場しませんでした。
しかし2011年、菅野教授らによって、全固体電池の能力を飛躍的に高める可能性を持つ物質が発見されます。
それが、菅野教授がトヨタや高エネルギー加速器研究機構(KEK)との共同研究によって発見したLi10GeP2S12(LGPS=リチウム・ゲルマニウム・リン・硫黄)です。
高性能な電池を作るには、必要な電流を生み出すために「イオン※」が高速で移動できる(伝導性が高い)電解質が必要です。電池の電解質には、イオンの伝導性が高いものが選ばれます。
※イオン:電子の過不足により、電気を帯びた状態になった原子。リチウムイオンは、電子を失いプラスの電気を帯びたリチウム原子。

菅野教授らが発見したこの物質は、固体であるにもかかわらず、イオンの伝導率がリチウムイオン電池で使われていた液体の電解質に匹敵するほど高い数値を示しました※。この物質を全固体電池の「固体電解質」に活用することで、全固体電池の能力が飛躍的に高まったのです。
※固体であるにもかかわらず、イオンが液体内部と同じように動き回れる物質を「超イオン伝導体」と言う。
「全固体電池を作る上での最大の課題は、『電解質』でした。固体の中でイオンが液体と同じくらい速く動くことは通常はありえません。ただ、実際に電池を作ってみると、非常によく動いた。それを示せたことで、産業側の方々に『これはひょっとすると、大きくしていけるのではないか』と思ってもらえたのかもしれません」(菅野教授)
その後、菅野教授らはさらに材料探索や全固体電池の試作を進めました。
その過程で、固体でありながらイオン伝導性が液体よりも高い材料を発見したり、電池の構成が同じなら、電解質として液体を使うより固体を使った方が多くの電流を得られることを見出したりと、全固体電池の可能性を徐々に明らかにしていったといいます。
「電池を作る上で、本質的に液体を固体にする利点があることを基礎研究で明らかにしていきました。固体に置き換えるだけでも、それに伴ってこれまでとは違う世界が広がっているというのが、研究している我々としての実感です」(菅野教授)
「実用化」は熾烈な競争の始まりにすぎない

全固体電池は、菅野教授の発見から約10年で次世代電池の「筆頭」と言われるまでになりました。もちろん、それ以前にも研究は進められていましたが、ここ10年で「世界観が変わった」と菅野教授は話します。
トヨタや日産など、日本の自動車メーカーも試作品の開発を進めており、一見すると、実用化まで「あと一歩」のところにまで迫っているようにも見えます。
では、ここから先、社会実装を進める中で、どのような壁が残されているのでしょうか。
菅野教授は、
「世の中のデバイスは、実績のある電池に基づいて設計がなされています。そこに新しい電池を入れ込むには、システムを変えないといけません。ただ、今うまくいっているものを変える必要は本来はありません。新しい電池が入り込むということ自体が、非常に難しいんです」
と、社会実装をする上での難しさを語ります。
少なくともリチウムイオン電池の限界が見えている中で、産業界からの要求を満たせそうな水準に達している次世代電池候補は、現状では全固体電池が最も有力です。
しかし、EVは、いままさに世界に普及していく過渡期を迎えています。ここで導入された技術は、この先10年、20年という長期間にわたってEVを支える技術になるはずです。
「それだけの長期間を支え続けられる電池かどうかを判断しなければならない。私なら、ゴーサインを出すに当たって、ありとあらゆる事象を検討します。となると、そう簡単には判断できないように思います」(菅野教授)
トヨタや日産など、業界をリードしているメーカーは「全固体電池の実用化」という最後の一歩を踏み越えるタイミングに向けて、いままさにその技術を見極めている最中なのでしょう。
また、菅野教授は、仮に全固体電池が市場投入されたとしても、それは始まりにすぎないとも語ります。
「そこからが勝負です。電極や電解質の材料は、どんどん良くなっていくと思います」(菅野教授)

実際、いま、自動車メーカーが先行して開発している全固体電池は「硫化物系」の材料を使っており、水に濡れると有毒な硫化水素が発生するというリスクがあります。また、コスト的により安い材料の探索や、環境への悪影響を抑えられる材料を見つけ出すことも重要です。
一度実用化がなされれば、そこからはより良い材料を探索し、それを実装していく流れが一気に加速していくはずです。
「また、電池として世に出ると、当然いろいろな問題が起こります。電池の中で起きている反応をしっかり理解しなければ、問題の改善にはつながりません。要するに、そういった部分を解き明かす基礎研究は当然重要になってくると思います」(菅野教授)
全固体電池の分野では、日本は世界的に見ても非常に高い技術・研究力を持っています。10年、20年先も世界のトップを走り続けられるのか、これから先、その競争はさらに過熱していくことになりそうです。
(文・三ツ村崇志)