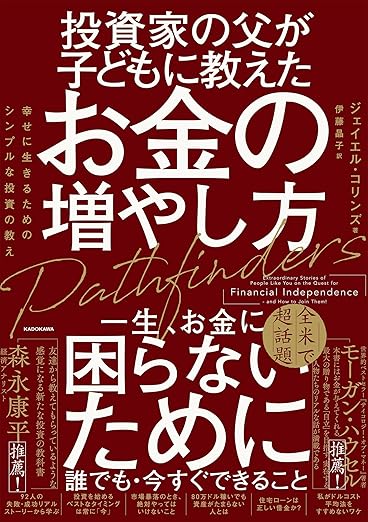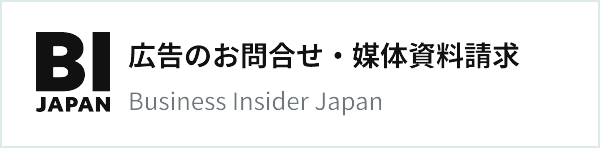アップルはMacBook ProおよびiMacの新製品を発表した。これらで使われているのが、同社の新プロセッサー「M3」シリーズだ。
アップルがMacに独自開発プロセッサを使うようになって3年が経過し、M1からM3へと世代交代している。
世代を追ってプロセッサーが性能アップしていくのはマーケティング上も当然のことで、そのこと自体に驚きはない。
だがよく見ると、無印・Pro・Maxという3つのバリエーションも、実は細部を見ると過去とは少し変わった状況がある。
取材のなかから見えてきたのは、アップルの新しい半導体戦略だ。
「M1からさらに進めた製品最適化」という考え方で、このM3世代のチップを作っているようだ。
「M3 Pro」から見えるM3の変化

今回アップルは3ラインのプロセッサーを同時に発表した。一般的な用途に向けた「M3」、プロフェッショナル製品向けの「M3 Pro」、そしてごく限られた人が求める水準の最高性能を実現する「M3 Max」だ。
無印・Pro・Maxという分け方自体は従来と同じで、おそらくはさらに上に「Ultra」があると予想はされるが、M3 Ultraはまだ発表されていない。従来は無印とPro・Maxは別のタイミングで発表されていたが、今回は3種類が同時発表となっている。
半導体の性能を測る指針の1つに「トランジスタ数」がある。
一般論として、1つの半導体に搭載されるトランジスタの数が多いほど性能は上がる。半導体製造技術の向上とは、「より多くのトランジスタを搭載した半導体を作れるようになる」ということでもある。
M3シリーズは、個人用PC向けとしては初めて「3nm(ナノメートル)プロセス」技術を使って製造されるプロセッサーで、微細化することによるトランジスタ数の増加=性能向上することが特徴だ。
次の表は、M1・M2・M3と、シリーズを経てトランジスタ数がどう増えたかを示すものだ。


M1に対してM3は1.56倍、M1 Maxに対してM3 Maxは1.61倍と大幅にトランジスタ数を増している。だがよく見ると、M3 ProはM1 Proに対して1.09倍しか増えていない。それどころか、M2 Proよりもトランジスタ数が減っている。
それでも、M3 Proの性能は、M1、M2を上回る処理能力がある。プロセッサーを構成する要素である「CPUコア」や「GPUコア」1つ1つの性能は上がっているので、性能全体は向上している。

単純な「価格順」の性能設定から、用途を想定した構成へ

なぜこのような「トランジスタを減らす」という変化が起きているのか?
筆者の取材によると、これは「そのプロセッサーが使われる製品の特質」が関係しているようだ。
M3 ProはM1 Pro・M2 Proと構造が変わっている。
現在のプロセッサーでは、メイン処理を担う「CPUコア」、グラフィック処理を担う「GPUコア」があり、それ以外に、AI処理や動画処理を担当する部分などがある。これらの中で、いわゆる「PCとしての性能」として語られるのはCPUコアとGPUコアの数だ。
さらにCPUコアについては、複雑な処理を得意とする「高性能コア」と、日常的で複雑ではない処理を低い消費電力でこなすのが得意な「高効率コア」があって、この2種類の組み合わせで動作している。
M1世代とM2世代の場合、ProはMaxの完全な「下位版」だった。すごく簡単に言えば、「メモリーとGPUコアの数が多い」のがMaxで、であり、少ないのがPro、という扱いだ。
それがM3世代では変わった。
M3 ProはM2 Proから高性能コアとGPUの数を減らし、高効率コアを増やしている。高性能コアやGPUコアはたくさんのトランジスタを必要とするので、M2 Proに対してトランジスタ数が減ったのだ。

結果として、M3 Proは「CPU性能はあまり上げず、GPU性能を上げた」プロセッサーになった。それでも、M3よりは性能が上になっている。
これはどうやら、M1世代のユーザーフィードバックを受けて、「Proを選ぶユーザーは、Maxほど性能は不要だが、日常的な処理の効率を求める」という分析があったらしい。
一方で、M3 Maxはとにかく最高性能になり、メインメモリーも128GBまで搭載可能になった。
M3 Max搭載製品は最低構成でも54万円近い「非常に高価なMac」だが、ノートPCでここまでの性能を備え、その気になれば生成AI開発にも使えるほどの大容量メモリーを搭載した製品は他になく、とにかく性能を求める人々には他に代え難い製品となっている。
円安傾向もあって全体的に価格が高めに見えるが、ドルで考えると、「価格と動作時間のM3」「M3よりは性能で有利だがM3 Maxより消費電力の低いM3 Pro」というすみ分けもはっきりしている。
M3世代は「高いほど性能がいい」というシンプルな構成から、「クラスごとに望まれる性能を想定してコアの組み合わせを変える」構成になった、と言えそうだ。



顕著な改善点はGPUに。生成AIも意識
では、M3世代全体で最も大きく改良された部分はというと「GPU」だ。
GPUコアの性能自体が上がったので、M3からM3 Maxまで、搭載しているGPUコアの量に合わせて性能も向上する。

3Dゲームなどの光の表現を高める「リアルタイムレイトレーシング」や、距離などに応じて3Dオブジェクトの精細感を変える「ハードウエアメッシュシェーダー」など、リッチな表現をより効率よく、低い消費電力で実現できる機能が特徴だ。CGのレンダリング速度は、M1とM3では2.5倍も向上しているという。
それだけでなく、「ダイナミックキャッシング」と呼ばれる機能もある。
通常GPUを使うような大規模な処理は、ソフトを作る段階で「GPUはこのくらいメモリーを使う」と指定して動かす。
だが実際には同じソフトの中でも、処理が重くメモリーを大量に使うタイミングとそうでないタイミングが存在するが、その差は考慮されず常に「最大の負荷」になりやすい。
M3ではメモリーの使用量を「作業が必要とする適切な量」だけ、自動的に割り振るようになる。これがダイナミックキャッシングだ。

ダイナミックキャッシングはゲームなどにも有効だが、生成AI学習にも有効と推察できる。最低でも74万円からとなるM3 Max+メモリー128GB搭載のモデルを買うような「覚悟が決まった方」にとってもうれしい機能になりそうだ。
生成AI開発もゲームも、やはりNVIDIA(エヌビディア)の高性能GPUを搭載したPCの方が有利な状況であるのは間違いない。アップルとしてはGPU強化を含めた改良で、状況を改善していこうと考えているのだろう。