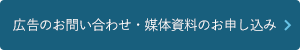三菱商事や三井物産、住友商事といった総合商社から、古河電気工業やフジクラといった大手メーカー、日揮に清水建設などのプラントエンジニアリングに長けた大企業。さらに、科学技術を社会実装するために大学や研究所を起点に生まれた数々のスタートアップ企業——。規模も業種も違う民間企業が、「世界と戦える核融合の実用化」の名の下に集結した。
1グラムの燃料から、石油8トン分ものエネルギーを生み出せるとも言われる「核融合」を、大企業からスタートアップまで、まさに総力戦で「日本の産業にする」取り組みが始まっている。
5月21日、国内の核融合産業に携わるプレイヤーたちの共同体であるフュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion、ジェイフュージョン)設立後、初めてとなる記者向け説明会が開催された。
J-Fusionの設立経緯とともに、核融合業界のここ数年の動きを振り返る。
核融合、研究フェーズから産業フェーズに
フュージョンエネルギー産業協議会の主要メンバー。
撮影:三ツ村崇志
J-Fusionは2023年に策定された政府の「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を踏まえ、この3月に設立した産業協議会だ。
会長を務めるのは、2019年に誕生した日本初の核融合スタートアップ・京都フュージョニアリングの共同創業者兼代表であり、京都大学で長年核融合関連技術を研究してきた小西哲之博士だ。
その他にも、副会長には住友商事の北島誠二執行役員と国内の核融合スタートアップとして核融合炉の建設を目指しているHelical Fusionの田口昴哉CEOが就任。常任理事には、プラントエンジニアリングで知られる日揮の藤原正彦執行役員、核融合炉の実現において欠かせない超伝導線材を製造する古河電気工業の森平英也社長が就任するなど、まさに大企業からスタートアップまで、属性も異なる産業領域のプレイヤーが「核融合の産業化」の旗の下に結集した形だ。
小西会長は、記者会見で
「ここ4、5年、世界中で核融合エネルギーを実用化しようという事業的な動きが高まっています。 地球環境・気候変動問題が深刻な状況で、フュージョンエネルギーの商業化を見据え、それぞれの国がどう産業を育てていくか、 そういうフェーズに入っています。
日本の企業として、フュージョンエネルギーを新たな産業として育てていこうという企業・法人が集まり、組織を作ることになりました」
と、J-Fusionの設立背景を語る。

京都フュージョニアリング創業者で代表を務める小西哲之氏。J-Fusionの会長を務める。
撮影:三ツ村崇志
小西会長が指摘する通り、核融合を取り巻く環境はここ数年で大きく変わってきた。
日本をはじめ、アメリカやEU、中国など7極の主要国の間では、長らく南フランスで進められている国際プロジェクトである国際熱核融合実験炉「ITER」を中心に、核融合発電の実現に向けた取り組みが進んでいた。その中でも日本には古河電工をはじめITERの主要部品を提供している素材・材料メーカーが複数あり、重要な役割を担ってきた。

フランスで建設中の国際熱核融合実験炉「ITER」の現場。施設面積は180ヘクタールほど。2020年11月撮影。
ITER Organization/EJF Riche
ただ、科学技術の進歩と共に、2010年代後半ごろから世界各国で核融合スタートアップが続々と誕生。イギリスやアメリカなどでは、独自に核融合発電の実現に向けた戦略を掲げる動きも増えてきた。
アメリカの核融合産業協会(FIA)によると、2023年の段階で核融合産業への民間投資は世界で約60億ドル(約9300億円:1ドル=156円換算)を越えているという。
「民間投資がいきなり(これまでの)10倍集まるようになった。研究開発の主役が民間に移ったわけです」(小西会長)
日本でもこの間、京都大学発の京都フュージョニアリング(2019年)を筆頭に、 核融合科学研究所と提携するHelical Fusion(2021年)、大阪大学の技術を起点としたEX-Fusion(2021年)、青色LEDの開発で2014年にノーベル物理学賞を受賞したことでも知られる中村修二博士がレーザー技術を生かして日米で設立したBlue Laser Fusion(2022年)、日大・筑波大学連合のLINEAイノベーション(2023年)といったスタートアップが勃興。政府も2023年に国家戦略の中で核融合(フュージョンエネルギー)の産業化を目指す方針を掲げ、J-Fusionの設立を後押しした。
5月21日段階で、J-Fusionへの加盟社数は発起人となった21社に加えて、特別会員の関西電力、正会員の出光興産、大林組、鹿島建設など、総勢50社にのぼる。手続きの関係上まだカウントできていない企業もあるとしており、今後しばらく加盟社数は増加することになるという。
J-Fusionでは、年2回の理事会を開催。安全規制、政策提言など目的別にWGを作り活動していくという。小西会長は、具体的な取り組みとして、国内外のフュージョン産業の技術動向調査、国内の技術マップの策定や海外機関との連携などを挙げる。特に人材育成ついては、
「これからのフュージョン産業を担う人材を育てていくことは世界的な活動です。 我々が乗り遅れると、日本の貴重な人材を外国に持ってかれてしまう、こういうような実は心配もあるわけです」(小西会長)
と危機感をあらわにした。
核融合の産業化へ、日本の存在感をどう高めるか?
核融合発電は、二酸化炭素(CO2)をはじめとした温室効果ガスを出さないうえ、原子力発電と異なり原理上、炉心溶融のような過酷事故の心配がなく、高レベル放射性廃棄物も生じないことなどが大きなメリットとされている。加えて資源に乏しくエネルギー輸入国である日本にとっては、エネルギーを「自給自足」できる可能性を秘めた技術としての期待も大きい。
一方で、核融合発電は古くから「夢のエネルギー源」として期待されていながら、いまだ実現した国、企業は存在しない。言ってみれば、まだ不確実性の高い技術だ。
ただ、技術革新によって時計の針は確実に進んでいる。民間企業の中には、例えばアメリカのHelion Energyが、2028年までにマイクロソフトへ核融合発電によって生み出した電力を供給する契約を結んだほか、MIT発核融合ベンチャーのCommonwealth Fusion Systemsも2030年代前半の実現を目指すなど、ここにきて「攻めた」目標を掲げている企業が増えてきた。日本でもHelical Fusionが2034年に核融合発電の実現を目指している。

ヘリオンエナジーの核融合エネルギー反応実験用プロトタイプ「Polaris」の一部。
Helion Energy/Handout via REUTERS
本格的な実現は、うまくいったとしても2030年代から2040年ごろであるという見方が強いものの、企業の言葉を信じるなら、かつて「30年先の技術」と言われていた核融合発電の実現が、5年先、10年先に迫ってきている。
世界では目下、そのタイミングでの産業化を目指した取り組みが進んでいるわけだ。日本としても、そこに合わせてサプライチェーンの構築を進めていかなければ、世界の核融合関連市場に乗り遅れてしまいかねない。
小西会長によると、すでに海外から核融合の関連機器の販売について、相談や注文が来ている企業もあるという。
こうした国際的にも需要のある技術を国内でしっかりと把握し、サプライチェーンとして世界へ展開する。課題は多いが、国内で核融合を産業化するためにも、
「今年中にまず全体で集まってどういう技術・課題があり、各会社がどう取り組んでいるのか分かる技術マップを制作するとともに、技術情報を見える形で双方に交換できるようなことをやりたいと思っています。
下手をすると呉越同舟となってしまいますが、どの会社が一番対応できるのか、そういったビジネス情報の交換を早々と始めなければいけない」(小西会長)
と、世界的なサプライチェーンの中で、日本の存在感を高める活動を進めていく必要があるとした。