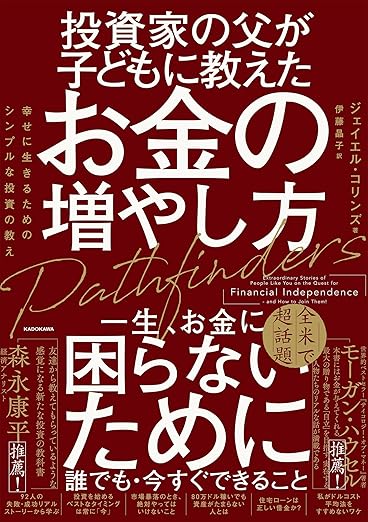財務省が1月14日に公表した2024年12月の「対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)」により、新NISA(少額投資非課税制度)導入に伴う「家計の円売り」の全容が明らかになった。
※家計の円売り……家計部門が保有する円貨性の金融資産を外貨性資産にシフトさせる動きを指す。例えば、日本の個人(投資家)が外国株を組入銘柄とする投資信託を購入する場合、円を売ってドルなど外貨を買う取引が発生するため、円相場を押し下げる(円安)要因となり得る。
「家計の円売り」の規模感を具体的に示す数字として注目されてきた投資信託委託会社等による対外証券投資は、2024年通年で11兆5069億円の買い越しだった。
2023年通年の買い越し幅(4兆5447億円)の2.5倍で、政府・与党が推進する「資産運用立国」の実現に向けた施策の効果が明確に表れた形だ【図表1】。

資本の海外流出を想起させる
2024年通年の対外証券投資に関して、投信委託会社以外の金融機関の動きも見ておきたい。
生命保険会社は2兆1200億円、銀行等および信託銀行(信託勘定)が8兆1554億円と、いずれも大幅な売り越しだった。前者は債券を、後者は株式・投資ファンドの持ち分を処分した結果だ。
一方、金融商品取引業者(証券会社に相当)は債券を中心に7兆2040億円の買い越しだった【図表2】。

上記を総合すると、2024年通年の対外証券投資は6815億円の買い越しという結果で、驚くほどの大きな数字ではない。
それでも投信委託会社等を経由した「家計の円売り」に注目が集まってしまうのは、キャピタルフライト(資本が海外に流出すること。多くの場合、経済への懸念や魅力の低下が背景にある)のイメージとの重なりがあるからだろう。
家計部門が保有する金融資産を長期的に海外に逃避させる意図で外国株を購入しているなら、そこでは(短期的な為替変動リスクを回避するための)為替ヘッジも想定されず、買い越し幅がそのまま円売りの規模として認識されるのも無理はない。
そうしたイメージの重ね合わせはあくまで想像の産物に過ぎないのだが、直情的な性質を備えた為替市場においては、そうした想像が事実を超えて影響力を持つケースが多々ある。
いずれにしても、上の【図表2】に示したように、投信委託会社経由の対外証券投資は2014年から23年の10年間で平均3.6兆円の買い越しにとどまっていたものが、冒頭で触れたように新NISA導入を経て3倍超の11.5兆円まで膨れ上がったわけで、それが為替市場における「新たな円の売り手」として注目されるのは当然と言えば当然のことだ。
「新NISA貧乏」の是非
さて、そのように話題を呼んだ「家計の円売り」は、2025年も続くだろうか。
10兆円超の買い越しが常態化するかどうかは別として、新NISA導入による非課税枠の新設がインセンティブとして働く限り、対外証券投資は今後も持続するに違いない。
しかし、近頃よく指摘される、有効に機能するインセンティブが存在しても、それを活用して投資に動くための(家計の)原資は限られているという問題は気になるところだ。
新NISA導入を受けて保有資産の多くを投資に振り向けたことで、消費を制約せざるを得なくなる事態、いわゆる「NISA貧乏」に陥る家計が出てきているという。そこまで切迫して原資が不足すれば、さすがに投資には動けなくなるだろう。
ただ、貧乏というワードが強すぎて真っ当な論理が吹き飛ばされている面もあって、冷静に考えてみれば、消費を抑制して投資に回す家計の判断が非合理的かと言うと、必ずしもそうとは言い切れない。
家計部門が行う資産運用は「投資」である以前に「防衛」の側面も大きい。何から資産を「防衛」しているかと言えば、もちろんインフレからだ。
2022年3月を起点とすると、円は対ドルで最大40%以上(最高値113円と最低値162円の比較)も下落している。
安全資産と見られてきた円を現預金で抱えているだけで、ドルに対する価値が4割も目減りする現実を目の当たりにして、自己資産に対する防衛本能が刺激された家計は少なくないだろう。
天然資源の90%以上、食糧の60%以上を輸入に頼る日本で暮らす以上、円安がもたらす輸入物価上昇の影響を回避するのは基本的に今後も不可能だ。
しかもその傍(かたわ)ら、株式市場では国内外を問わず史上最高値の更新が繰り返され、国内の不動産市場も活況を呈しているのだから、漠然とでも「何かしなくてはマズい」と不安を駆り立てられるのは無理もない。
そんなタイミングだからこそ、国が用意した新NISA導入というインセンティブは家計にとって投資に動き出す絶好の契機と映るだろうし、消費に回してきた現預金を株式などリスク性資産への投資へ、中でも円ではなくドルをはじめとする外貨への投資へ、と動くのは合理的な判断と言うほかない。
「貯蓄としての投資」
「NISA貧乏」というフレーズにはおそらく資産運用への過剰な傾倒をけん制する意味合いが込められていると思われるが、あまり適切な指摘とは言えない。前節で述べたように、家計の判断は極めて合理的なものだ。
デフレ下で現預金を「貯蓄」する行為も、インフレ下で株式や投資信託、不動産などに「投資」する行為も、経済・物価情勢に合わせた最適行動という意味では何ら異なるところがない。
少なくとも、投資のせいで「貧乏になっている(だから消費できない)」といった言説は本質的ではない。
新NISAを介した投資行動は「予備的な」動機に突き動かされたものと考えられ、その意味で、投資でありながら貯蓄の色合いを備えていると言える。
小泉純一郎政権の発足(2001年)以降、繰り返し「貯蓄から投資へ」の加速が推奨され、貯蓄と投資は互いを代替する(もしくは対立する)行為と理解されてきたフシがあるものの、実情として、昨今の家計は「貯蓄としての投資」を選好していると言えないだろうか。
※寄稿は個人的見解であり、所属組織とは無関係です。