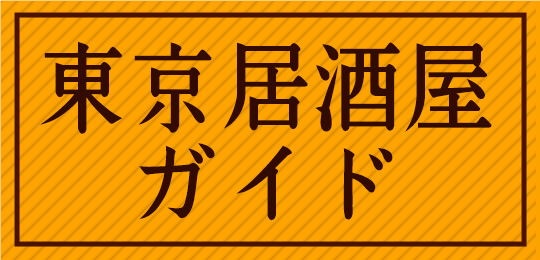①地理的表示(GI)法の本格始動による「食材のブランド化」
トレンド1つ目は、「食材のブランド化」。昨年6月から申請の受付が開始され、地域に根差した農林水産物・食品のブランドを保護する目的で施行された「地理的表示法」。2016年からの本格始動を前に、2015年12月22日には「夕張メロン」や「神戸ビーフ」を含む7つの食材が、初めてブランドとして承認されました。このように承認された食材は保護され、ブランドとしての価値を保つことができるようになります。
これにより、「夕張メロン」のように既に認知度が高い食材はもちろんですが、ここ数年でブランド食材として知られるようになった、北海道厚岸の牡蠣「カキエモン」や「マルエモン」、月に数十頭しか出荷できない宮崎の幻の牛肉「尾崎牛」のような、“知られていないけど実は良質な食材”が、GI法によって今後出てくることが予想されます。
このように、GI法によって「食材のブランド化」が進むことで、消費者は質の高い食材を選択することができるようになります。そして飲食店では、その食材に特化した専門店の増加や、食材を前面に押し出したメニュー強化などが進むと予想されます。

ここ数年でブランド食材となった幻の牛肉「尾崎牛」提供店舗:渋谷「ざぶとん」)
②インフラと成功例の顕在化で進む、クラウドファンディング×飲食店
トレンド2つ目は、震災復興をきっかけに日本でも浸透し始めている「クラウドファンディング」。「クラウドファンディング」とは「crowd(群衆)+funding(資金調達)」の造語で、ある志をもった人や団体に対する資金を、インターネットを通じて支援者から収集し実現する手法を指します。そんな「クラウドファンディング」が昨今では、飲食業界にも拡がりつつあります。昨年飲食特化型のクラウドファンディングプログラムが登場するなど、インフラが整ったことや、「クラウドファンディング」による飲食店開業の成功事例が顕在化したことで、元々飲食店開業に対して潜在的に熱意を持っていた方が動き始めており、今後“クラウドファンディング×飲食店”の動きは加速することが予想されます。
そもそも「クラウドファンディング」は「ホットペッパーグルメトレンド座談会」の調査では、女性より男性の方が認知が高く、20代男性では40人に1人がクラウドファンディングによる飲食店に投資した経験を持っているなど、若年男性を中心に広がりを見せています。(調査データは下図ご参照)
港区のカフェバー「ブルーバオバブ」というセネガル料理を提供するお店は、飲食業界未経験者のオーナーがどんな方でも気持ちが安らげるカフェを作りたいという想いから、クラウドファンディングで店舗を開業。精神科の先生を招いたセミナーを企画するなど、一風変わったスタイルで話題を集め、目標額を超える投資が集まりました。
このように、インフラの整備や成功事例の顕在化が後押しとなり、2016年以降は“クラウドファンディング×飲食店”の動きが加速すると予想しています。

クラウドファンディングで運転資金を集め、開業した「cafe bar Blue Baobab」
本文内使用データご参照
◆クラウドファンディングの認知有無

(単一回答)
◆クラウドファンディングによる飲食店の展開の認知有無

(単一回答)
クラウドファンディング×飲食店 事例①
うつ病の人を救いたい…飲食未経験で飛び込んだ私の想いを形にできた、クラウドファンディング
■Blue Baobab店長・下和田 里咲(しもわだ りさ)氏インタビュー
飲食店開業決意のきっかけ
システムエンジニア時代にうつ病の人が周りに多くいたことから、その人たちの救いになるようなコミュニティを作りたいと思ったことがきっかけです。ネット上でのコミュニティも考えましたが、数々の方々へのヒアリングから、「常設で気軽に行ける場所が欲しい」という意見から、対面コミュニケ―ションが出来る飲食店の開業を決定しました。
クラウドファンデングをしたきっかけ
ビジネススクールで「クラウドファンディング」があることを知りました。開店資金は自分で集めたものの、開業時に利用できるものは活用したいと思い、運転資金の一部を調達するために「クラウドファンディング」を活用しました。企業の立ち上がりを勢いよくするのに効果的だったと思います。
クラウドファンデングをする上で一番大変なことは?
プレッシャーが多いことですね。自分だけではなく支援者の想いを背負うために、銀行借り入れよりも大変です。そもそも、知らない人に「コンセプト」だけで共感してもらうことがとても大変なので、開業後のビジョンまで設計をし、しっかりと想いを持つことが大切だと思います。ただ、実施したことはお店の告知にも繋り、支援者がお店を身近に感じてくれるので、気持ち的な心強さは感じています。
どうして「バオバブ」なの?
共に働くアフリカ人スタッフから、アフリカには、暑くて乾燥して、他の植物が育たないような過酷な状況にも耐えて、周りの人たちに果実や、やすらぎを与えてくれる「バオバブ」の木があることを聞きました。そこで、自分の店も「バオバブ」の木の様なカフェになりたいと思い、店名に採用しました。
今後のビジョンは?
今年はうつの人のみならず、普通の人たちにも楽しんでもらえるイベントを実施することで、イベント運営の経験を蓄えていきたいと思っています。そして、来年以降は本来の目的である、うつで悩む人たち向けのセミナーも徐々に展開していきたいです。

下和田 里咲(しもわだ りさ)
神奈川県生まれ。システム開発会社でSEやプロジェクトマネージャを務めながらも数年後、十数年後の仕事に不安を覚え、ビジネススクールへ入学。ビジネススクール在学中に退職し、本ビジネスを立ち上げるために医療関係者やメンタル疾患のNPO関係者、カウンセラーなどから情報収集。2015年5月に合同会社を設立し、同年8月より飲食店「Blue Baobab」開業。
cafe bar Blue Baobab【神谷町/東京都】

東京では珍しいセネガル料理のお店。

家でくつろいでいるように感じられるアットホームな内装のため、外国人だけでなく日本人にも好評の店舗。
クラウドファンディング×飲食店 事例②
「この鯖で勝負したい!」鯖へのあくなき挑戦を後押しした、クラウドファンディング
■株式会社鯖や 代表取締役 右田 孝宣(みぎた たかのぶ)氏インタビュー
どうして鯖なのか
海外で飲食業を経験して帰国し、11年前に妻と始めた小さな居酒屋で好評だったのが鯖寿司でした。鯖を使った料理は幅広く、年間を通じて供給量もある。ずっと主役をはれるじゃないか、と思い「鯖へのあくなき挑戦」というポリシーを掲げて創業しました。さらに、鯖の種類はたくさんありますが、最高級の青森の八戸前沖鯖がいちばん美味しかったので、「この鯖で勝負したい」という思いで当初、青森に仕入れ先を求めました。
クラウドファンデングをしたきっかけ
経営が厳しく頭打ちになっていた頃、商工会議所の方からクラウドファンディングを教えてもらいました。資金調達にもなるし、消費者に鯖が必要とされているか等、マーケティングにも活用出来るという観点から、直感的に試してみようと思いました。
クラウドファンデングをしてみて実際どうでしたか?
「想いに共感していただくことさえできれば、意外と資金が集まるものなんだ。」と思いました。一般の方から出資を募るのでもちろん責任は感じましたが、一方でお店を開く前にファンが出来るため、心強さや安心感を同時に得ることができましたね。また、皆さんのお金で開業できているので、自然と「自分の店」という感覚ではなくなりました。俯瞰的に見ることができるから、今お店に何が必要かなど、第三者として判断ができるんですよね。
クラウドファンデングで一番苦労したことは?
事前のPRには力を入れました。クラウドファンディングの窓口会社が情報を出す前に、自社でも各所に情報を流すことで「SABAR」の注目度をあげ、窓口会社にも必然的にPRしてもらえるような雰囲気作りを頑張りましたね。あとは、開業後の資金繰りがとても大変です。通常飲食店では、3年間償却で資金を回すところ、SABARでは1年間で原価償却しなければいけませんからね。
どんな方にクラウドファンディングはオススメだと思いますか?
既存事業ではなく、新規事業を立ち上げる方にはオススメだと思います。マーケティングに活用いただくこともできますから。また、食材・産地など、専門性に特化した事業だとより良いかもしれませんね。なんにせよ、確固たる想いや軸をきちんともって、展開後までストーリーやビジョンを描けていれば大丈夫だと思います。
今後のビジョンは?
1年間かけて鯖の養殖をしているので、そこでのオーナー募集など、鯖にまつわる新しいビジネスの部分でクラウドファンディングを活用したいという思いはあります。SABARに関しては、鯖にこだわって国内では38店舗展開させたいです。また、夢物語かもしれませんが38か国に店舗を展開し、海外の皆さんにもトロサバの魅力をお伝えすることが出来るようになると嬉しいですね。

右田 孝宣(みぎた たかのぶ)
1974年、大阪府生まれ。大阪市立淀商業高校卒業後、魚屋に勤める。
とろさば料理専門店 SABAR 恵比寿店 【恵比寿/東京都】

東北近海(主に八戸、三陸沖)で獲れる、脂質含量が21%以上あるトロサバを使用したトロサバ専門店。

メニュー数はサバにちなんで38種類用意され、世界各国の料理でアレンジしたトロサバ料理を味わえる。大阪・京都の店舗とともに、予約が取りづらいほどの評判のお店。
「ホットペッパー グルメ トレンド座談会」とは
シーズン毎に“今”流行りの外食トレンドを発表する、株式会社リクルートライフスタイルの外食のプロフェッショナル集団。アンケート調査や、レストランの現場から“生の声”を聞き、「外食のリアル」を語ります。メンバーには、飲食トレンドの数値化・可視化を行うホットペッパーグルメリサーチセンター センター長や、食材と飲食店のマッチング事業も行っている一般社団法人「東の食の会」事務局メンバーなど、各ジャンルのスペシャリスト計6名で構成されます。