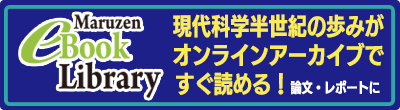今国内で巨大地震の発生が警戒されているのは,西日本の南海トラフや,北海道から三陸沖にかけての千島海溝から日本海溝北部,そして首都圏を中心とした関東地方の地震につながる神奈川県沖の相模トラフなどの地域だ。これらの場所で起こる巨大地震は,いずれも地下でプレートがぶつかり合い,重い海洋プレートが陸のプレートの下へ沈み込む際に起こる「プレート境界型地震」に分類される。文字通り,プレートの境界面で起こる地震だ。
なかでも,南海トラフにおける大地震はこれまで,およそ100〜150年の周期で発生してきた。前回の発生となる昭和東南海地震と昭和南海地震から約80年が経過した今,再び南海トラフで大きな地震が起こる時期が迫っていると考えられている。2024年8月8日には,同日発生した日向灘での地震を受けて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された。
巨大地震が警戒される地域で実際に大きな地震が起きた場合,「その地震がプレートの境界面がずれて起きたのか,プレート内部の断層によるものかを判断することが,その後の地震発生可能性の高まりを評価する上で重要だ」と防災科学技術研究所の地震津波火山ネットワークセンター長を務める青井真は指摘する。2024年8月8日に宮崎県で最大震度6弱を観測した日向灘の地震も,プレート境界面で発生した地震だった。
しかし,ここで大きな問題がある。下の模式図を見ると,プレート境界で起こる地震は,沖合で起きたものほど震源が浅くなることがわかる。ところが震源が陸地から遠く浅くなるほど陸上の各観測点で得られるデータは互いに似通ってしまい,震源を精度良く決定するのが難しくなるのだ。(図版は地震調査研究推進本部の資料などをもとに作成)

そこで,海底観測網の出番となる。実は今,南海トラフ一帯における地震活動を海底でリアルタイム観測するシステムの設置が急ピッチで進められている。2024年7月には,高知県沖〜日向灘の海底地震津波観測網「N-net」の半分が完成し,試験運用がスタートした。残り半分の整備も進み,年度内の完成を目指している。また,高知県の室戸岬の沖合では,海底の地層を深く掘り進み,地震の発生現場のすぐそばで岩盤の変化を観測する「長期孔内観測システム」の設置が2024年1月に完了した。これら観測網の整備は,私たちの地震への備えと理解に大きな変化をもたらすと期待されている。
詳細は日経サイエンス2024年11月号の誌面をどうぞ
お詫びと訂正
本文40ページ「プレート境界の浅部に着目」の記事につきまして,海上保安庁の研究成果を「2016年にScience誌に掲載された」としておりました箇所は,正しくは「2016年にNature誌に掲載された」でした(https://www.nature.com/articles/nature17632)。
お詫びして訂正いたします。
なお,後日販売のPDFについては,修正版を販売いたします。
協力 青井 真(あおい・しん)/荒木英一郎(あらき・えいいちろう)/平田 直(ひらた・なおし)
青井は防災科学技術研究所地震津波火山ネットワークセンター長。陸海統合地震津波火山観測網「MOWLAS」(モウラス)を統括すると共に,地震や津波に関するリアルタイム防災情報の研究を手がけている。荒木は海洋研究開発機構海域地震火山部門の地震津波予測研究開発センター観測システム開発研究グループリーダー。DONETや長期孔内観測システムの装置開発と設置,それらの観測データを用いた研究を手がける。平田は東京大学名誉教授で,政府の地震調査委員会の委員長を務める。
関連記事
「特集:超巨大地震に至る地下の変動」,日経サイエンス2019年2月号。
「フィリピン海プレートの動きを探る」,中島林彦,日経サイエンス2017年10月号。