追跡 中国流出文書 5 ~認知戦~

ことし2月、中国のサイバーセキュリティー企業の“内部文書”がネット上に流出した。シリーズでお伝えしている「追跡 中国・流出文書」。最終回は、文書の中で言及されていた、ある言葉に注目する。
「認知戦」
さまざまな関係者への取材によって、中国が進めようとしているサイバー空間での新しい戦いの姿が見えてきた。
(NHKスペシャル取材班/福田陽平・新里昌士・高野浩司・杉田沙智代)
「認知戦」
さまざまな関係者への取材によって、中国が進めようとしているサイバー空間での新しい戦いの姿が見えてきた。
(NHKスペシャル取材班/福田陽平・新里昌士・高野浩司・杉田沙智代)
「認知戦」の文字
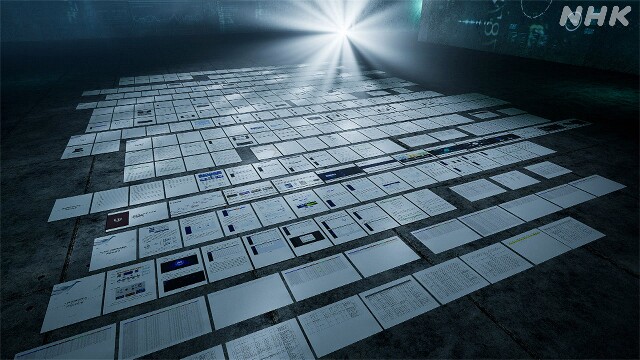
577点に及ぶ中国のサイバーセキュリティー企業、i-SOON社から流出したとされるファイル。文書の中には、公安=警察組織向けに開発されたという製品の説明書も含まれ、次のような一節があった。
「認知戦はますます注目され、世界情勢は静かに変化している」

この製品は「インテリジェンス」=重要な情報を大量に収集できるプラットフォームをうたっていて、こうしたシステムが開発された背景として、「認知戦」を優位に進める必要性が強調されていた。
認知戦とは、何なのか。
たとえば、NATO=北大西洋条約機構のリポートでは、ハーバード大学の研究を引用して「ターゲット層の考え方を変え、それを通じて行動を変えることに焦点を当てている」と紹介している。
さまざまな定義があるものの、近年では「SNSなどを用いて、人々の心理(認知)に働きかけ、相手の行動様式を変えていく手法」という意味で使われている。情報通信技術の発展に伴い、2010年代以降、ロシアなどの軍事大国が重視してきた。
認知戦とは、何なのか。
たとえば、NATO=北大西洋条約機構のリポートでは、ハーバード大学の研究を引用して「ターゲット層の考え方を変え、それを通じて行動を変えることに焦点を当てている」と紹介している。
さまざまな定義があるものの、近年では「SNSなどを用いて、人々の心理(認知)に働きかけ、相手の行動様式を変えていく手法」という意味で使われている。情報通信技術の発展に伴い、2010年代以降、ロシアなどの軍事大国が重視してきた。
カナダの情報当局で長年、諜報員として活動したミシェル・ジュヌ=カツヤ氏は、言論の自由が保障された民主主義国家にとって、大きな脅威だと強調する。

ミシェル・ジュヌ=カツヤさん
「認知戦はあなたの脳をターゲットとして操作し、どの情報を受け取るのかをコントロールしようとするものです。SNSといったメディアを通じて、数百万、数千万規模の人々に影響を与えることができます。つまり、銃弾を一発も撃つことなく、民主主義システムを覆すことも可能になるのです」
「認知戦はあなたの脳をターゲットとして操作し、どの情報を受け取るのかをコントロールしようとするものです。SNSといったメディアを通じて、数百万、数千万規模の人々に影響を与えることができます。つまり、銃弾を一発も撃つことなく、民主主義システムを覆すことも可能になるのです」
アメリカの「ランド研究所」で、中国の軍事戦略を研究するネイサン・ボシャンムスタファガ氏は、この認知戦に、i-SOON社のような民間企業の技術が取り入れられていると指摘している。

ネイサン・ボシャンムスタファガさん
「中国は、認知領域では、高度なコンピューティングや脳科学など、新しいテクノロジーを活用することに関心があるようです。i-SOON文書の事例からも民間企業を活用することに非常に興味を持っていることは確かです」
「中国は、認知領域では、高度なコンピューティングや脳科学など、新しいテクノロジーを活用することに関心があるようです。i-SOON文書の事例からも民間企業を活用することに非常に興味を持っていることは確かです」
抗議集会の「裏」にSNS
流出したi-SOON文書に記載されていた、情報窃取や世論コントロールのための技術は、この「認知戦」に活用されているのではないか。
私たちは、文書の分析から、市民の個人情報など、大量のデータが盗み出されていた可能性がある台湾に注目した。
私たちは、文書の分析から、市民の個人情報など、大量のデータが盗み出されていた可能性がある台湾に注目した。

「当局よ!対応しろ!」
去年末、台湾では、インドからの労働者受け入れに反対する抗議集会が開かれていた。人々の怒りの矛先は、政策を進めようとしていた当時の政権に向けられていた。

集会に参加していた女性
「多くの若い女性たちがインドからの労働者に対し懸念を表明しています」
「多くの若い女性たちがインドからの労働者に対し懸念を表明しています」
集会に参加していた別の女性
「政権は信用できません」
「政権は信用できません」

集会にいた多くが、若い女性たち。参加した理由を聞くと、一様に同じ答えが返ってきた。

集会に参加していた女性
「DCARDから活動を知りました」
「DCARDから活動を知りました」
集会に参加していた別の女性
「DCARDでたくさん話題となっていました」
「DCARDでたくさん話題となっていました」
「DCARD」。台湾の若者に人気のSNSのひとつだ。一体、なにが投稿されていたのか。
意図的な拡散か?

インターネット上の世論操作について分析する、台湾の調査機関「ダブルシンクラボ」。抗議集会に至るまでのSNSの動向をつぶさに調べた結果、ひとつの投稿にたどり着いたという。

林逢凱さん
「これが最初に広まったもので、最も注目されたものです。“インドから労働者を受け入れれば、台湾が性暴力の島になる”と書かれています」
「これが最初に広まったもので、最も注目されたものです。“インドから労働者を受け入れれば、台湾が性暴力の島になる”と書かれています」

それは、抗議集会のおよそ3週間前、インドからの労働者を受け入れれば、性暴力の増加につながると誤認させるような内容だった。
その2日後の11月15日。今度は、旧ツイッター、Xで、同調するような投稿が急増。

ダブルシンクラボが調べると、その多くが「ボット」と呼ばれるプログラムで操作されているアカウントだとみられたという。

こうした大量の投稿は、結果として、若者の不安をあおり、その後、受け入れに反対する投稿が相次いだ。

さらに、この事態をネットメディアが取り上げ、拡散。

同じ頃には、複数のSNSで、抗議集会への参加が呼びかけられていた。
調査したアナリストの林逢凱さんは、このケースは、中国側による「認知戦」の疑いがあると指摘している。その根拠のひとつとして挙げたのは、台湾では、使われない用語が多く使われていたことだ。
調査したアナリストの林逢凱さんは、このケースは、中国側による「認知戦」の疑いがあると指摘している。その根拠のひとつとして挙げたのは、台湾では、使われない用語が多く使われていたことだ。

林逢凱さん
「コメントの一部の用語は台湾では一般的ではありません。たとえば『盜竊』(盗難)という言葉は台湾では言わず、『竊盜』(窃盗)と言います。『缺心眼』(頭が悪い)も台湾の用語ではなく、中国の用語です」
「コメントの一部の用語は台湾では一般的ではありません。たとえば『盜竊』(盗難)という言葉は台湾では言わず、『竊盜』(窃盗)と言います。『缺心眼』(頭が悪い)も台湾の用語ではなく、中国の用語です」
さらに、内容にも、不審な点がみつかったという。

林逢凱さん
「コメントにはインド人を批判する否定的な内容が含まれるだけでなく、中国と協力したほうが良いという意見も見られました。つまり、情報操作を行っているのは中国である可能性があると私たちは考えています」
「コメントにはインド人を批判する否定的な内容が含まれるだけでなく、中国と協力したほうが良いという意見も見られました。つまり、情報操作を行っているのは中国である可能性があると私たちは考えています」
SNSの投稿をきっかけに「ボット」で人為的に情報を拡散し、人々の認知を変え、行動を促す。「認知戦」の一端が浮かび上がった。
社会の「くさび」狙う
中国の認知戦に関しては、台湾以外にも、世界の複数の調査機関から報告が上がっている。

アメリカのセキュリティー会社「マンディアント」のジョン・ハルクイスト氏は、その一例として、2021年4月にアメリカで見つかったケースを挙げた。
ネット上に出回っていた1枚の画像。
ネット上に出回っていた1枚の画像。

人種差別に抗議する4人の市民が写っていて、ひとりはプラカードを手に持っている。しかし、これは人種差別への抗議とは無関係の画像で、フェイクだった。
プラカードの内容は改ざんされ、投稿されたとみられている。
この時期はコロナ禍で、アジア系アメリカ人に向けて、人種差別に抗議するよう呼びかける投稿が急増した。英語だけでなく、日本語や韓国語などの複数の言語で行われ、数千の画像や動画などが投稿されたという。
プラカードの内容は改ざんされ、投稿されたとみられている。
この時期はコロナ禍で、アジア系アメリカ人に向けて、人種差別に抗議するよう呼びかける投稿が急増した。英語だけでなく、日本語や韓国語などの複数の言語で行われ、数千の画像や動画などが投稿されたという。
ジョン・ハルクイストさん
「これは非常に興味深いケースで、実際に人々を街頭に出すという物理的なイベントを作り出そうとしたのです。結果的には、誰も現れませんでしたが、写真を加工して、あたかも人が集まったかのように見せかけました。デジタル技術を使えば、物事をねつ造できるのです」
「これは非常に興味深いケースで、実際に人々を街頭に出すという物理的なイベントを作り出そうとしたのです。結果的には、誰も現れませんでしたが、写真を加工して、あたかも人が集まったかのように見せかけました。デジタル技術を使えば、物事をねつ造できるのです」
ハルクイスト氏は、中国が社会の分断につながる問題につけ込むことで世論操作を試みていると指摘し、警鐘をならす。

ジョン・ハルクイストさん
「標的とする国にくさびを打ち込むような問題を見つけ、攻撃しています。中国が目指すのは、政府やメディアが伝えていることを信じさせず、むしろ、陰謀論や社会が分断していると信じさせることです。デジタル空間を脱して、現実の世界で結果を生み出そうとしているのです」
「標的とする国にくさびを打ち込むような問題を見つけ、攻撃しています。中国が目指すのは、政府やメディアが伝えていることを信じさせず、むしろ、陰謀論や社会が分断していると信じさせることです。デジタル空間を脱して、現実の世界で結果を生み出そうとしているのです」
「オルタナティブ」というくさび
社会の分断を狙い、人々を扇動し、行動にまでつなげる。
こうした「認知戦」は、SNSが多様化しているいま、より容易に、効果的に実現できる状況が出てきている。
アメリカの調査会社「ピラ・テクノロジーズ」のエリック・カーウィン氏が警戒を呼びかけるのは、「オルタナティブ」=代替プラットフォームと呼ばれるタイプのSNSだ。
SNSでも、世界中に広くユーザーを持つ旧ツイッターのXやフェイスブックなどは、いわゆる「主流プラットフォーム」と呼ばれるが、近年、偽情報の拡散などを防ぐため、独自にポリシーを設け、投稿に一定程度、制限をかけていることが多い。
こうした「認知戦」は、SNSが多様化しているいま、より容易に、効果的に実現できる状況が出てきている。
アメリカの調査会社「ピラ・テクノロジーズ」のエリック・カーウィン氏が警戒を呼びかけるのは、「オルタナティブ」=代替プラットフォームと呼ばれるタイプのSNSだ。
SNSでも、世界中に広くユーザーを持つ旧ツイッターのXやフェイスブックなどは、いわゆる「主流プラットフォーム」と呼ばれるが、近年、偽情報の拡散などを防ぐため、独自にポリシーを設け、投稿に一定程度、制限をかけていることが多い。

一方、オルタナティブプラットフォームは、原則、自由で、制限を嫌うユーザーの受け皿となっていると指摘されている。
トランプ前大統領が主流プラットフォームのアカウントが停止された際も、独自のオルタナティブプラットフォームで発信を行った。
トランプ前大統領が主流プラットフォームのアカウントが停止された際も、独自のオルタナティブプラットフォームで発信を行った。

エリック・カーウィンさん
「主流のソーシャルメディアでは、一般的には、オープンに人種差別的な発言や極端な発言をすることはできません。それに対して、オルタナティブプラットフォームでは、自分が望むように発言することができる場として利用されているのです」
「主流のソーシャルメディアでは、一般的には、オープンに人種差別的な発言や極端な発言をすることはできません。それに対して、オルタナティブプラットフォームでは、自分が望むように発言することができる場として利用されているのです」
カーウィン氏は、こうしたオルタナティブプラットフォームが、人々を過激化させる要因のひとつとなっているとする。
例としてあげたのは、2021年に起きたアメリカ連邦議会への乱入事件だ。カーウィン氏によると、議会乱入のためのミーティングの計画、旅行や宿泊の手配、さらには武器の保管場所についての議論が、いずれもオルタナティブプラットフォームで行われていたという。
エリック・カーウィンさん
「そこでは多くの過激化が進行し、犯罪行為が計画され実行されています。ハッシュタグはXから始まっていたとしても、オルタナティブプラットフォームで取り上げられて過激化し、極端な形で広められ、最終的に主流メディアに戻ってくるのです」
「そこでは多くの過激化が進行し、犯罪行為が計画され実行されています。ハッシュタグはXから始まっていたとしても、オルタナティブプラットフォームで取り上げられて過激化し、極端な形で広められ、最終的に主流メディアに戻ってくるのです」
カーウィン氏は、こうした過激化しやすいオルタナティブプラットフォームが情報工作のターゲットにされることの危険性を指摘している。

エリック・カーウィンさん
「ただ種をまくだけで十分です。情報工作を行う組織や国家は、もはや大規模で複雑な活動を行う必要はありません。メッセージを信じる準備が整っている人々を見つけることができれば、一つのメッセージ、一つの加工された画像、一つの加工された音声録音を送り込むだけで十分な影響を与えることができるのです」
「ただ種をまくだけで十分です。情報工作を行う組織や国家は、もはや大規模で複雑な活動を行う必要はありません。メッセージを信じる準備が整っている人々を見つけることができれば、一つのメッセージ、一つの加工された画像、一つの加工された音声録音を送り込むだけで十分な影響を与えることができるのです」
オルタナティブプラットフォームを対象にした工作活動は、複数の調査会社が分析していて、中国側によるものと見られるとする分析結果も明らかにしている。
「元中佐」を直撃
中国によると見られる認知戦は、実際には誰がどのように行っているのか。
取材を進めていると、「認知戦」を担うとされる組織に属していた人物の情報がカナダから寄せられた。
ブリティッシュコロンビア州で、公安関係者の留学問題など、中国の脅威について取材を続けるグレアム・ウッド記者だ。
取材を進めていると、「認知戦」を担うとされる組織に属していた人物の情報がカナダから寄せられた。
ブリティッシュコロンビア州で、公安関係者の留学問題など、中国の脅威について取材を続けるグレアム・ウッド記者だ。

グレアム・ウッド記者
「その人物は中国の軍事アカデミーに20年以上所属している高位の軍人です。最大の懸念はサイバー戦争に関与している人物をカナダが受けれている可能性があるということです」
「その人物は中国の軍事アカデミーに20年以上所属している高位の軍人です。最大の懸念はサイバー戦争に関与している人物をカナダが受けれている可能性があるということです」

中国の人民解放軍「戦略支援部隊」の元中佐の男性。
男性は、いま、カナダに移住をしていて、その受け入れを巡って、地元で問題になっているという。
私たちは、元中佐がいるというカナダのウィニペグ市に向かった。
家の前で待つこと5時間。
犬の散歩のため、家から出てきた元中佐に声をかけた。
男性は、いま、カナダに移住をしていて、その受け入れを巡って、地元で問題になっているという。
私たちは、元中佐がいるというカナダのウィニペグ市に向かった。
家の前で待つこと5時間。
犬の散歩のため、家から出てきた元中佐に声をかけた。

取材班「あなたは●●さんですか?」
男性「あなたは誰ですか?」
取材班「私は日本のNHKの記者です。今は何をして暮らしていますか?」
男性「妻と暮らしています」
取材班「あなたは働いていないのですか?」
男性「はい」
男性「あなたは誰ですか?」
取材班「私は日本のNHKの記者です。今は何をして暮らしていますか?」
男性「妻と暮らしています」
取材班「あなたは働いていないのですか?」
男性「はい」
しばらくやりとりを続けたあと、私たちは、核心に触れる質問を投げかけた。

取材班「いつ人民解放軍をやめたんですか」
男性「その件はまとめて話します。一言、二言で片付けられません。弁護士と相談し、再度連絡します」
男性「その件はまとめて話します。一言、二言で片付けられません。弁護士と相談し、再度連絡します」
これ以上の回答を避けた男性。その後、連絡はなく、中国当局の思惑を直接問いただすことはできなかった。
「すでに戦争は始まっている」
一方で、中国の認知戦のいったんを知る人物に接触することができた。
人民解放軍海軍の元中佐、姚誠氏だ。
人民解放軍海軍の元中佐、姚誠氏だ。

6年前にアメリカに亡命し、現在は軍事研究家として活動している。
姚誠さん
「軍人どうしのチャット記録を私に共有してくれる人がいます。軍の中にはまだ親しい仲間もいて、共産党に不満を持っている人が多いのです」
「軍人どうしのチャット記録を私に共有してくれる人がいます。軍の中にはまだ親しい仲間もいて、共産党に不満を持っている人が多いのです」

姚誠氏によると、軍内部では、幹部の粛正が相次ぎ、不安定な状態になっているとみられ、そうした中で、武力に寄らない「認知戦」が、より重要な位置を占めるようになっていると分析している。

姚誠さん
「現代、そして未来の戦争において、情報化は、解放軍改革の要です。いまの西側諸国と中国との多くの問題の根本が、価値観や意識の隔たりにあります。そこで『認知戦』が重要になるのです。現在を正確に理解するなら、戦争はすでに始まっています。ただ目の前でミサイルが発射されていないだけなのです」
「現代、そして未来の戦争において、情報化は、解放軍改革の要です。いまの西側諸国と中国との多くの問題の根本が、価値観や意識の隔たりにあります。そこで『認知戦』が重要になるのです。現在を正確に理解するなら、戦争はすでに始まっています。ただ目の前でミサイルが発射されていないだけなのです」
わたしたちはどうするのか
私たちは「認知戦」にどう立ち向かえばいいのか。
取材の最後に「認知戦」研究の先駆者に、話を聞いた。
取材の最後に「認知戦」研究の先駆者に、話を聞いた。

ランド・ウォルツマン博士。
アメリカ国防総省国防高等研究計画局=DARPAで、認知戦につながる研究を行った。2011年から4年間にわたり、総額5000万ドルをかけた研究では、SNS上で、どのように情報が拡散していくのかのメカニズムなど、200以上の論文が生み出された。
ウォルツマン博士は「認知戦」には「認知戦」で対抗するしかないと強調した。
アメリカ国防総省国防高等研究計画局=DARPAで、認知戦につながる研究を行った。2011年から4年間にわたり、総額5000万ドルをかけた研究では、SNS上で、どのように情報が拡散していくのかのメカニズムなど、200以上の論文が生み出された。
ウォルツマン博士は「認知戦」には「認知戦」で対抗するしかないと強調した。
ランド・ウォルツマン博士
「人々に積極的にメッセージを送る必要があるのです。頭の中にしっかりとアイデアを植え付ける必要があります。重要なのは、人はある考えが固定化されると、取り除くのは難しいということです。より大きく、より良く、より速く、他のプレイヤーが行動を起こす前に、人々の心にしっかりと刻み込むこと。それが最善の方法です」
「人々に積極的にメッセージを送る必要があるのです。頭の中にしっかりとアイデアを植え付ける必要があります。重要なのは、人はある考えが固定化されると、取り除くのは難しいということです。より大きく、より良く、より速く、他のプレイヤーが行動を起こす前に、人々の心にしっかりと刻み込むこと。それが最善の方法です」
しかし、政府機関などが、個人の行動に影響を与えようと、意図的に特定のメッセージを言論空間に広げることに倫理的に問題はないのか。
そう問うと…。
そう問うと…。

ランド・ウォルツマン博士
「代替案は、何も技術を持たないということしかありません。その方がいいんですか?電気も水道もないような19世紀の生活をしましょう、と言っているようなものです。もし、良いメッセージを伝え、人を助けるために使っているのであれば、私はそれに問題を感じません。多くの人はそれを問題視し、それが『フェアじゃない』とか『良くない行為だ』と考えます。しかし、重要なのは、脳の働き方を理解し、それに基づいて働きかけることです。すべてが悪いことだとは限らないのです」
「代替案は、何も技術を持たないということしかありません。その方がいいんですか?電気も水道もないような19世紀の生活をしましょう、と言っているようなものです。もし、良いメッセージを伝え、人を助けるために使っているのであれば、私はそれに問題を感じません。多くの人はそれを問題視し、それが『フェアじゃない』とか『良くない行為だ』と考えます。しかし、重要なのは、脳の働き方を理解し、それに基づいて働きかけることです。すべてが悪いことだとは限らないのです」

ウォルツマン博士の反論に答えに窮した私たち。
これまで世界中の専門家にも、認知戦について話を聞き、対応策について質問してきたが、最も多くの答えが、メディアリテラシーの教育の重要性だった。
しかし、ウォルツマン博士は、これにも懐疑的だった。
これまで世界中の専門家にも、認知戦について話を聞き、対応策について質問してきたが、最も多くの答えが、メディアリテラシーの教育の重要性だった。
しかし、ウォルツマン博士は、これにも懐疑的だった。
ランド・ウォルツマン博士
「それはポリティカリーコレクトなのかもしれませんが、何もできません。たとえばメディアリテラシーのトレーニングというのは、聞こえはいいです。一部の人には効果的かもしれませんが、規模は決して大きくならないし、問題解決にはなりません。つまり、それはただのおとぎ話です。私は信じません」
「それはポリティカリーコレクトなのかもしれませんが、何もできません。たとえばメディアリテラシーのトレーニングというのは、聞こえはいいです。一部の人には効果的かもしれませんが、規模は決して大きくならないし、問題解決にはなりません。つまり、それはただのおとぎ話です。私は信じません」
では、どのような未来が到来するのか。
最後の質問に、ウォルツマン博士は次のように答えた。
最後の質問に、ウォルツマン博士は次のように答えた。

ランド・ウォルツマン博士
「今のままでは、すべてが信頼されなくなっていくでしょう。物事はますます分断されていくでしょう。人々は最終的に、どこかの小さな『エコーチェンバー』を選んで暮らすようになり、そして、そこがあなたの居場所となるのです。残念ながら、それが今、私たちが歩んでいる進化の道なのです。しかし、そうである必要はないのです」
「今のままでは、すべてが信頼されなくなっていくでしょう。物事はますます分断されていくでしょう。人々は最終的に、どこかの小さな『エコーチェンバー』を選んで暮らすようになり、そして、そこがあなたの居場所となるのです。残念ながら、それが今、私たちが歩んでいる進化の道なのです。しかし、そうである必要はないのです」
「エコーチェンバー」
SNSなどで自分と同じような考え方ばかり見聞きしているうちにその考えが正しいと思い込むことを意味する。
ウォルツマン博士のことばからは、いま、この事態に歯止めをかけなければ、手遅れになるという危機感がにじんでいた。
SNSなどで自分と同じような考え方ばかり見聞きしているうちにその考えが正しいと思い込むことを意味する。
ウォルツマン博士のことばからは、いま、この事態に歯止めをかけなければ、手遅れになるという危機感がにじんでいた。

それぞれの信じる「事実」だけしか受け入れない社会。
認知戦という見えない“戦争”が、私たちの世界を歪ませている現実。そして社会の信用が失われ、分断が深まっていく未来。
私たちは、何を選択し、どう立ち向かっていけばいいのか。
流出文書が問いかけるものは、あまりにも大きく重い。
認知戦という見えない“戦争”が、私たちの世界を歪ませている現実。そして社会の信用が失われ、分断が深まっていく未来。
私たちは、何を選択し、どう立ち向かっていけばいいのか。
流出文書が問いかけるものは、あまりにも大きく重い。
NHKでは、今回の流出文書について詳しい内容を番組で放送した。
NHKスペシャル 調査報道 新世紀 File6 中国・流出文書を追う

科学文化部
記者
福田 陽平
サイバーセキュリティーを専門に取材
記者
福田 陽平
サイバーセキュリティーを専門に取材

政経国際番組部
ディレクター
新里 昌士
中国や中東地域を中心に取材
ディレクター
新里 昌士
中国や中東地域を中心に取材

政経国際番組部
ディレクター
高野 浩司
原発事故や偽情報対策などを取材
ディレクター
高野 浩司
原発事故や偽情報対策などを取材

ブリュッセル支局長
杉田 沙智代
中国や欧州の政策を取材
杉田 沙智代
中国や欧州の政策を取材