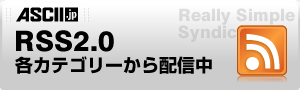本連載「Apple Geeks」は、Apple製ハードウェア/ソフトウェア、またこれらの中核をなすOS X/iOSに関する解説を、余すことなくお贈りする連載です(連載目次はこちら)。
UNIX使い向けを始め、Apple関連テクノロジー情報を知りつくしたいユーザーに役立つ情報を提供します。
WWDC 2013の基調講演で印象深かったことといえば、Mavericksで強化される「マルチディスプレー」だ。プライマリーやセカンダリーといった概念がなくなり、接続するディスプレーすべてがフラット化される。それぞれのディスプレーには独立したメニューバーが配置され、それぞれ異なるアプリをフルスクリーンモードで表示しておくことが可能になる。聴衆の拍手は、Finderの新機能が披露されたときより大きかったのではないだろうか。
その「マルチディスプレイ」は、外部ディスプレーへのワイヤレス出力もサポートする。もちろん利用するのは「AirPlay(ミラーリング)」、ディスプレーとHDMI接続したApple TVが受像機となる。現行のApple TV(第3世代)であれば1920×1080ピクセルを表示できるので、同じ解像度のiMac/21.5インチと組み合わせれば違和感なく利用できそうだ。
しかし、気になった点がひとつ。AirPlayは名称からしてワイヤレス(IEEE 802.11x)での利用を想像しがちだが、実のところ有線(Ethernet)でも接続できる。それに、1920×1080ピクセルの画面を30fpsあたりのレートで転送しようとすれば、目安として4Mbps以上の安定した帯域を確保せねばならず、是が非でもワイヤレスでという事情がないかぎり有線のほうがストレスはない。Mavericksのマルチディスプレー機能も、主なターゲットがデスクトップ機ユーザーである以上、有線接続をよしとする考えなのかもしれない。
もうひとつ、AirPlayにはインフラストラクチャーモードでの利用を前提とする仕様がある。たとえば、Apple TVとMacは1対1の排他的な関係で接続されるが、直接通信するわけではなく無線LANアクセスポイント/ルーターを経由する。だから、それらのネットワーク機器から離れた位置でAirPlay接続すると、帯域が不足してフレーム落ちを起こしたり音が途絶えたりしてしまうのだ。この点、(OS Xの)AirDropのように直接通信する仕組みがあれば、AirPlayを使ったマルチディスプレーもより使いやすくなるに違いない。

この連載の記事
-
第187回
iPhone
NFCの世界を一変させる!? iOS 11「Core NFC」の提供開始が意味するもの -
第186回
iPhone
Appleと「4K HDR」 - iOS 11で写真/動画を変える「HEIF」と「HEVC」 -
第185回
iPhone
iPhone 7搭載の「A10 Fusion」「W1」は何を変えるか -
第184回
iPhone
オープンソース化された「PowerShell」をMacで使う -
第183回
iPhone
アップル製デバイス連携の鍵、「Continuity」とは? -
第182回
iPhone
DCI-P3準拠へと歩むiPhone/iPad - WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(2) -
第181回
iPhone
WWDC基調講演で秘められた新技術は、ここにある(1) -
第180回
iPhone
WWDC直前、買い替え前にマイMacのココをチェック -
第179回
iPhone
私がiTunesを使わなくなった5つの理由 -
第178回
iPhone
今あえてiPhone「Live Photos」を知る -
第177回
iPhone
「Windows Subsystem for Linux」はOS Xのライバルとなるか? - この連載の一覧へ