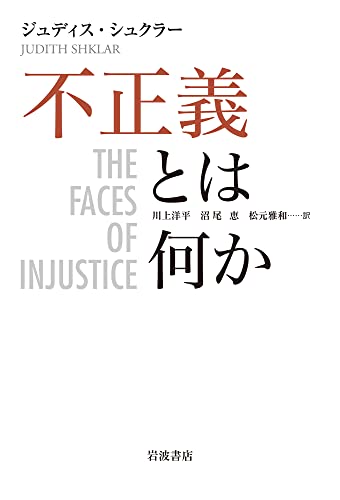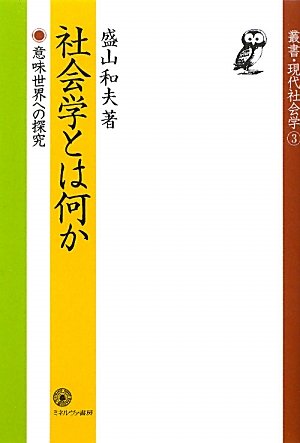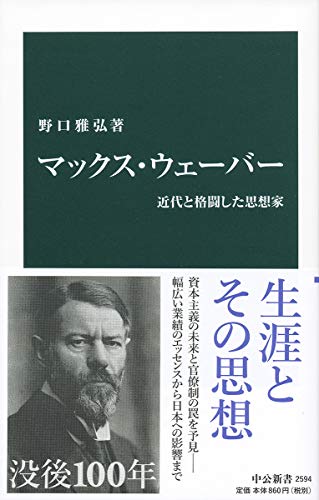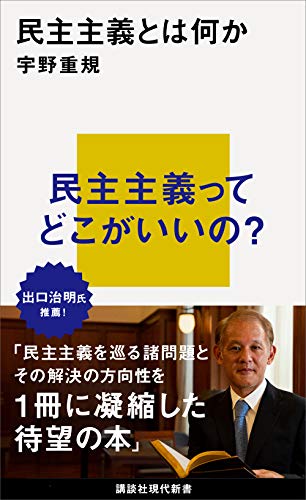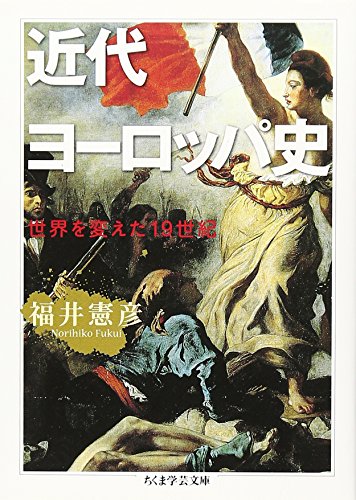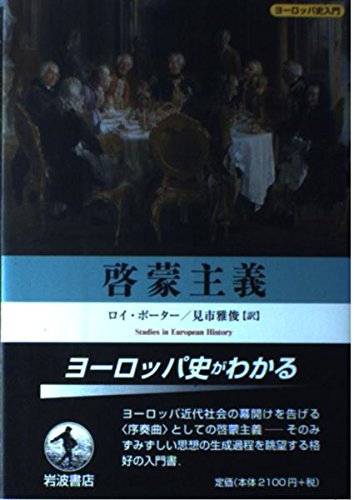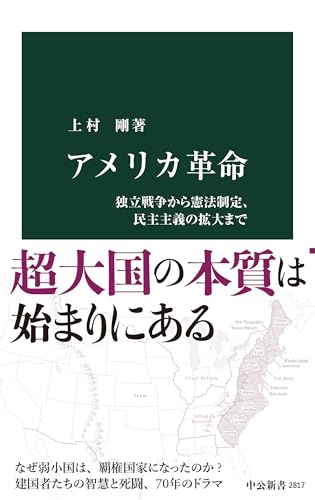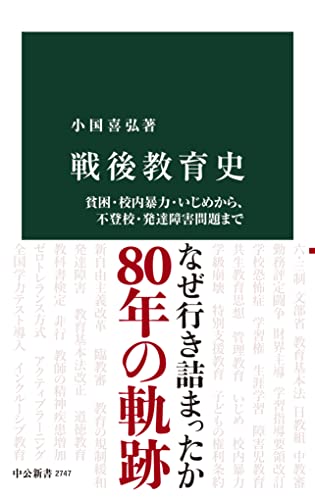本日、1月2日はわたしの誕生日です。36歳になりました。ヘビ年なので年男でめでたいです。よかったらなんか購入してください。
さて、例年、わたしは哲学を中心としながらもさまざまなジャンルの人文書を読んでおります。また、最新の本を読むということは少なくて、何年も前に出版された本を読んでいることが多い。なので、本当なら「年間ベスト」というのを作ることはできないんだけれど……あえて作りました。また、以下では、2024年(や2023年末に)読んだ本たちのなかで、良かったものや印象に残ったものをざっくりと紹介していきます。
ただし、Very Short Introductionの邦訳本については3日前の記事で言及済みなので今年読んだものであってもこちらでは取り上げません。また、3日前の記事と同じく、大半はBlueskyのほうに投稿した感想の流用です。本によって感想の文字量や丁寧さに大幅なバラつきがあるのは、感想を投稿した当時のわたしのテンションや気分や忙しさなどによるものです。誤字もいっぱいありそうだけど、悪いのは2025年のわたしではなく2024年のわたしです。
●2024年の本ベスト5
数字の近い2023年の本や2014年の本も含んでいます。
『まっとうな政治を求めて 「リベラルな」という形容詞』
コミュニタリアン/社会民主主義の政治哲学者として有名なウォルツァーが、コロナ禍で自宅から出れず参考資料もあまり使えない状況で、自身の経験を振り返ったり最近の出来事に言及したりしながら民主主義や社会主義、コミュニタリアニズムにフェミニズムといった様々な政治思想について語ることを通じて、そのいずれの思想にも付けられる形容詞としての「リベラル」を浮き彫りにしていく……といった構成。多元性と寛容とアイロニー、もっとくだけていうと「他の可能性」や「留保」を重要視する思想や考え方としての「リベラリズム」の意義やエッセンスが、実によく伝わりました。
単に抽象的な政治哲学を論じたり教条的なお題目を唱えたりするのではなく、ウォルツァー自身が政治・社会運動に関わってきた経験が反映されているからこそのプラグマティックな議論になっているところが重要。思想や理論だけでなく「現場」……運動の集団や雑誌の編集部、あるいは自分をそれらの思想に引き入れてくれる恩師や友人など……も重要であり、現場に身を置くと他の人たちの視点や留保が大切になってくるからリベラリズムが必要になってくる、という筋道が、ウォルツァーの人生を振り返りながら語られるからこそ見えてきました。
後半では#MeTooに「トランスジェンダー問題」、キャンセル・カルチャーについても言及されていますが、コミュニタリアニズムから連想されるような「反ポリコレ」的な議論にはなっておらず、かなり中庸でまともな議論がされております。また、普段触れることのない「社会民主主義」の考え方のエッセンスを知ることもできました。
『実存主義者のカフェにて 自由と存在とアプリコットカクテルを』
実存主義どころかそれを批判していた構造主義やポストモダンすらも古びた現在に、あえてサルトルからスタートしてフッサールまで遡りつつ思想史を展開していくという点ところに、著者の問題意識や戦略がうかがえました。実存主義だけでなく現象学にもたっぷり尺を割かれており、フッサールやハイデガーやメルロ=ポンティの思想がいままでにないくらいわかりやすく解説されている点が、優れていると思います。
一方、ハイデガーを「悪役」に位置付ける構成や思想・政治運動としての共産主義に対する冷淡さなど、いかにも英語圏の本らしい一面的なストーリー作りや浅薄さも存在するので、やや注意が必要な本でもあります。
レヴィ=ストロースによるサルトル批判がほぼ出てこないところにも、違和感を抱きました。「哲学者は思想よりも人物そのものが面白い」というのが著者の結論で、思想としての実存主義については「自由が重要な問題になっている地域(発展途上国など)では今だに重要」という感じに締められているんだけれど、構造主義によって批判されたような実存主義思想の弱点は結局ほとんど扱われていないために、片手落ちだと思った。
そして、本書を読んでいくうちに、サルトルやボーヴォワールに抱いていた好感が(著者の意図とは裏腹に)どんどん減っていった。頑固で芯が通っているカミュや、粘り強く考え続けたメルロ=ポンティのほうが政治的にも思想的にもよっぽど優れた人物であるように思えるし、場当たり的な遊び人であったサルトルらの欠点が哲学としての実存主義の弱点(根拠のなさや深みのなさ)にもつながっているのではないか……と思わされてしまった。
……と、いまのところ絶賛の書評しか目にしないので批判を多めに書いたけれど、読みものとしては十分に面白いと思います。よかったポイントは下記など。
・現象学と実存主義という20世紀半ばまでの大陸哲学のメインストリームについて、思想そのものについてもわかりやすく説明されているうえに人物のエピソードで補強されて理解しやすい。
・マイナーな思想家についても詳しく知れる。
・当時のフランスやドイツ、アルジェリアなどの社会の状況についても知れるという世界史的な面白さがある。
・後半になるとマードックやリチャード・ライトなど英米の文学者たちが絡んでくるので文学系の人にも楽しみやすい。
『ジョン・ロールズ 誰もが「生きづらくない社会」へ』
「公正としての正義」とはどのような考え方なのか、ロールズの思想における「自尊心」やその「社会的基礎」の位置付けと重要さなど、これまでのロールズ入門ではよく理解しきれなかったポイントがわかりやすく解説されている点が、非常によかったです。
9月に中部哲学会で「レジリエンスとリベラリズム」というテーマで発表した際にも、参考にさせてもらいました。
……ただし、やはりページ数が短くてロールズの魅力が伝わりづらいという難点もあるので、森田浩之さんの『ロールズ正義論入門』と合わせて読むことをオススメします。
『わかる!ニーチェ』
タイトル通り、わかりやすかった。著者や訳者のニーチェ贔屓もちょっとは感じたけど、「人間とは衝動の塊」とか「真理の追及がルサンチマンにつながる」とか「力への意志」に関する解釈とか、いずれも理解しやすい内容だったし、それなりに納得させられました。
それはそれとして、やはりニーチェは「厨二病」というか「大二病」的な思想だとも感じた。賢い大学生なら独自に辿り着けそうな思想というか。
あとがきでスティーブン・ピンカーがディスられているところも面白かったです。
思想家ごとに「時代」の文脈 と「思想」の文脈から初めて紹介し、さらにその思想家が「自由」と「公共」についてどう考えたかをまとめる、という練られていて密な構成が、とても良いです。思想の背景にある歴史や社会と経済の状況にもかなり気配りされており、思想”史”を学ぶことの面白さが体験できます。
全体的な結論としては「社会主義の失敗は歴史が証明したのでその理想だけは忘れないようにしながら、議会制民主主義と福祉国家を維持するためにがんばっていきましょう」といった感じ。経済史への目配りが非常に効いているのが、思想史の本として特徴的です。
●『モヤモヤする正義』の執筆にあたって(2024年内に)読んだ本たち
ストア哲学の歴史や古代における実践と、現代の認知行動療法の関係性や共通点について分析して論じられている本です。「現代ストア哲学」の本はいくつか出ているけれど、そのなかでも分厚く、また哲学的にも心理学的にも内容が細かくて参考になる。ただし、著者のドナルド・ロバートソンによるストア哲学の解釈や特徴付けには独特のクセや偏りがあるので注意が必要です。
「レトリック」や「印象」に注意しましょう、という(ロバートソン流の)ストア哲学の発想は『モヤモヤする正義』でも重要なポイントになっています。
……しかし、『認知行動療法の哲学』の「改題」はなんだかレトリカルな内容で、本書のメッセージと矛盾しているのではないか、と思わなくもなかった。
『差別の哲学入門』
マイクロアグレッションに関する議論については『モヤモヤする正義』第5章で疑問を呈していますが……全体的には、「差別」の定義や種類について合理的に考えていくことを通じて(分析)哲学的な思考や発想にも導入されていく内容になっており、啓蒙的な本だと思いました。「差別」だけでなく「哲学」への入門としてもおすすめ。
『男性学基本論文集』
こちらは褒めるところも見つけられなかった。『モヤモヤする正義』第6章で批判しています。
『私は本屋が好きでしたーーあふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏』
表現の自由をテーマにした第2章を書くにあたって参考にしたり、終章で言及したりしました。
『物象化』
短いうえに議論も比較的明瞭でわかりやすく、本文を読み終わったら訳者解説がたっぷりの分量で復習させてくれるという親切な構成。「社会病理」を考えるには正義論や分析哲学だけでは不十分である、そして正義に適っていても病理的な社会は存在する……というのが主なメッセージだと解釈したけれど、これは本書に限らず批判理論の全体を通じて中核的な考え方なのではないかと思った。
読みながら「この本でいう物象化ってマッチングアプリ批判にも当てはまるな」と思っていたら終盤で実際にマッチングアプリが登場したところが面白かった。また、ジャーナリストは他者を物象化するだけでなく自分の価値観や感情に蓋をしてしまう「自己物象化」を行う、という指摘も印象に残りました。
『承認をめぐる闘争: 社会的コンフリクトの道徳的文法』
印象的なタイトルだけが人口に膾炙している本ですが、いざ読んでみるとゴリゴリにヘーゲル哲学について議論されている内容で、なかなか難しい!
『モヤモヤする正義』の終章で引用しております。
『不正義とは何か』
「難解」という評判があったので尻込みしていましたが、いざ読んでみるとわかりやすかったです。単なる「自己責任論批判」に終始せず、不運と不正義の区別や理に適った訴えとそうでない訴えの区別について論じられているなど、既存の正義論を批判しながらも極端な否定にははしらない、バランスの取れた内容であるように感じられた。終章で紹介しています。
『政治と情念』
昨今ではコミュニタリアンのマイケル・サンデルなんかがアイデンティティ・ポリティクスを批判したり「とりあえず労働者の経済的苦境をなんとかしよう」といった主張をしたりしているなかで、同じくコミュニタリアンであるウォルツァーは本書においてアイデンティティを重視したり「何でもかんでも階級だけで捉えようとしたらダメ」といった主張をしているのは、時代の違いを考慮しても大切なポイントだな、と考えました。
「討議リベラリズムは誰もが理性を持つという点で対等性を保証するが、情念を重視するする思想においても”相手も自分も利益や信念を持つという点で対等だ”と考えられる」というくだりが印象に残りました。『モヤモヤする正義』の終章の脚注にさりげなく登場します。
同じように正義論を批判しているシュクラーやアイデンティティ・ポリティクスを重視するウォルツァーに比べても文章や議論が上滑りしているという感覚が強く、アジテーション効果はあるかもしれないけれどフェアネスや誠実さを志向しているようには思えない……などと、ネガティブな感情を抱きながら読んだ。ホネットは『承認をめぐる闘争』の序盤でヤングの議論を「自分の設定した議論の枠組みをぶち壊しにした」として切り捨てていたけれど、わかるような気がする。
とはいえ、批判理論の発想がわかりやすく示されているので、『モヤモヤする正義』の終章で引用させてもらいました。また、本書の第7章における能力主義批判やアファーマティブ・アクション擁護、そして第8章における都市論は興味深くて、ここら辺は改めて読み返すことになると思います。
『アドルノ入門』
入門書としては内容や言い回しが難解だったけれど、アドルノさんとは価値観や問題意識が似ているおかげで、まあまあしっかり理解できた。読みものとしても、なかなかおもしろかったです。終章で引用しています。
VSIの翻訳である『一冊でわかる ハーバーマス』に比べるとだいぶのんべだらりとしているが、そのおかげで気楽に読めました。著者の真面目さとハーバーマスの真面目さが掛け算されて、背筋をシャキッとさせられるような内容です。1990年代というSNS以前の時代に書かれたこともあり、牧歌的なところもよかったです。終章で紹介しています。
『ネットはなぜいつも揉めているのか』
テーマが似ているので『モヤモヤする正義』と共鳴するところが多く感じられました。6章で参照しております。
このブログで何度か取り上げてきた本の邦訳がついに出版されました。けっこう話題になったようで、なによりです。『モヤモヤする正義』では6章や7章で参照しています
『社会正義論の系譜: ヒュームからウォルツァーまで (叢書フロネーシス)』
第10章「契約論的社会正義 -いくつかの現代の議論の概観-」(ポール・ケリー)を『モヤモヤする正義』第3章で引用しています。ケリー論文は「アイデンティティの政治」に対するリベラリズムからの批判/回答のお手本みたいな内容で参考になる。
原著が1998年なので当然のことながら内容は古びているというか既視感があるし、翻訳も堅く拙くて読みづらいけれど、この本で提起されている様々な論点…1980年代から90年代のリベラル・コミュニタリアン論争を背景とした「手続き的正義」や「分配的正義」など政治哲学の基本的な論点、リベラリズムとアイデンティティ・ジェンダー・環境などのトピックの相剋…は現在ではまったく「解決」されることなく争点として残り続けているし、各論文で行われている議論も現在に通じるものが多いので、ネットやグローバリゼーションを経ても現在の論争の状況は80年代からほとんど変わることなく地続きなのだ、ということを再確認できました。
『道徳的に考えるとはどういうことか』
内容にはあまり説得されなかったけど、ヌスバウムの『感情と法』の副読本という感じで読みました。「論理」と「感情」と「想像力」の違いを説明しているところも、参考になった。『モヤモヤする正義』の4章で引用しています。
『自省録』
年末年始はこういった人生論を読むことに決めているので、2023年の年末に読みました。「世間の目なんか気にするな」「しょうもない奴らになんと言われても気にするな」みたいな箇所がちらほらあって、「アウレリウスさんはついつい世間やしょうもない奴の言動を気にしてしまうからこそ、自分に言い聞かせるためにこういうこと書くんだろうな」と思った。『モヤモヤする正義』の最終章の脚注でちょびっと登場しています。
●単行本など
『リベラルな共同体 ドゥオーキンの政治・道徳理論』
ドゥオーキンの思想をガッツリと復習できました。
『人生の意味の哲学入門』
前半の論文を読んでいてい「こういう議論も必要なのは理解するけど、分析哲学で『人生の意味」を扱うのって根本的に矛盾しているというかつまらないよな…」と思わされてきたところで、後半の論文で「やっぱり『人生の意味』は分析哲学だけでは扱いきれませんよ(それでも分析哲学による議論もある程度までは必要だし参考になりますよ)」と著者たち自身が認めることで読者の側の理解も深まる、という構成になっています。
安くなっていたので購入してリベラリズムやコミュニタリアニズムを復習するために読んだけれど、さすがに賞味期限が切れているというか、『リベラル・コミュニタリアン論争』を読んでおけば間に合う内容でした。
個人の自由とか権利とかではなく「リベラルさ(寛大さ)」を重視する政治思想としての「リベラリズム」を、イギリスではなくフランス(ときどきドイツ)に由来するものとして捉えて、その系譜を語っていく……という内容。
出だしでは「アメリカ以外の世界の多くの国では『リベラル』が自由市場主義・小さな政府を志向するものと捉えられている」という問題意識から始まるんだけど、「ヨーロッパならともかく別に日本ではそんなことないしな…」と思わされ、序盤の数章も「リベラルは古来から徳と共通善を重視してきたのだ」という筋書きにイマイチ説得力を感じずにノレなかったけど、読み進めていくとだんだん面白くなってきた。
トマス・ ホッブズやジョン・ロックを差し置いてフランスにリベラリズムの系譜を見出す筋書きにはやはりかなり無理があると思うし、序盤は知らんフランス人の人名が出てきて「こいつらにどれだけの重要さがあるの」と辟易しながら読んでいたけれど、中盤頃からはJ・S・ミルやアメリカ大統領など馴染みのある英米系の人々が頻繁に登場して彼らに仏独の思想家が与えた影響を知れて、普段は触れる機会のないフランス(ときどきドイツ)のリベラリズムの歴史を学ぶことにも意義を感じられた。
フランス革命を始めとして思想ではなく実際の政治的状況が重視されている面も興味深かった。とくに、ビスマルクがリベラリストたちを懐柔して骨抜きにすることで国民からも政治的批判能力を失わせていき権威主義的な政治支配を強固にする…というくだりは現代の日本にも通じるものがあると思った。本書でしつこく強調される「リベラリズムは個人の権利や利益からではなく、共通善や徳を重視する(べき)思想だ」という主張も、このくだりによって「たしかに一理あるな」とは思わせる。
ニューディールの頃までは本来は共通善や徳を重視していたアメリカのリベラリストたちが権利主義・自由市場主義になった背景には冷戦がある、というのも納得。とはいえ、訳者解説でも表現されているように、やっぱりホッブズやロックを軽視している時点からまず無理があるし、「失われた歴史」ではあっても「正しい歴史」を語る本ではないなと思った。
また、これも訳者解説で触れられていたけど、共通善や徳ではなく個人の権利を重視する・個人の権利を基礎とするタイプのリベラリズムの理論的正当性が軽視されていて、ロールズも雑に「冷戦のせいで変節した後のアメリカ型リベラリスト」の括りに入れられているのはかなりどうかと思いました。結局はリベラル・コミュニタリアン論争におけるコミュニタリアン側の主張の焼き直しに終始する結論になっていたように思えます。思想の由来や歴史的経緯と、正しさは切り離せるはずだし…。
『99%のためのマルクス入門』
タメにはなるんだけど入門書としての導入やストーリーラインが不在というか、初手からマルクスの思想とその現代的修正を直球でぶつけられているような読み心地でした。
また、以下のようなロジックが登場するんだけど……:(A)資本主義社会では賃労働者が労働を行い生産を行うから、(B)社会の本来の主役は労働者であるはずなのに、(C)実際には資本主義社会では資本が主役になっている(資本家は資本の人格化に過ぎない)、(D)なので現代の社会はおかしい。
ここの議論ではかなり唐突に「社会の主役」という発想が登場して、(B)の部分にかなり違和感を抱きました。そしてその後も(A)や(C)については深堀りした説明がされるけれど(B)の説明はあまりなかったように思える。
一方、第4章はマルクスが理想とする社会のあり方や、マルクスの人間観がくわしく取り上げられており、本書のなかではこの章がいちばんおもしろかった。
とくに興味深かったのが、『ドイツ・イデオロギー』の「朝には狩りをし、昼には釣りをし、夕方には家畜を追い、そして食後には批評をすることができ~」の後には「私は狩人、漁師、牧人、あるいは批評家にならないという率直な欲望を持つことができるようになる」と続いており、むしろ後半のほうが重要な点。マルクスは古代ギリシアの哲学者にならって「職人芸」や「一芸に秀でること」に大した価値を見出さず、分業によって特定の職業に縛り付けられることを人間の在り方としてよいものと見なさかった、とのことですが、わたしも昔からこのような価値観を抱いておりますので、実に共感できました。
『生き方としての哲学』
ストア主義者は政治から撤退しがちであったという話もされている一方で、哲学における「対話」というのは議論における他者の権利や自分より上位にある理性という規範を認めることであり、理性に従おうと試みたときにはエゴイズムを放棄せざるを得なくなる……という議論が印象に残った。
哲学者も社会や生活に対する関心を持つべきだけれど、有意義な社会参加・政治参加をするからにこそ理性によって陶冶される「内面の平和」が重要…というのは実にバランス取れていて良い見方だと思います。マルクス・アウレリウスが『自省録』で示していたような考え方ですね。
後半でも「普遍的な理性」と「同胞や共同体への道徳的な義務」などをつなげるストア派的な考え方がたびたび出てきて、倫理学的な議論としても面白かった。本書のなかでは「普遍的な道徳は以前から存在していて発見されるのを待っている」的な言い方がされていたけれど、ストア派的な倫理学の議論は読むたびに、ピーター・シンガーの『輪の拡大』を思い出します。
『人間の条件』
アーレントの思想に関心を抱き始めたので、本人の書いたものも読んでみました。感想は秘めておきます。
『社会学とは何か』
全体的に「社会」というのは実在するか否か(著者は「否」の立場)、実在しないとして「社会」をどう扱うか……という社会学者たちの悪戦苦闘の歴史を、諸々の理論の登場と挫折の過程を通じて描くという本。社会学の教科書としても使えると思います。
ジンメルやウェーバーなどの歴史上の偉大な社会学者に対して「この考え方を採用する社会学としての意味がなくなる」とか「この概念をこの定義で説明すると矛盾することになる」とかいう風に、まるで存命の相手にするかのように“マジレス”な感じで批判しているところが、良く悪くも独特。
基本的には理論メインの本ながら、パーソンズの理論が「1968年の学生反乱」をきっかけに問い直されたり、それまで客観性や「社会の外部にいること」を重視してきた社会学の方法論が1970年代から問題視されるようになる…など、「社会学」の背後にある「社会」の動きもうっすらと見えてくる。近年では社会学は「斜に構える学問」とは真逆な規範的なイメージが強いけど、その裏にある事情が伝わってきました。
また「社会学とは現状分析と規範提示の両方を含む『秩序構想の学』『共同性の学』であるべきだ」という結論を提示。ハーバーマスも出てきたりして「共同性」は「公共性」と近い概念のようですが、「真理」を重視する学問共同体での(理想的な)議論のあり方が公共性の理想例として提示されたり、学問上の論争で戦わされるのはあくまで「仮説」に過ぎないと念押したり規範的な問題意識があるのに「客観的」に振る舞うのは矛盾だから問題意識を明示せよみたいに論じられたり……などなど、最近のわたしの考えにも合致するところが多くて、興味深く読めました。
『暴政 20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン』
Blueskyで本書の感想がバズっていたので気になって読みましたが、新品で注文したのが届いてみると文庫本サイズの薄い本で「これで1320円かい」とけっこうムカつきました。
内容としては、ハンナ・アーレントを中核とするような反・全体主義や反・権威主義、反・ポピュリズムな思想のエッセンスをわかりやすく表現した感じ。「解説」では「パンフレットではない」とされているけれど、良くも悪くもパンフレット的な本だと思いました。わたしも含めて本書の内容に共感できる人や元々アーレント的な思想・問題意識を持っている人が「その通りだ」「確かにそうだ」と同意したり問題を再確認したりすることはできるけれど、その思想が何らかの形で論証や正当化されているわけではないので、異なる思想を持つ人を説得したり感化したりすることはできない……というタイプの本です。
2016年のトランプ当選前後のアメリカの政治状況の惨憺たる有り様を示しつつ、それに対して前向きな反論の言葉を力強く提示してくれるのはよい……のだけれど、そこから何ら変化が起こらなかった2024年に読むと虚しさも強く感じました。
……とはいえ、政治的にも思想的にもモチベーションを保ち続けるためには、こういうパンフレットやアジテーションとしての書籍も必要だということは、わたしも最近になって理解するようになりました。
2024年の当選の際に目の前の出来事しか見ず8年前と何ら変わり映えしない小手先の「分析」を披露していたタイプの知識人を目にして「冷静」とか「中立」とかの薄っぺらさを感じさせられてしまったし、スナイダーみたいな形で政治にコミットする方が知識人として担うべき役割をきちんと果たしているとも思います。
本書の内容について言及すると、「制度や手続きがあるから大丈夫」「まだ慌てるような時間じゃない」という考え方に代表されるような、正常性バイアスに影響された様子見や楽観的思考が手厳しく批判されて、ナチス時代の実例などを示しながら「制度も手続きも国家も、壊れる時には一気に壊れてしまうよ」と警鐘を鳴らしているところが重要だと思った。終盤ではピンカー的な合理的楽観主義も暗に批判されている。
また、「自分の言葉を大切にしよう」「私的領域も確保しよう」というアーレントっぽい個人主義も言いつつ、「制度や職業倫理に基づくきちんとしたジャーナリズムを信頼しよう」ともきちんと言っているところがいいと思いました。単に理念を言い続けているだけでなく「シビルソサエティ」や「法廷、新聞、法律、労働組合」などの具体的な制度や活動を支援したり守ろうとしたりする意思を持とうと促したり、「紙媒体のジャーナリズム」の重要さを説く一方でインターネットを徹底的に批判しているのは、具体的かつまともでよいと思う。ただこの内容で1320円はやっぱり高いです。
『入門 哲学の名著』
代表的な西洋哲学者たちの主著20冊について、要約とこれまでになされてきた批判のまとめ、そして各章の訳者による補足(著者のまとめ方に対する苦言や、批判に対する反論など)が収められており、実にバランスよく西洋哲学史を復習できる。ただ、原著は版を重ねるごとに対象の著作が追加されており、現在では33冊にまで増えているようなので、最新版の邦訳も出てほしいと思った。哲学史の通史の邦訳本で読みやすいものって、意外とないのです。
ほんとうにオーソドックスな解説書という感じなので、感想を書くのは難しいんだけれど、地味で興味を惹かれづらいロックの著作を二つ取り上げてくれているところ、ミルの『自由論』に対してちゃんと批判しているところ、サルトルの解説は熱が入っていて著者の情熱が伝わってくるところ、難解なイメージのあるカントやウィトゲンシュタインの思想も実にわかりやすく解説してくれているところ、などなどがよかったです。
『弁証法的想像力:フランクフルト学派と社会研究所の歴史 1923-1950』
『実存主義者のカフェにて』を読んだ後に、同じ時代の裏側にいたドイツ系の(そしてユダヤ系の人たち)の思想史も読みたいな……と思って手に取りました。しかし、如何せん昔の本なのでなかなか読みづらかった。
中公新書の『フランクフルト学派』を読んだときと同じく、前向きで生産的なフロムと、ひたすら頑固なアドルノに好感を抱いた。フロムがフロイト使いながらも、過度に性愛を強調するあたりをばっさり切り捨てて家族関係とか愛情をフィーチャーしているのは、好感が抱けるし理論・思想的にもまともだと思った。また、6章では駄々をこねるアドルノに対して知人が送った手紙が紹介されるけど、まるでホールデン・コールフィールドを大人が説教しているみたいな内容で笑ってしまいました。
また、70年代に書かれた本なので、現代では見放されたイメージの強いマルクーゼの出番が多いところも印象に残りました。
3章ではホルクハイマーが社会的・政治的事象をいたずらに心理的事象と「同一」させることについて苦言を呈しているけれど、この「同一」については現在でも進化心理学・人類学や経済学なんかの理論を使ってやろうとしている人々がうじゃうじゃいるので、使う理論がなんであるかはともかく「同一」させることへの欲望は時代が変わっても残っているんだなと考えさせられました。
●新書本など
『戦後フランス思想』
この本を読んだ時点ではボーヴォワールに好感を抱いたけど、その後で『実存主義者のカフェにて』を読んだことで、やや嫌いになりました。
新書なのでページ数が短く、そして伝記的な事実や各人の人間関係にゴシップみたいなトピックに紙幅が多く割かれているせいで「戦後フランス思想ってすごく狭い身内サークル内で成立していたんだな」という印象を抱かされてしまった(実際そうなんだけど)。また、各思想家の哲学についても多少は解説されているんだけど、それが今日的にどのような意義があるか、あるいはどのような面白さがあるかまでは深掘りされていないので、どうにも中途半端に感じた。
……とはいえ、本書を読んだおかげで『実存主義者のカフェにて』を買う決心がついたし、予習にもなったのでよかったです。
『ハンナ・アーレント 「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』
伝記的な要素が強いけれど、アーレントが直面した時代の問題を描くことで、アーレントの思想の意義や価値を浮き彫りにすることを試みている本だと思いました。そして、その試みは成功していると感じました。アーレントの思想そのものの入門書よりも、まずはこの本を読んでみることをオススメします。
『ハンナ・アレント再論―〈あるべき政治〉を求めて』
こちらは、あんまり面白くなかった。とはいえ、「複数性」に関する議論や「真実より意見のほうが重要」などについては印象に残りました。
『マックス・ウェーバー 近代と格闘した思想家』
『わかる!ニーチェ』から続けて読んだということもあり、ウェーバーとニーチェの思想の親和性が感じられたのが印象的でした。
伝記事実を多めに紹介しながら、その流れで思想も解説してく……というのは『ハンナ・アーレント』や『戦後フランス思想』にも通じる中公新書の西洋思想紹介の定番スタイルなんだけれど、ウェーバーの人生はアーレントや戦後フランスの人々に比べるとドラマチックさに欠けるな、と思いました。
あと節の末ごとに他の思想家や研究者、フィクション作品を持ち出すのはいいけど「ウェーバーと関係があると言えなくもない」みたいなビミョーな関連付けが多過ぎるので、無理にそんなことしなくてもいいのでは……と思った。
『フランクフルト学派:ホルクハイマー、アドルノから21世紀の「批判理論」へ』
「批判理論は批判ばっかりで代替となる案や規範を提示しない」という意見に対して「現状を批判するのみの思想も必要だ」と、正面から批判理論を擁護する出だしがむしろ好ましく、序盤からグッと興味を惹きつけてくれました。
2014年の本ですが、10年前とは思えないくらいアクチュアルで、とても面白かったです。「フランクフルト学はアメリカにも日本にもいるし、あなただったなれる」みたいな締めがスターウォーズのエピソード8みたいで、よかった。
マルクスとフロイトを統合したフロムからスタートして「異質な考え方を統合させる」というところにフランクフルト学派の特徴を見出しているところが本書のポイントかな。
『民主主義とは何か』
古代ギリシアから現代までの、民主主義思想が駆け足で説明されていくので、ちょっと内容が薄く感じた。とはいえ、まとめや整理の仕方はさすがに優れていて、参考になりました。
『「死にたい」と言われたら 自殺の心理学』
『男はなぜ孤独死するのか』とあわせて読みました。プラグマティックな議論だけでなく、そもそも自殺を予防しようとすること自体に正当性はあるのかなど、根本的な議論も含まれているところが実に興味深く、啓蒙させられます。
『刑の重さは何で決まるのか』
刑法学のなかでも「量刑論」の考え方について学べる本。新書本としては内容がすこしハードだけど、じっくり読むとおもしろい。終盤では修復的司法の考え方や意義についてわかりやすく整理されているところも重要だと思いました。
『「自由」はいかに可能か 社会構想のための哲学』
「自由の相互承認」などヘーゲル哲学の考え方は他の考え方より優れている、ということを立証しようとする箇所が多くて、ちょっと疲れた。とはいえ、最近ではヘーゲル的な積極的自由論の意義がだいぶわかるようになってきました。
2014年の本なんだけど、冒頭に「いまは無理に自由に生きようとしなければヌクヌクとほどほどに幸せに暮らせる、という雰囲気があるよね」といった社会観を前提にした論述があって、10年後のいまとなってはそんな雰囲気は皆無であり社会がどんどん殺伐していっていることに気付かされました。
『いまを生きるカント倫理学』
わかりやすくてよかったしカントの魅力は伝わったけど、どんな問題にもカントを適用したりなんでもかんでもカントを「正解」に位置付けようとしているように感じられて、ちょっと無理があるなとも思った。同じ著者の『意志の倫理学 カントに学ぶ善への勇気』のほうがオススメかな。
基本的に過ぎる内容であんまり面白くなかったけれど、「価格メカニズム」についてしっかりしっかり学ぶことはできました。
「買う側より売る側のほうが遥かに大変」、という当たり前の事実が心に残った。リスクに怯えてしまう人間なので、自分で(元手をかけて)商売することを志せる人間って(商売や資本主義自体の良し悪しはさておき)すごいなと思う。
『近代ヨーロッパ史——世界を変えた19世紀』
政治だけでなく思想や経済、技術や制度が歴史に与えた影響がバランスよく取り上げられていたのが良かったです。通史を一気に読むことならではの理解が得られたというか、「思想史や経済史の本ばっかり読むまえに、オーソドックスな通史の本をしっかりと読んでおくべきだ(った)な」という思いを抱かされますた。
近代ヨーロッパの負の側面はもちろん取り上げられているけれど、啓蒙思想が歴史に与えた影響が強調されながら、近代的な人間の在り方とか目的合理的な考え方のあり方とかいうのがこの時代にできたと論じられているのが印象的。一方で農村部の人々の生活やロマン主義にも紙幅が割かれているのが弁証法的でよかったです。
『第一次世界大戦』
第一次世界大戦といえば「銃後」が注目されがちなところ、あえて戦線の変遷や戦況の推移を中心に取り上げた……とのことですが、わたしは基本的に戦争に興味がない人間なので、もっと人物史や社会史・文化史の要素があった方がよかったです。
とはいえ、定評ある入門書だけあってコンパクトにまとまっているし、戦争を通じて「列強体制」の論理が弱まったとかナショナリズムと福祉国家が進展したとか、基本的な歴史の流れをよく学ぶことができました。
現代と啓蒙時代の共通点と相違点を適度に取り上げつつ、啓蒙主義の成り立ちや意義がバランスよく論じられていて、とても参考になる本でした。
執筆当時(1990年代)における「階級闘争」重視派と「政治文化」重視派の論争に触れて、後者に寄せて説明した内容。リン・ハントの議論や、ハーバーマスの公共圏に関する議論、あるいはメリトクラシーに関する議論など、馴染みのある用語が出てきたおかげで理解しやすかった。
フランス革命の本は、これまでは岩波ジュニア新書の『フランス革命:歴史における劇薬』くらいしか読んだことがありませでしたが、悲劇性を重視してエモーショナルだった『歴史における劇薬』に比べて『ヨーロッパ史入門』はマジで淡々としている。そして、悲劇性を強調すること自体もある種のレトリックになるな、ということに思い当たりました。いまだに、アンチ・フランス革命な言説はエドマンド・バーク的な反動保守の主張に利用されることがあるしね。
序章からアファーマティブ・アクションの歴史を考える意義をしっかり伝えてくれる構成なのがよい。「制度的人種主義」の説明も、レイシズム理論が苦手なわたしにとってもわかりやすくて、受け入れやすかった。
アメリカでは「不平等の是正」としてのアファーマティブ・アクションに対して「逆差別」との批判がされるようになり、目的を「多様性の実現」にすり替えて継続したが本来の趣旨が忘れられていくうちに最終的に違憲となりました……という流れが綺麗に説明されているのが良いです。
政策としてのアファーマティブ・アクションがどうかという問題とは別に本来の「不平等の是正」は必ずしも実現されていないからそこに立ち返りましょう、といった結論も真っ当。一方で、本書ではアファーマティブ・アクションの対義語みたいな感じにされていて扱いのよくない「メリトクラシー」の根強さや規範的意義も逆説的に考えさせられた。
あとがきで「アメリカではアファーマティブ・アクションは違憲になったけれど、他の諸外国では現在もアファーマティブ・アクションやクオータ制度が導入されている」という話がちらっとされているけれど、「やっぱりアメリカは特殊な国なんだから他の国のことももっと知らなければならないんだな」という思いを抱きます。
『カナダ人権史:多文化共生社会はこうして築かれた』
「人権は法律・法典や理論ではなく歴史を通じて社会のなかで作られていく」という著者の主張に基づく、歴史社会学のアプローチでカナダの人権史を描いた本。……なんだけれど、意外と「カナダ独特」というところは感じられず、むしろ「権利が拡がる流れはどこの国も近いんだな」と思ってしまった。
「……アメリカ合衆国の権利文化の中心にあるのは、憲法の起草者たちのもともとの意図や憲法の文言に関する議論である。カナダの人権の歴史には、このような傾向はまったくみられない。むしろ、カナダでは、権利文化がたえずつくり直されているように思われる。」(p.189):この箇所は、カナダと諸外国の違いというよりも、むしろアメリカと他の国との違いを表すものとして、印象に残りました。
基本的には政治史なんだけれど、ところどころで植民地時代のアメリカにおける人々の生活の様子とか産業や経済の状況などについての記述が入ることで、飽きずに読んでいけました。
先住民・黒人に対する差別・迫害についても定期的に触れたり女性の人物も多く登場するのは現代的であり新鮮だと感じる一方で、マジョリティや従来の「正史」に対する批判が行き過ぎているということもなく、バランス感覚に優れている本だと思います。
内容としてはどんどんハードになっていき、新書としてはなかなか手応えがありましたが、初期アメリカにおける憲法をめぐる葛藤とレトリックについての理解が深まりました。なお、登場人物のみんなには「自分のできることを頑張っていてえらいな」と思わされて好印象を抱きましたが、アンドリュー・ジャクソンだけはドナルド・トランプみたいなロクでもない人間だったので印象がかなり悪かったです。
『民主主義を疑ってみる:自分で考えるための政治思想講義』
とくに共和主義と社会主義の章は知らなかった知識が多く、たいへん参考になりました。古代ギリシアにおけるノモスやピュシスの議論や、政治思想史におけるヘレニズム哲学の役割などについても参考になりました。
一方で、由主義の章では著者の描くストーリーのためにストア哲学や功利主義にピンカー的な主張が矮小化されて紹介されているように思えた。
著者の重視する「シティズンシップ」についてはわたしも「公共性」という表現で『モヤモヤする正義』のなかで価値を説いたし、共和主義・自由主義・社会主義などを経由したうえで民主主義を肯定する結論にもまあ同意できるけど、たとえば『アゲイント・デモクラシー』で行われているような徹底した民主主義否定論に対する反論にはなっていないように思えました。民主主義や政治に対して本気で無力感を抱いている人を説得できる内容ではない、というか。
『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』
各時代の経済や人口(または戦争)などの外的状況と経営者・労働者・政府それぞれの思惑が衝突と妥協を繰り返しながら日本社会の慣行が歴史を通じて形成されていく姿が具体的に描かれていて面白かったです。合間で引用される当時の経営者や労働者や学生らの「声」も昭和映画っぽくてよかったです。
この本は学生ではなく社会人になってから読むべきですね。現に自分の自由を制限してストレスを与えまくってくる雇用慣行や労働環境にも、時代と成り行きに制約されながらの「合理性」が存在すること、とはいえそれは絶対的ではなく可変的なものであることが学べました。
また、本書でも『日本のメリトクラシー』が何度も参照されますが、読んでいて思い出すのは、やはりマイケル・サンデルのメリトクラシー批判。哲学的にも社会学的にもぜんぜん妥当でなかったり内容が空虚であったりする「能力」という概念も、身分差別を打破するための民主主義・平等主義的な感性からアメリカでなく日本でも必要とされたこと、でもそれがけっきょく経営者に有利で労働者に不利なように操作されていく…という世知辛さを感じました。
「勉強した内容より大学名が優先され、旧帝大や早慶ばかり有利であり続ける社会ってバカみたいだしわびしいな」という価値観に対して、日本社会がそうなった理由を説明して、でも正当化はしない、という塩梅の本だと思いました。これが経済学者の書いた本だと、事実と価値・規範は分けるべきだとしながらも「説明」にとどまらず「正当化」に傾いちゃってしまう気がするし、そもそも時代や状況に制約されたなかでの合理性や慣行を丁寧に扱える人も少ないと思いますので、(歴史)社会学の強みや良さというものも感じました。
そして、その時々の「合理性」の陰で排除されたり残余に押し込められてきた人々(とくに女学生や女性労働者、「推薦」から漏れた学生など)に関する描写や引用が印象に残ったし、表向きには強調されない著者のメッセージがうかがえました。
『自分で考える勇気 カント哲学入門』
カントの思想や生き様を「勇気」(と「啓蒙」)というキーワードによって語り解説する、というのが面白く、読むモチベーションを湧かせてくれました。カントの語る認識論や倫理学、美学や政治哲学なんかはすべて一貫した理論体系に基づいていることも、よく伝わった。
倫理学の入門書で他の理論と並べられるとカント倫理って素っ頓狂であったり応用力が低そうだったりに思えるけれど、カント哲学という体系のなかに位置付けて説明されると、妥当に思えてくるもんですね。
また、他のカント倫理学の入門書に比べると、善や義務や意志と「幸福」との関係を繰り返し指摘しているところが印象的でした。「自己の完全性」と「他人の幸福」を追求するのがカントの理想のようです。
一方で、前半は読者に「自分で考える勇気」を持たせることや啓蒙の精神が感じられたけれど、終盤は、やや無理気味なカント哲学の理論を著者から押し付けられているように感じてしまったかな。
『人生の短さについて 他2篇』
『自省録』と合わせて、2023年の年末に読みました。5年くらい前に読んだときはかなり感銘を受けた記憶があるけれど、再読するとちょっと内容が浅いように思えた。
『戦後民主主義』『戦後教育史』『「家庭」の誕生』
ちょっと思うところあって昭和〜平成の日本の歴史を勉強したいと思い、まとめて読んだ。この中でも『戦後民主主義』は小熊英二さんの『「民主」と「愛国」』を思い出させる内容で、かなり良い本でした(他2冊も悪くはない)。これら3冊の本は扱っている時代やトピックが似ているのもあって同じキーワードや人物が登場してそれぞれ別の文脈や視点で取り上げられる、というのが良かった。
図書館で借りて流し読みしてしまったけれど、改めてきちんと読み返したいと思っています。
『移民と日本社会』
日本社会に限定されているけれど、思った以上にVSIの『移民』と議論やトピックが被っていて、移民に関する現象とか問題とかはどこの国でも普遍的なんだなと思った。中公新書には『移民と経済』という本もありますが、本書でも経済に関する議論が多く含まれています。
『正義とは何か』
新書本としては詰め込みすぎであり、図書館で借りてさっと読んでしまったけれど、本来なら赤ペンを持って線を引きながらじっくりと読むべき内容です。……なんにせよ、ロールズ以前のいろんな正義論について紹介されていて、参考になりました。アリストテレスとプラトン、ロックとヒュームとアダム・スミスのあたりが興味深かった。
『ケアの倫理──フェミニズムの政治思想』
こちらも、新書本としてはハード過ぎるというか、選書あたりで出すべき内容だったと思います。
読んでいて思ったのは、エヴァ・フェダー・キテイ的な、ケア労働(再生産労働)に基づくロールズ批判はアナーキズムやリバタリアニズムと同じように政治・国家の正当性を掘り崩すことのできる思想だということ。そして、アナーキズムやリバタリアニズムと同じように、(キテイ的な)ケア論とはそれ自体を規範として採用するのには適さないけれど、極論と対比させること現行規範への理解を深めたり反省を促したりするという点で意義のある思想だということです。