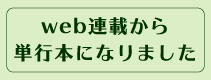衝撃の「鍵盤ハーモニカノンフィクション文学」 小西恒夫(南川朱生(ピアノニマス)『鍵盤ハーモニカの本』)
ある楽器が一定の社会的認知度を獲得する過程として「文化(シーン)の形成」がある。
鍵盤ハーモニカは人によっては楽器というよりむしろ「教材もしくはおもちゃ」という趣のほうが腑に落ちる代物かも知れない。果たして本当にそうなのか、明白な正解は無い。しかし少なくとも本書『鍵盤ハーモニカの本』の著者である南川朱生氏は、真っ向からこれを「楽器」だと主張する。
鍵盤ハーモニカ奏者である南川氏のライブ会場に足を運べば「鍵盤ハーモニカが素晴らしい芸術性を備えた楽器である」ことを、その圧倒的なパフォーマンスで体感させてくれる。しかし鍵盤ハーモニカ研究家としての南川氏は、このことを活字上でも見事に証明してみせた。
本書に掲載された膨大かつパブリックな史実群が本来の鍵盤ハーモニカ像をホログラムのように立体視させ、その進化の過程を(それが決して一本道でないことも含めて)つまびらかにしていく。ここまで説得力のある鍵盤ハーモニカ研究書は唯一無二である一方、この楽器の辿った数奇とも言える運命に想いを馳せれば、ノンフィクション文学としても十分堪能出来る。鍵盤ハーモニカという切り口で捉えた数々の発見はおそらく世界初出と思われる見解も多く、今後鍵盤ハーモニカの歴史は「本書『鍵盤ハーモニカの本』発表以前・以後」という基準で語られていくことになるであろう(但し業界関係各位がこの書を『ないもの』と見做さない限りは……)。
鍵盤ハーモニカを取り巻く「文化」
ところで南川氏は何故ここまで直向きに鍵盤ハーモニカの「楽器としての」特性(人権ともいえる)を訴えるのか……単なる偏愛や情熱の賜物だろうか、私はそうは思わない。
日本の経済成長の歯車に翻弄され、毎年児童数の数パーセントが「自動的に買ってくれる」大量生産商品として世に放たれ続けた鍵盤ハーモニカ。そしてメソッドもハートも音楽もない状態で投げ渡された「それ」を、親も子も学校も「純粋な楽器」として昇華出来る筈もなく、やがてまた時間の狭間へとスルーパスされていく、これの、繰り返し……(勿論子供には罪も責任もないし、一部の教育現場では幸せな例外事例も多々あろう)。この状態が何十年と積み重ねられた、悲しいかな、これが今日の鍵盤ハーモニカをとりまく文化である。
私事で恐縮だが、私は鍵盤ハーモニカ講師として各地の小学校へ赴く事がある。現場の先生方から高頻度で繰り出されるのは「小西先生は、普段は何の楽器をされているんですか?」というフレーズ。イノセントな慣用句であることは重々承知しているが、鍵盤ハーモニカの講師として来校しているのに……と少々違和感と寂しさを覚える。このように「楽器としての人権」を剥奪され続けてきた鍵盤ハーモニカの復権を成し遂げる為には、一体何が必要なのか。答えは全て本書『鍵盤ハーモニカの本』に記されてはいるが、既得権益や根深い社会常識の壁に阻まれ、実現の日は遥か夢幻の先にあるどころか、このままでは種の絶滅さえも危惧される。鍵盤ハーモニカが大量生産市場に依存しているが故の運命といえよう。
本書『鍵盤ハーモニカの本』のなかで著者南川朱生氏は鍵盤ハーモニカを「音響物体」として再認識することに着眼しているが、これは楽器としての最も根源的な定義がそこにあるからである。このような科学的なカテゴライズに加え、著者は様々な角度(実用面・音楽面・歴史変遷等々)からこの楽器を「鍵盤ハーモニカたらしめている」要素を浮き彫りにし、これらの「鍵盤ハーモニカ」が時代のニーズにどう応え、どのように当時の人々に愛されたのか、そしてそれがどのように変遷し今日に至ったのかを地続きの事象として描き切っている。
かかる歴史にも今日のこの状況にも所詮、功も罪も無いのかも知れない。ならばせめてこの数奇なシロモノが「何者」なのかをしっかりと受容し見極めていく責任が、我々には有るのではなかろうか。南川氏自身が本文中にてこの楽器のことを「水のような」と喩えているが、社会との関連性という文脈において「我々の身体組成の数パーセントは鍵盤ハーモニカで出来ている」と言っても、決して過言ではない。
鍵盤ハーモニカの旅へ
南川氏が誘なう鍵盤ハーモニカの旅。我々はその旅に同行し、これまでの常識を根本から覆す 「鍵盤ハーモニカの地平(真実)」を目の当たりにすることになる。そしてその時、我々は自ら の胸に選択を強いられるであろう…鍵盤ハーモニカとは、一体何者なのか?
楽器なのか、おもちゃなのか、使い捨て教材なのか……親も子も、学校も、プロもアマも、もちろん製造者も、鍵盤ハーモニカに関わる全ての人間が、その選択の責任を担っている。そしてその選択の集合体の先にしか、鍵盤ハーモニカの未来はない。南川氏が本書執筆に賭けた壮絶なまでの熱量は、その選択への、鍵盤ハーモニカの未来への願いのように、私には思えてならない。