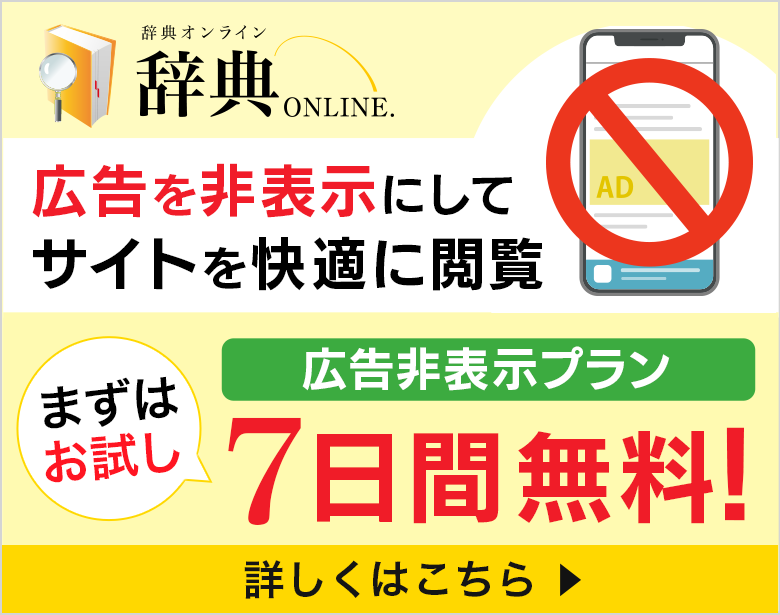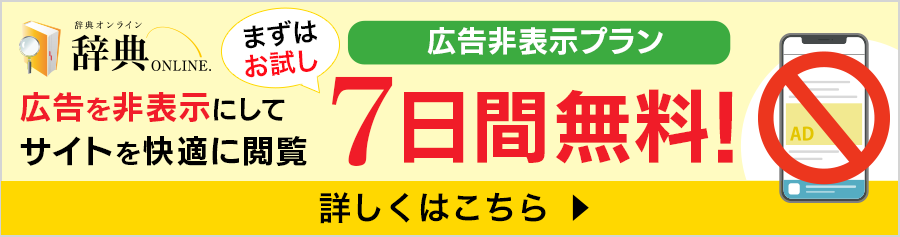知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむとは
知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ
ちしゃはみずをたのしみ、じんしゃはやまをたのしむ

| 言葉 | 知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ |
|---|---|
| 読み方 | ちしゃはみずをたのしみ、じんしゃはやまをたのしむ |
| 意味 | ものの道理をわきまえた人は、判断に迷いがないからよどみなく流れる川を愛し楽しむ。また、仁徳を備えた人は、静かな心で何事にも動じないからどっしりかまえた山を愛し楽しむということ。
単に「知者は水を楽しむ」「仁者は山を楽しむ」ともいう。 |
| 出典 | 『論語』雍也 |
| 異形 | 知者は水を楽しむ(ちしゃはみずをたのしむ) |
| 仁者は山を楽しむ(じんしゃはやまをたのしむ) | |
| 使用漢字 | 知 / 者 / 水 / 楽 / 仁 / 山 |
「知」を含むことわざ
- 相対のことはこちゃ知らぬ(あいたいのことはこちゃしらぬ)
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)
- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)
- 息の臭きは主知らず(いきのくさきはぬししらず)
- いざ知らず(いざしらず)
- 衣食足りて栄辱を知る(いしょくたりてえいじょくをしる)
- 衣食足りて礼節を知る(いしょくたりてれいせつをしる)
- 衣食足れば則ち栄辱を知る(いしょくたればすなわちえいじょくをしる)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
「水」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 汗水流す(あせみずながす)
- 汗水を流す(あせみずをながす)
- 頭から水を浴びたよう(あたまからみずをあびたよう)
- 頭から水を掛けられたよう(あたまからみずをかけられたよう)
- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)
- 魚と水(うおとみず)
- 魚の水に離れたよう(うおのみずにはなれたよう)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
「楽」を含むことわざ
- あって地獄、なくて極楽(あってじごく、なくてごくらく)
- 親苦、子楽、孫乞食(おやく、こらく、まごこじき)
- 歓楽極まりて哀情多し(かんらくきわまりてあいじょうおおし)
- 楽屋裏を覗く(がくやうらをのぞく)
- 楽屋から火を出す(がくやからひをだす)
- 楽屋で声を嗄らす(がくやでこえをからす)
- 聞いて極楽、見て地獄(きいてごくらく、みてじごく)
- 曲肱の楽しみ(きょっこうのたのしみ)
- 苦あれば楽あり(くあればらくあり)
- 苦あれば楽あり、楽あれば苦あり(くあればらくあり、らくあればくあり)
「仁」を含むことわざ
- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)
- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)
- 医は仁術(いはじんじゅつ)
- 巧言令色、鮮なし仁(こうげんれいしょく、すくなしじん)
- 剛毅朴訥、仁に近し(ごうきぼくとつ、じんにちかし)
- 仁義を切る(じんぎをきる)
- 仁者は憂えず、知者は惑わず、勇者は懼れず(じんしゃはうれえず、ちしゃはまどわず、ゆうしゃはおそれず)
- 仁者は敵なし(じんしゃはてきなし)
- 仁者は山を楽しむ(じんしゃはやまをたのしむ)
- 宋襄の仁(そうじょうのじん)