
Founder & CEO
btrax
Brandon K. Hillさん(@BrandonKHill)
北海道生まれの日米ハーフ。サンフランシスコと東京のデザイン会社btrax代表。サンフランシスコ州立大学デザイン科卒。 サンフラン市長アドバイザー、経済産業省 始動プログラム公式メンター。ポッドキャストも運営
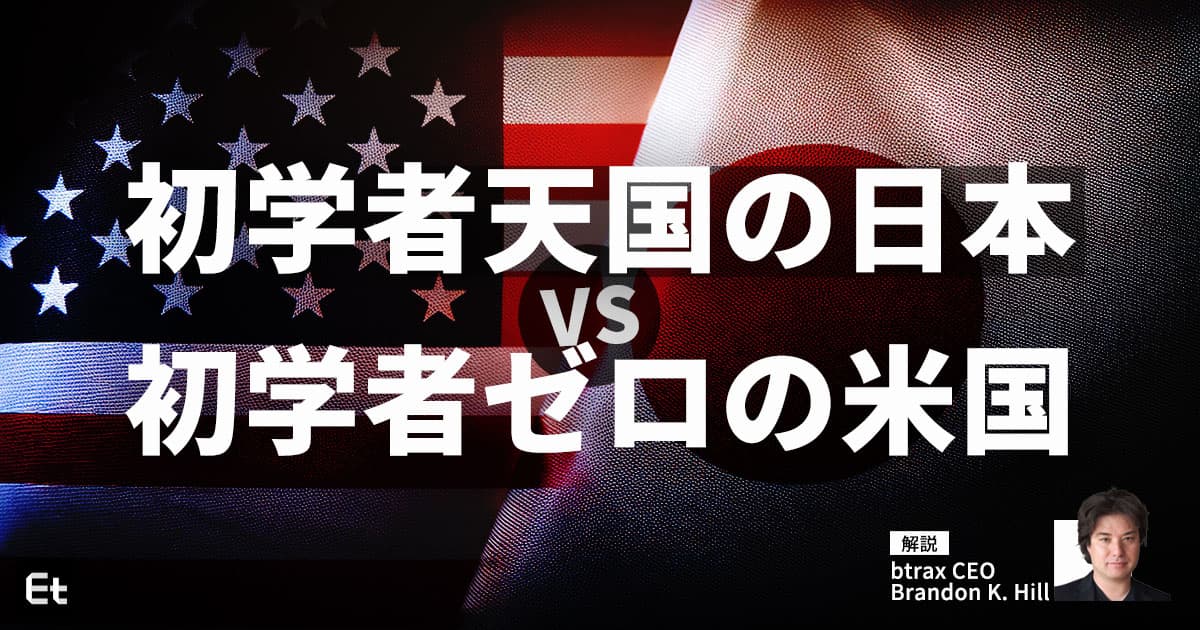
「つよつよエンジニアは、初学者に厳しすぎ」
「いやいや、自力で調べて解決するのがエンジニアだろ」
「自分で考えろ、って効率悪くない?」
「育成スタンスが優しくないから、いつまで経ってもIT人材不足」
先日もX上で話題になった「エンジニア育成」の議論。もはや、一生議論されているテーマと言っても過言ではないが、世界トップレベルの「つよつよエンジニア」がひしめく米国からみると、この議論は一体どのように見えるのだろうか。
米国のテック業界やそこで働くエンジニア事情にも詳しいブランドンさんに聞いた。

Founder & CEO
btrax
Brandon K. Hillさん(@BrandonKHill)
北海道生まれの日米ハーフ。サンフランシスコと東京のデザイン会社btrax代表。サンフランシスコ州立大学デザイン科卒。 サンフラン市長アドバイザー、経済産業省 始動プログラム公式メンター。ポッドキャストも運営
目次
「エンジニア教育、どこまでやるのが正解?」系の議論は、米国からみるとどのように映ったのか。ブランドンさんに聞くと「そもそも米国と日本ではエンジニアのキャリアの始まり方が違うので、こうした議論は発生しない」のだと話す。
「独学なり、インターンなり、何でもいいのですが、そもそも一定のスキルが身に付いている状態でないと米国では正社員として採用されません」
米国には新卒採用という概念がなく、ジョブ型雇用が前提なので、社会人1年目だからといって「会社側が教える」仕組みがない。そのため、先のポストで言われているような“初学者”は採用されないどころか、エンジニアにすらなれないのだ。

「もう一つ、構造的な違いとして大きいのが、どのタイミングでも会社は従業員を解雇できてしまう点です。
無事採用されたとしても、いざプロジェクトに入ってスキルが足りないと分かれば、自力、かつ素早くアップデートしなければなりません。それができないエンジニアは、パワハラされる間もなくクビにされて終わりです」
「できないと言った社員は即解雇」で有名なイーロン・マスクを彷彿とさせる話だが、何もイーロンに限った話ではないようだ。実際、ブランドンさんは、10年前に当時Twitter社員だった友人からこんな話を聞いたという。
「初期のTwitterにはRuby on Railsが採用されていました。ただ、サービスのスケールが大きくなるにしたがって、拡張性に劣るレイルズの弱点がボトルネックになる可能性が見えてきたそうです。
将来的にユーザー数が増大することを見据え、Scalaへの移行が決定すると『1週間以内にScalaを扱えるようになってください』とエンジニア全員に通達された。扱えるようにならない者は解雇となります、以上。そんなスピード感だったそうです」

厳しい環境にも思えるが、そんなカルチャーのメリットについて、ブランドンさんは「衛生的なビジネス環境だと思う」という見方をする。
「日本のビジネスシーンでパワハラという言葉が散見されるのは、やはり解雇規制に一因があると感じます。なぜなら、企業側に解雇できる権限があれば、パワハラなんて面倒くさいことはしないはずなんです。文句を言ってくる社員は“解雇しておしまい”にするだけ。でも日本ではそれができません。
だから、不平不満を言う社員や受け身な社員に対して、上司がわざと厳しく当たったり、嫌がらせをして本人が辞めたくなるように仕向ける、みたいなことが起こってしまうのではないでしょうか。ビジネスをする場として衛生的に非常に良くないし、不毛だと感じますね」
また、育成コストが最小限で済むことも社内の衛生環境を保つポイントだと付け加える。
「できるエンジニアからすると初学者の育成は面倒だし、疲弊します。スキルを活かしたい、いいものづくりがしたいと思っているのに、他者の育成に時間が取られてしまうわけですから。嫌気がさしてフリーランスになるエンジニアを何人も見ました。そうやって優秀なエンジニアを手放すのは、組織にとっていい事はないはずです」
手取り足取り教えてもらう慣習がない米国とはいえ、誰しも「はじめての社会人」、「はじめましてのプロジェクト」に入るタイミングはあるだろう。そんな時、100%手放しというわけにはいかないのではないだろうか。
「もちろんそういう時は、上司がコードレビューをしたり、必要な知識を学ぶためのオンライン講座を提供したりしますよ。ただ、それはあくまでも『仕事ができるように』サポートしているのであって『育てる』ためではありません」
大抵の米国企業は入社後1週間ほどはオンボーディング期間を設けるが、その中身は会社システムへのアクセスの仕方や勤怠ツールの使い方といったレクチャーが中心という。
「業務を進めるために必要なスキルを身に付けることは、エンジニアが各々やるべきこととしてみなされます。なので、オンボーディング期間が終われば“毎日査定”される日々がスタートします」
さすが成果主義の国らしい話だが、そのハードモードな環境に愚痴を言いたくなる瞬間もあるだろう。日本でよく見られる“若手同士が飲み会で上司や会社の愚痴を言い合う”なんて場面はどんな様子なのか。
「愚痴る前に訴訟を起こされますね(笑)。ただ大前提、米国では愚痴を言う人やネガティブなことを言う人はローパフォーマーとみなされる傾向にあります。
Googleの採用基準に『good natured person』(いい人)があることで広まった考え方ですが、不平不満を言う人は組織の雰囲気や生産性を下げるため、人前でネガティブな発言をしたり、SNSで書き込んだのがバレると解雇されることも少なくありません。
入社時に交わす契約書にも、ネガティブな発信をしたら『1回目は注意、2回目は解雇』と明記している会社も多いです。不当解雇と訴えられるのを避けるためですけどね。
利益は伸びているにも関わらずGAFAMが定期的に大規模レイオフを行うのも、その成長スピードに追いつけないローパフォーマーをふるいにかけたい思惑があるからです」
裏を返せば、解雇規制があり、手取り足取り教えてくれる日本は「初学者エンジニアに優しい国」かもしれない。
「それを優しいと捉えるか、アマチュアの集まりと捉えるかは人それぞれですね」と手厳しい言葉を放つブランドンさんに、あえて米国環境のデメリットも聞いてみた。
「最大のデメリットは、ジュニアエンジニアがファーストキャリアを築きづらいことだと思います。面接時には『作ったものを見せて』と言われたり、目の前でコードを書かされたりするのでスキルをごまかせません。
また、世界中からエリートが集まり、いくらでもスゴ腕エンジニアが湧いてくるため、晴れて正社員になれてもストイックに勉強し続けることが求められます」
そんな中でも「アーリーステージにあるスタートアップは救いになっている」と教えてくれた。
「起業したばかりのスタートアップは資金がなかったり、若者がCEOだったり、企業としてまだまだ形づくられてない部分が多いので、手伝う感覚で始められるんです。GoogleやFacebookに入る前にそういった場所で、ものづくりの実践経験を積む若者は多いです。
見渡せばアーリーステージのスタートアップだらけですし、ハッカソンやインターンも沢山機会提供されているので、腕試しするチャンスは沢山転がっています」

日本は米国のようになるべきと言いたいわけではない。ただ、もし今後日本が米国のような環境にシフトするとしたら、何が足りないだろうか。その問いに、ブランドンさんは「やっぱり、給与水準をあげること。それを解雇規制緩和をセットで行うことだと思います」と即答する。
「米国のエンジニアが年収2000万円、3000万円もらえるのは、前提、優秀な人材だからです。できない人は採用しませんし、入社後にできないと分かれば解雇できるので給与設定を高くできるんです。
それと比べて日本は、初学者を一人前にしていく文化がベースにある。中途採用で経験者を迎えても、本当の実力は働いてもらわないと判明しませんし、能力が低いと分かったところで辞めさせることができません。
企業はそのリスク込みで給与設定しなくてはならないので、月給20万円、30万円なんていう下限設定になってしまう。それはそうですよね、ハズレを引いてしまった時のために会社へのダメージを最小限にしておきたいと考えるのは無理もありませんから」
給与水準の向上と解雇規制の緩和。これをセットで見直さない限り、日本におけるエンジニア育成議論は終わりを迎えないのかもしれない。
取材・文・編集/玉城智子(編集部)
※掲載当初、Twitterが「Pythonへ移行」と記していましたが、誤りだったため、「Scalaへ移行」へ訂正しています。





タグ