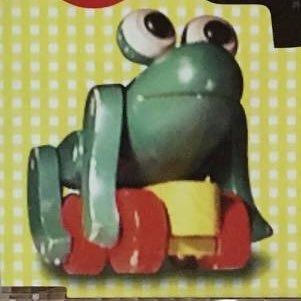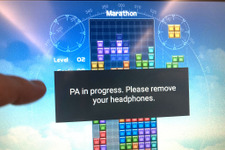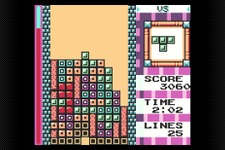たった7種類の落ちてくるピースを綺麗にはめて、一列揃えて消す……そんな単純なルールでありながら、世界中のゲーマーが夢中になるのが『テトリス(TETRIS)』という作品です。
そんな『テトリス』が最初に遊べる状態で生まれたのは、1984年6月6日のこと。元はゲームクリエイターではなくソ連の研究者であったアレクセイ・パジトノフがソ連のコンピューターであるElectronika 60(Электроника-60)向けに作ったプログラムでした。
そこから世界に広がったテトリスは、アメリカから日本まで各国で愛されるパズルゲームとなり、今日に至るまで何本もの作品が発表されています。
40周年という記念すべき日を迎えたことを、本記事では筆者が所有している『テトリス』から40本をピックアップして紹介。さまざまな会社がさまざまな形で生み出した歴代の『テトリス』を見て、40年という長い歴史を共に振り返りましょう。
なお、選定タイトルはオーソドックスな『テトリス』のルールをベースにしたもののみをピックアップ。『ボンブリス』や『テトリスフラッシュ』のみの作品は選んでいません。また、公式にライセンスされていない作品も除外しています。
No.1『テトリス』(ゲームボーイ、1989)

日本のユーザーに最も馴染みがあり、売上本数も高い『テトリス』のひとつが、このゲームボーイ版です。ロシア民謡をベースにした田中宏和氏作曲の「コロブチカ」が耳に残っている人も多いのではないでしょうか。

本作には、まっさらな状態からエンドレスにブロックを重ねていく一般的なマラソンルールの「GAME A」と、すでに積み上がった状態から一定数ラインを消す「GAME B」の2モードが収録。


どちらも成績によって、ロケットが打ち上がるエンディングを見ることができます。
本作は『テトリス』史上初めて対戦ルールを実装した作品で、30ラインを早く消すというルールの元通信ケーブルを介して対戦ができます。現在はNintendo Switch Onlineにも配信されており、オンラインで対戦も可能です。
No.2『Tetris』(発売元:任天堂、Nintendo Entertainment System、1989)

今日に至るまで、競技シーンで使われ続ける作品です。任天堂が開発していますが、日本では発売されませんでした。

大まかな仕様やモードはGB版と共通しており、GAME AとGAME Bの2通りが楽しめます。GB版と共に田中宏和氏が手掛けた楽曲は、チャイコフスキー「くるみ割り人形」の「金平糖の踊り」に加え、GB版のTYPE B楽曲と同じものや、浮遊感のあるオリジナル曲が用意されています。

ルールはいわゆる「クラシックテトリス」と言われるもので、テトリミノのローテーションが完全なランダムだったり、テトリミノ接地後に動かせなかったり、といった仕様です(現代ルールとの違いは後ほど説明します)。クラシック版はより正確で機敏な操作と判断が求められるという点が人気を集める理由のひとつです。
現在も大会を通じて楽しまれており、新たな操作テクなども見つかっています。上位プレイヤーのテトリミノさばきには惚れ惚れします。
No.3『テトリス』(発売元:BPS、ファミリーコンピュータ、1988)

一方日本のファミコンでは、『テトリス』を世界に広めた立役者のひとりであるヘンク・B・ロジャース氏が設立したBPS(Bullet-Proof Software)のものが発売されました。日本でリリースされた『テトリス』としては、最初期の作品となります。

モードは基本的に25ラインを消すまでのスコアアタックで、落ちる速さと最初から設置されたブロックの量を決めてスタートします。BGMはロシアの民謡などをベースとしており、「トロイカ」と「カリンカ」に加え、「アラベスク」のフレーズを加えつつもテクノ調に仕上がった名曲「TECHNOTRIS」が収録されています。
本作ならではの特徴といえば、その独特な操作方法。十字キー下で回転(左回転のみ)、Aボタンでハードドロップなど後の作品からは考えられない操作になっているほか、接地してからの固定も早いので、難易度は高めです。


最も盤面が複雑で落下スピードの早いステージ9ラウンド5をクリアすると、ダンスをする人々のアニメーションが流れ、最後に聖ワシリイ大聖堂に花火が打ち上がる様子が見られます。
No.4『テトリス』(発売元:セガ、アーケード、1988)

『テトリス』は家庭用だけでなく、アーケードでも人気を博した作品です。その立役者のひとつとなったのが、日本における『テトリス』黎明期に稼働したセガのアーケード版です。直接的な対戦ルールではありませんでしたが、2人で並んでマラソンをするという形のマルチプレイも実装されています。

ルールはオーソドックスなマラソンですが、本作の良い点は接地後に少しだけ猶予があること。本作は落ちても少しだけブロックをずらすことができるため、落下速度が早すぎてまともに操作できないという点を解決しており、さらなる戦略性が生まれました。こうした仕様は、後発作品にも多大な影響を与えたと言われています。

耳に残るメロディのサウンドトラックや、なぜか登場する猿のキャラクター、実写の背景画像など、ロシア・ソ連的なテイストをほぼ取り入れていない点はこの時期の『テトリス』としては異色です。
No.5『テトリスDS』(発売元:任天堂、ニンテンドーDS、2006)

現在新作としてリリースされる『テトリス』のほとんどは、2002年に定められたガイドライン(通称ワールドルール)によってその仕様が決まっています。具体的には、テトリミノのホールド機能や次にくるテトリミノを最低3つ表示、落下場所にゴーストが表示される、テトリミノの出現順の調整などが定められ、全体的に遊びやすくなりました。この『テトリスDS』も、そんなワールドルールを採用した作品です。

本作ではマラソンから対戦、詰将棋のようなものまでかなり幅広いモードが用意されており、1本だけでもかなりのコンテンツ量が用意されています。操作性も機敏で、ストレスなく楽しめます。

ビジュアルやサウンドは任天堂発売のファミコンゲームをテーマにしており、『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』などをアレンジした映像や音楽が楽しめます。マラソンの最後では、ゲームボーイの『テトリス』がテーマになるというサプライズ演出もあります。
No.6『SEGA AGES 2500 シリーズ Vol.28 テトリスコレクション』(発売元:セガ、PlayStation 2、2006)

クラシックゲームを復刻する『SEGA AGES』シリーズの一環として発売されたのが、この『テトリスコレクション』。セガ発売の『テトリス』とその関連作が収録されたお得かつ歴史的意義の深い1本です。


収録作は1988年のアーケード版に加え、セガ・マークIIIと同等の性能や機能を持った「システムE」版や、アーケード版をベースにワールドルールでリメイクした『テトリス ニューセンチュリー』など。『フラッシュポイント』や『ブロクシード』といった派生作品も遊べます。

特筆すべきは、いわくつき(?)のメガドライブ(MD)版が遊べること。当時アーケードのヒットを受けMDへの開発が進められていたものの、セガにライセンスしていたテンゲンは実際にはライセンスを出す権利がなく、アンドロメダ・ソフトウェア、ミラーソフト、アタリ、テンゲン、セガと複数社をまたいだ玄孫……をひとつ越えた“来孫ライセンス”ともいうべき状態になってしまっていたのです。
そんな中、任天堂がELORGから直接的な独占契約を受けた結果、発売日まで告知されるほど進められていたMD版を自粛することになりました。このあたりの事件は、Apple TV+で配信されている映画「テトリス」でも取り扱われています(やや脚色はありますが)。
そんなMD版も、本作ならバッチリプレイ可能。アーケードとの演出やモードの違いをひとまとめにして楽しめるので、『テトリス』の歴史を知りたい方には必携の1本です。
No.7『テトリス』(発売元:セガ、メガドライブミニ、2019)

メガドライブミニでは、そんなメガドライブ版『テトリス』のもうひとつの姿を見ることができます。本作に収録されている『テトリス』は事前番組などで明言されていた通り、本来のMD版『テトリス』ではありません。

本作の正体は、メガドライブミニに合わせて新規に作られた、アーケード版を忠実再現したもの。あくまでメガドライブ上で実現できることは守りつつ、ほぼ完璧なアーケード準拠のものが出来上がっています。これも、大事な『テトリス』の歴史の1ページです。
No.8『TETRIS 99』(配信元:任天堂、ニンテンドースイッチ、2019)

『PUBG』の流行をきっかけに、2017年頃より大きな盛り上がりを見せた「バトルロイヤル」。最後のひとりまで生き残るというわかりやすいルールで愛されましたが、その多くがシューターであった中、本作はなんと『テトリス』でバトルロイヤルを実現しています。

といっても、基本的にプレイヤーがやることはいつものテトリスと同じ。しかし、右スティックで戦略を変更することで、他のプレイヤーを狙ったり、こちらを狙っている敵に反撃したりできます。相手を狙ってブロックを消していけばお邪魔ブロックを送りつけることが可能です。

任天堂タイトルとのコラボが頻繁に行われており、ゲーム内で獲得できるチケットを使えば背景やブロック、サウンドを変更できるテーマを獲得可能。『星のカービィ ディスカバリー』や『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』といった新作から、『ドンキーコング』やGB版『テトリス』といった旧作のテーマにも変更できます。
No.9『テトリス2+ボンブリス』(発売元:BPS、ファミリーコンピュータ、1991)

先述したように、ファミコン第1作目の『テトリス』は現代から見るとややいびつな作品です。しかし、ファミコン後期に発売された本作は、オーソドックスで完成度の高い『テトリス』に仕上がっているほか、『ボンブリス』が初めて作られた作品でもあります。
ゲームは第1作目のTYPE-A、TYPE-Bに加え、下から徐々にせり上がってくるTYPE-Cもプレイできます。操作が一般的なテトリスのものに戻っているのが最大の利点で、かなり遊びやすくなりました。一方、テトリミノの落下がなめらかなので、ややソフトドロップの調節がしにくいという難点もあります。

本作はチュンソフト(現・スパイク・チュンソフト)が開発を行なっており、プロデューサーに石原恒和氏、ディレクターに中村光一氏、コンポーザーにすぎやまこういち氏、協力として宮本茂氏や遠藤雅伸氏が参加していて、後にも先にも例がない豪華なメンバーが揃った作品です。サウンドトラックは、どことなく『ドラゴンクエスト』を彷彿とさせます。
No.10『TETRIS』(配信元:The Tetris Company、Web、2014)

『テトリス』公式サイト上で無料で遊べる作品です。広告を見る必要はありますが、何度でも無料でプレイできます。
基本ルールはひたすらマラソンというシンプルなものですが、コントローラーではなくマウスで操作できるのが特徴。操作は非常に洗練されており、置きたい場所にカーソルを合わせるだけで思い通りに配置できるのが快感。


左クリックでハードドロップ、右クリックでホールドもできるので、サクサク操作できます。Tスピンも行えるため、高等テクを極めるためのブロックの積み方を身体に覚えさせるツールとしても有用かもしれません。