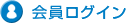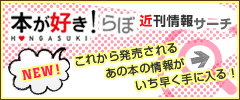レビュアー:
▼
サラリーマンの風雅は「課長風月」であり、「青色3号」の風雅は「アチョー風月」である。(後半はウソです)
橋本治からは最近読了した『風雅の虎の巻』の抜粋&コメントに挑戦。
本書では手加減なしの「本質尽くし」がこれでもかと展開されていて、
現代人の良心を持つ読者には眉を顰めずして読み進めることができない。
あるいは本書を軽快に読むことが“それ“を捨てる修行になるかもしれない。
これはカルチャースクール一般に対するイヤミではあって、言い方を変えれば
「名前に惹かれてやってくる人に実質なんて分からない」と。
ただそれは文化の需給関係とは別次元の話であって、要するに
講師も受講者も(お金やイデオロギーによって)満足していれば市場は成立する。
「お金が全て」の資本主義社会では実質が軽視されるとはいうけれど、
(日本の大衆文化については)昔からそんなものはなかったらしい。
文化は生活の実質を充実させるためにあり、文化人が備える「文化の実質」は
生活に応用される際にその本質を骨抜きにされる。
だから(本質的に孤独ゆえ)文化を担う人々には様々な覚悟を必要としたのだろう。
それが境遇によって否応なく決定されていればいずれ達観が訪れるのだろうし、
あるいは外の世界を知らずに純粋培養されていれば(余裕の)風雅が醸されるのか。
そして、文化人が生活の実質をも獲得することは叶わないのか?
簡単に言えば「素直にひねくれる人間も存在し得る」と。
素直にひねくれる人間は、素直な自分を人に理解されたいと思っても、
”素直”な人からは屈折しているようにしか見えないから諦めるしかない。
共生的な身体が生育過程で損なわれた人間には、共生に実感が伴うことがない。
…どうにも救われない話だと思ってしまうが、人間以外ではありえない現象ながら、
人間だからこそ別途救われる方法もあって、きっとそれは、
「徹底的に頭で生きる」ことだろうかと想像する。
昔(千年近く前)の日本の身分の違いは、お互い想像を絶するものであったのか。
現代日本において「西洋近代化はどこまで進んだか?」を考えるにおいて、
本書はよいテキストになると思う。
和魂と洋才の比率がどの程度であるのか。
きっと本書を読めば「和魂の残存比率」の想定値がガクンと下がるだろう。
ちと散漫に過ぎたか…
p.s.
野暮ですが、「ひと言コメント」の後半は英訳すればわかるダジャレです。
(前半の「課長風月」は本書中に数多くあるハシモト氏の「名言」のひとつです)
しかしああ書くと着色料みたいだな…「赤色102号」とか。
本書では手加減なしの「本質尽くし」がこれでもかと展開されていて、
現代人の良心を持つ読者には眉を顰めずして読み進めることができない。
あるいは本書を軽快に読むことが“それ“を捨てる修行になるかもしれない。
"思想的に分かりやすく、しかし技巧的には高度である"ことがイデオロギッシュになる時というのは、それが"真面目なイナカの人”を対象とした時に初めて成立するんです。思想がイデオロギッシュなんじゃない、その思想を入れる”型”が──そういう“型”を選択してしまう思想が、イデオロギッシュなんですね。(…)
藤原定家には歌論書というのが結構いっぱいあって、そこで色んなことを言ってるんですけれども、その内容と彼自身の歌とはとんでもなく違っているっていうのは昔っから言われてることです。「和歌は分かりやすいのが第一だ」なんて人には言っといて、自分の作る歌は全然そんなもんじゃない、とか。
お分かりでしょう? 彼が歌論書を与えた”人”っていうのは、新大衆の田舎者ンだったんですよ。そんな相手にホントのことを言ったってしょうがないって分かってて、彼は”大衆相手の分かりやすいハウツー書”を作ってたんですね。
カルチャー・スクールの元祖で家元の最初というのはこういうこと。
p.128-129
これはカルチャースクール一般に対するイヤミではあって、言い方を変えれば
「名前に惹かれてやってくる人に実質なんて分からない」と。
ただそれは文化の需給関係とは別次元の話であって、要するに
講師も受講者も(お金やイデオロギーによって)満足していれば市場は成立する。
「お金が全て」の資本主義社会では実質が軽視されるとはいうけれど、
(日本の大衆文化については)昔からそんなものはなかったらしい。
文化は生活の実質を充実させるためにあり、文化人が備える「文化の実質」は
生活に応用される際にその本質を骨抜きにされる。
だから(本質的に孤独ゆえ)文化を担う人々には様々な覚悟を必要としたのだろう。
それが境遇によって否応なく決定されていればいずれ達観が訪れるのだろうし、
あるいは外の世界を知らずに純粋培養されていれば(余裕の)風雅が醸されるのか。
そして、文化人が生活の実質をも獲得することは叶わないのか?
「既成から出ろ!」「既成を脱ぎ捨てろ!」が既に”既成”になってしまったら、それは二重の”既成”によって窒息させられるようなもんです。別の言い方をすれば、分かりやすい既成の本歌によって出口を塞がれてしまったに等しい。「人工の中から自然な叫びは生まれない」という単純な考え方は、「人工という既成現実はまた人間の自然の叫びをねじ曲げる」という、もっと大きな”本当”を理解しないんです。単純な正義感は屈折した心理を理解しない、とかね。“わざわざ人から”屈折”と言われかねないような心理状態を取らざるをえない必然性”なんていうものだってあるんですけどね。
新古今というものは、一言で言ってしまえば、「俺は簡単に理解されたくなんかないよ!」っていう叫びを、いとも素直に述べた和歌世界ということにもなりましょう。
素直であらんが為に「バカに分かられたくないね!」っていう装飾をふんだんに凝らした世界──つまり現代の新人類なんです。
p.133-134
簡単に言えば「素直にひねくれる人間も存在し得る」と。
素直にひねくれる人間は、素直な自分を人に理解されたいと思っても、
”素直”な人からは屈折しているようにしか見えないから諦めるしかない。
共生的な身体が生育過程で損なわれた人間には、共生に実感が伴うことがない。
…どうにも救われない話だと思ってしまうが、人間以外ではありえない現象ながら、
人間だからこそ別途救われる方法もあって、きっとそれは、
「徹底的に頭で生きる」ことだろうかと想像する。
昔(千年近く前)の日本の身分の違いは、お互い想像を絶するものであったのか。
世界広しといえども、折にふれて和歌を詠んで、その後はなにかっていうと俳句を詠んで、自分の周りにある“風景”というものを人間感情でどこもかしこもビショビショにしちゃった文化は他にあるまいっていうようなもんですが、日本文化っていうのは、自分の中には自分がなくて、自分を探したかったら自分の周りの風景にさわれっていう、初めっからアイデンティティーなんてものを無視してる文化なんですね。言ってみれば、自分という”肉体”はなくて、”自分”を知りたかったら、感じたかったら、自分にふさわしい“衣装”をまとえという、そういう文化ですね。
自分というものは平気で”空洞”になってるから楽だけど、でも探そうとするとどこにもないから苦しい──日本が”伝統的日本”を捨てて”西洋近代”っていうのを求めたのは、この後者”自分が見つからなくて苦しい”からの脱却をはかりたかったからですね。
p.152-153
現代日本において「西洋近代化はどこまで進んだか?」を考えるにおいて、
本書はよいテキストになると思う。
和魂と洋才の比率がどの程度であるのか。
きっと本書を読めば「和魂の残存比率」の想定値がガクンと下がるだろう。
ちと散漫に過ぎたか…
p.s.
野暮ですが、「ひと言コメント」の後半は英訳すればわかるダジャレです。
(前半の「課長風月」は本書中に数多くあるハシモト氏の「名言」のひとつです)
しかしああ書くと着色料みたいだな…「赤色102号」とか。
投票する
投票するには、ログインしてください。
こんにちは、chee-choffもとい、せんだです。
読書が趣味→生活→生活+仕事、とどんどん高じています。
書評のスタイルにとらわれず、「読めば読みたくなる文章」を心がけて文章を載せています。
多種多様、あるいは謎のテーマで三冊本のセットを組んで販売するネット古書店をやっています。
興味がありましたら一度HPにお越し下さい。
本業は現在「ブリコラジール」という屋号で個人事業をやっています。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:筑摩書房
- ページ数:349
- ISBN:9784480038654
- 発売日:2003年07月01日
- 価格:819円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。