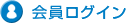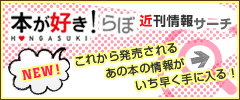レビュアー:
▼
科学ってどうやって始まってどうやって現在に至るの?
知人が大学時代、科学史(科学哲学)を専攻していて、よく話を聞いた。疑似科学と反証可能性やらパラダイム論やら。そのときに話したことから僕が理解したことは、科学というものは思った以上に恣意的で人間的で、始まりは宗教的でさえあることだ。
アインシュタインが量子力学の不確定性原理のことを聞いて「神はサイコロを振らない」と言ったそうだが、そもそも科学は神の創りたもうた自然を解き明かす神聖な学問だったのである。
そんなことだから、科学者は世界がシンプルで美しい法則で成り立っているに違いないと信じ、普遍性のある(誰もが納得できる再現性を持って証明できるもの)法則があると信じ、それを解き明かそうとして、科学の営みを行なっていたということだ。
仮説について。
仮説は塗り替えられていくものだが、塗り替えられた仮説に関しても専門家が幾人も試行錯誤して辿り着いたものであって素人が簡単に覆せるものではないし、専門家であっても何通りものチェックを経てようやく定着したものだということも知った。つまりは現在の科学も進行形で変化しているということだ。
さらに、基本的にポッと出てきた論に対しては基本的に疑ってかかり自らの手で試す(考える)営為だということも理解できた。
とまあ、知人がそんな感じのことを言い聞かせてくれていた経緯もあって東日本大震災の原発事故後に起きたヒステリックな各方面の反応について自己判断をする際に迷うことなく、いかがわしい言説に惑わされずに済んだ。
(EM菌とか、放射性物質に対する知識とか、もしかしたらスピリチュアルなことに対して、そんなに詳しくなくても、「これはおかしいだろう」と感覚的に思うことができた)
しかし、SNSやテレビを観ているとそういういかがわしい言説に惑わされる人は多くいるみたいで、なぜ惑わされるのだろう?それはどういう構造でもってそういう考えを持たされる人が多い(少なくともビジネスになる程度には)という状況になっているのかと気になるようになった。
大抵の場合、そういった疑似科学的なものだったりスピリチュアルなものに傾倒している人の言葉は、「現代社会は歪んでいるからこそ、その中にはない言葉を信じようとしている」ように見える。実際はがっつり取り込まれているのだけれど、少なくとも本人の意識の中では「歪んだ現代社会の中で、自分と自分の仲間は正しいことをしている」と思っているように見える。
これを僕は現代社会=現代の科学と読み換えることもできると思っていて、だから、なぜ現代の科学が歪んでいると思われるようになったのか? 具体的に書くと東日本大震災以降、日本で科学がどうやって扱われてきたのか? それ以前に世界で科学はどのように生まれ浸透してきたのか? といった疑問が僕の頭のどこかに常にいるようになった。
そんなわけで、科学史や科学哲学には結構興味があって、どこで勧められたかもう覚えていないが、本書『思想史のなかの科学』はその興味を満たすはじめの一歩にちょうど良いとタイトルや概要を読んで思っていたのである。
長い前置きだったが、結果として上述した僕の知りたかった「世界における科学についての概要」を知ることができたのは嬉しいことだった。
本書は、科学史の概要を書いたものである。昨今、問題意識として原子力や環境破壊など科学がもたらしたものに対して疑いを持たれることが多いが、どうもその場合、「科学を冠するものは全部嫌だ。科学以前の素朴な暮らしに戻ろう」みたいなものになりやすい。
本書では「現在の科学には限界があることも分かってきたのでその意見は理解できるが極端である。次に進むためには今までの科学を踏まえたものでなければならないはずで、だからこそ、現在の科学がいったいどういうものかをまず解き明かすことが重要である」という立場を取っている。
ということで、科学ってどうやって始まってどうやって現在に至るの?ということを概観していくのである。
本書では、まず人類史を5つの段階として捉える。
1.人類革命→類人猿から人間になったときまで
2.農業革命→農業の誕生と浸透
3.都市革命→農業の浸透の結果として王を中心とした都市が生まれる
4.哲学革命→ギリシア(アリストテレス)、インド(ウパニシャッドからの仏教)、中国(孔子など諸子百家)による現在まで続く思想的基軸が生まれた
5.科学革命→17世紀の西欧にて、理論と実験が結びついた現在まで続く科学が生まれた(我々が「科学」というときはこの科学革命で生まれた科学のことを指している)
本書の素晴らしいところは、5番の科学革命からではなく、3番の都市革命以降から説明していくところだ。
我々が知っている科学以前にも科学と言えるものがあって、それがなぜ?どうやって?西欧でだけ現在の科学たりえたのかを教えてくれる。
例えば、メソポタミアやエジプトなど古代文明でも高度な天文学や数学の知識があったことは割と有名だと思うが、それは実際的・実用的な知識であって、理論的な背景は神話に求められていたことだとか、中国やインドで生まれた科学についても教えてくれる。
この中にギリシア科学も含まれる。アリストテレスやピュタゴラスのことだ。純粋に理論として世界の秘密を解明しようとしているものである。当時は手を動かす仕事は奴隷の仕事だったので、実験をするとか実証するとかそういった発想は持てなかったようだ。
これが近代社会の成立により、階級がなくなり職人と学者の交流が進むことによって、ギリシア以来の理論的な考え方を、実験によって証明していく、現在の科学に通じる作法が生まれたのだ。
その特徴は、物事を要素に還元していくことで、全ての物質は原子の離合集散でできているのだから、これを解き明かせば、その物質を支配することができるというような考え方である。それらの要素がそれぞれの機能を果たすことで世界は回っており、その法則を解き明かす、ということでもある。機械論的自然観というやつだ。
この考え方がどんどんと進んでいった結果、原子力開発を生み、科学が社会を豊かにするものとして制度となり経済を回す存在になっていったことで、現状の科学では扱いきれないほどの結果=地球環境の破壊を招いたというわけだ。その反面で現代人が受け取った恩恵は計り知れないけれども、結果、社会的にも環境的にもあらたな問題を招いてしまったのも事実である。
本書では、「だからといって今までの考え方自体を否定するのはおかしくない?」と言っているわけだが、なかなか科学革命の次はやってこないので悩ましい……という感じの終わり方になっている。
途中、面倒になってだいぶ端折ったが大体こんな感じの内容で、特に面白かったのは、量子論が出てきたあたりで、科学者にとって不確定性原理は「いままでの俺たちって何だったの!?」と怒りたくなるような転回だったことがよく分かった。
17世紀からとはいえ、神が創りたもうた自然の法則を解き明かすために「もっとシンプルで美しい法則があるはず!」とか頑張っていたはずなのに、量子の世界に入ってみたら「ごめんなさい、そもそも確定しないものなの」ってことになったのだから「神が創りたもうた世界がそんな曖昧模糊なはずはないっ!!!!!」と怒って然るべきである。正直この時代の科学者のことを勝手に想像してかわいそうとか思っちゃうのである。
自分の中の疑問がかなりの部分、解決したので素晴らしい本だったと思うのだけれども、物足りない点もいくつかあって、それは、「日本では科学はどういう扱われ方をしてきたのか?」ということと「情報革命についてもう少し突っ込んで欲しかった」ということ。
前者はどんな本を読めば良いか分からない。後者については本書[改訂新版]が2002年初版なので仕方ないとも思っている。スマホ以前でありブロックチェーンやIoT以前のことなのだ。ということで、テイストはだいぶ違うがWIRED日本版の元編集長・若林恵『さよなら未来』を読んでみようと思う。
カルチャー寄りにはなるが、本書の次に読むことで「現在」を考えるときの参考にきっとなるはずだという直感があるのだ。
アインシュタインが量子力学の不確定性原理のことを聞いて「神はサイコロを振らない」と言ったそうだが、そもそも科学は神の創りたもうた自然を解き明かす神聖な学問だったのである。
そんなことだから、科学者は世界がシンプルで美しい法則で成り立っているに違いないと信じ、普遍性のある(誰もが納得できる再現性を持って証明できるもの)法則があると信じ、それを解き明かそうとして、科学の営みを行なっていたということだ。
仮説について。
仮説は塗り替えられていくものだが、塗り替えられた仮説に関しても専門家が幾人も試行錯誤して辿り着いたものであって素人が簡単に覆せるものではないし、専門家であっても何通りものチェックを経てようやく定着したものだということも知った。つまりは現在の科学も進行形で変化しているということだ。
さらに、基本的にポッと出てきた論に対しては基本的に疑ってかかり自らの手で試す(考える)営為だということも理解できた。
とまあ、知人がそんな感じのことを言い聞かせてくれていた経緯もあって東日本大震災の原発事故後に起きたヒステリックな各方面の反応について自己判断をする際に迷うことなく、いかがわしい言説に惑わされずに済んだ。
(EM菌とか、放射性物質に対する知識とか、もしかしたらスピリチュアルなことに対して、そんなに詳しくなくても、「これはおかしいだろう」と感覚的に思うことができた)
しかし、SNSやテレビを観ているとそういういかがわしい言説に惑わされる人は多くいるみたいで、なぜ惑わされるのだろう?それはどういう構造でもってそういう考えを持たされる人が多い(少なくともビジネスになる程度には)という状況になっているのかと気になるようになった。
大抵の場合、そういった疑似科学的なものだったりスピリチュアルなものに傾倒している人の言葉は、「現代社会は歪んでいるからこそ、その中にはない言葉を信じようとしている」ように見える。実際はがっつり取り込まれているのだけれど、少なくとも本人の意識の中では「歪んだ現代社会の中で、自分と自分の仲間は正しいことをしている」と思っているように見える。
これを僕は現代社会=現代の科学と読み換えることもできると思っていて、だから、なぜ現代の科学が歪んでいると思われるようになったのか? 具体的に書くと東日本大震災以降、日本で科学がどうやって扱われてきたのか? それ以前に世界で科学はどのように生まれ浸透してきたのか? といった疑問が僕の頭のどこかに常にいるようになった。
そんなわけで、科学史や科学哲学には結構興味があって、どこで勧められたかもう覚えていないが、本書『思想史のなかの科学』はその興味を満たすはじめの一歩にちょうど良いとタイトルや概要を読んで思っていたのである。
長い前置きだったが、結果として上述した僕の知りたかった「世界における科学についての概要」を知ることができたのは嬉しいことだった。
本書は、科学史の概要を書いたものである。昨今、問題意識として原子力や環境破壊など科学がもたらしたものに対して疑いを持たれることが多いが、どうもその場合、「科学を冠するものは全部嫌だ。科学以前の素朴な暮らしに戻ろう」みたいなものになりやすい。
本書では「現在の科学には限界があることも分かってきたのでその意見は理解できるが極端である。次に進むためには今までの科学を踏まえたものでなければならないはずで、だからこそ、現在の科学がいったいどういうものかをまず解き明かすことが重要である」という立場を取っている。
ということで、科学ってどうやって始まってどうやって現在に至るの?ということを概観していくのである。
本書では、まず人類史を5つの段階として捉える。
1.人類革命→類人猿から人間になったときまで
2.農業革命→農業の誕生と浸透
3.都市革命→農業の浸透の結果として王を中心とした都市が生まれる
4.哲学革命→ギリシア(アリストテレス)、インド(ウパニシャッドからの仏教)、中国(孔子など諸子百家)による現在まで続く思想的基軸が生まれた
5.科学革命→17世紀の西欧にて、理論と実験が結びついた現在まで続く科学が生まれた(我々が「科学」というときはこの科学革命で生まれた科学のことを指している)
本書の素晴らしいところは、5番の科学革命からではなく、3番の都市革命以降から説明していくところだ。
我々が知っている科学以前にも科学と言えるものがあって、それがなぜ?どうやって?西欧でだけ現在の科学たりえたのかを教えてくれる。
例えば、メソポタミアやエジプトなど古代文明でも高度な天文学や数学の知識があったことは割と有名だと思うが、それは実際的・実用的な知識であって、理論的な背景は神話に求められていたことだとか、中国やインドで生まれた科学についても教えてくれる。
この中にギリシア科学も含まれる。アリストテレスやピュタゴラスのことだ。純粋に理論として世界の秘密を解明しようとしているものである。当時は手を動かす仕事は奴隷の仕事だったので、実験をするとか実証するとかそういった発想は持てなかったようだ。
これが近代社会の成立により、階級がなくなり職人と学者の交流が進むことによって、ギリシア以来の理論的な考え方を、実験によって証明していく、現在の科学に通じる作法が生まれたのだ。
その特徴は、物事を要素に還元していくことで、全ての物質は原子の離合集散でできているのだから、これを解き明かせば、その物質を支配することができるというような考え方である。それらの要素がそれぞれの機能を果たすことで世界は回っており、その法則を解き明かす、ということでもある。機械論的自然観というやつだ。
この考え方がどんどんと進んでいった結果、原子力開発を生み、科学が社会を豊かにするものとして制度となり経済を回す存在になっていったことで、現状の科学では扱いきれないほどの結果=地球環境の破壊を招いたというわけだ。その反面で現代人が受け取った恩恵は計り知れないけれども、結果、社会的にも環境的にもあらたな問題を招いてしまったのも事実である。
本書では、「だからといって今までの考え方自体を否定するのはおかしくない?」と言っているわけだが、なかなか科学革命の次はやってこないので悩ましい……という感じの終わり方になっている。
途中、面倒になってだいぶ端折ったが大体こんな感じの内容で、特に面白かったのは、量子論が出てきたあたりで、科学者にとって不確定性原理は「いままでの俺たちって何だったの!?」と怒りたくなるような転回だったことがよく分かった。
17世紀からとはいえ、神が創りたもうた自然の法則を解き明かすために「もっとシンプルで美しい法則があるはず!」とか頑張っていたはずなのに、量子の世界に入ってみたら「ごめんなさい、そもそも確定しないものなの」ってことになったのだから「神が創りたもうた世界がそんな曖昧模糊なはずはないっ!!!!!」と怒って然るべきである。正直この時代の科学者のことを勝手に想像してかわいそうとか思っちゃうのである。
自分の中の疑問がかなりの部分、解決したので素晴らしい本だったと思うのだけれども、物足りない点もいくつかあって、それは、「日本では科学はどういう扱われ方をしてきたのか?」ということと「情報革命についてもう少し突っ込んで欲しかった」ということ。
前者はどんな本を読めば良いか分からない。後者については本書[改訂新版]が2002年初版なので仕方ないとも思っている。スマホ以前でありブロックチェーンやIoT以前のことなのだ。ということで、テイストはだいぶ違うがWIRED日本版の元編集長・若林恵『さよなら未来』を読んでみようと思う。
カルチャー寄りにはなるが、本書の次に読むことで「現在」を考えるときの参考にきっとなるはずだという直感があるのだ。
お気に入り度:









掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
本屋を応援する活動BOOOKSHOP LOVERです。本が好き!の中の人でもあります。
主に本屋の本と本の本、デザイン周りが好きですが、SFも好きです。社会系の本もちゃんと読みたいところ。積ん読しまくりであります。
- この書評の得票合計:
- 37票
| 読んで楽しい: | 1票 | |
|---|---|---|
| 素晴らしい洞察: | 3票 | |
| 参考になる: | 33票 |
あなたの感想は?
投票するには、ログインしてください。
この書評へのコメント

コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:平凡社
- ページ数:366
- ISBN:9784582764307
- 発売日:2002年04月01日
- 価格:1470円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。