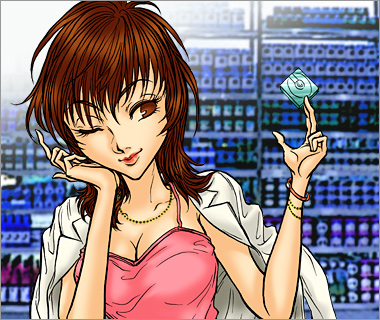レコメンデーションの虚実(10)〜「テープを作ってあげるよ」から生まれるボランティア精神とリスペクト:ソーシャルメディア セカンドステージ(1/2 ページ)
“俺のすばらしいセレクション”をレコメンデーションに
『ハイ・フィデリティ』というイギリスの小説がある。2000年にジョン・キューザック主演で映画化もされた。主人公のロブは、しがない中古レコード店の経営者。恋人の女性弁護士ローラが家を出て行ったのをきっかけに、自分自身の人生を問い直す作業を強いられるという物語だ。だがこの小説のおもしろさはそんな本筋のストーリーよりも、ロブと彼の店で働く内気なディック、尊大なバリーといううだつの上がらない3人の男が、他人のためのミュージックテープ作りにいつも熱中しているところにある。
「おはよう、ディック」
彼はあわてて巨大なヘッドフォンをはずそうとし、そのせいで片方が耳にひっかかり、もう片方が目の方までずりさがる。
「ああ、やあ。やあ、ロブ」
「遅れてごめん」
「いや、いいんだ」
「いい週末だったかい?」
ぼくはドアの鍵をあけ、彼は持ちものをかき集める。
「うん、まあ、まあまだね。カムデンでリコリス・コムフィッツのファーストを見つけたよ。テスタメント・オブ・ユースのやつさ。イギリスじゃリリースされなかったんだぜ。日本からの輸入盤だけなんだ」
「すごいじゃないか」彼が何を言っているのか、クソほどもわからない。
「テープを作ってあげるよ」
「ありがとう」
「セカンドが好きだって言ってたもんね。<ポップ、ガールズ、エトセトラ>。カバーにハッティ・ジャックスが写ってるやつ。でも、カバーは見たことがないんだよね。ぼくがテープを作ってあげただけだったから」
たしかに彼はぼくのためにリコリス・コムフィッツのテープを作り、ぼくはそれを気に入ったと言ったのだろう。ぼくの部屋は、ディックが作ってくれたテープでいっぱいだ。聞いてみたことは、ほとんどない。(『ハイ・フィデリティ』ニック・ホーンビィ、森田義信訳、新潮文庫)
この小説では、「他人の作ったミュージックテープ」がさんざんな皮肉の対象にもなっているが、しかしこれはレコメンデーションの1つの可能性でもある。自分が「この人のセレクションはすばらしい」と思う人にミュージックテープを作ってもらう。そこにはそのセレクションに対する安心感と、作ってくれた人に対するリスペクトがある。作る側には、「この人にすばらしい音楽を教えてあげたい」というボランティア精神、そして「どうだ、俺の趣味はこんなに凄いんだよ」という自分のセレクションに対する誇らしさが同居している。
ボランティア精神と尊敬の念と
集合知を形作るものが、送り手側のボランティア精神と受け手の側のリスペクトだとすれば、このミュージックテープというのはまさしく集合知モデルの萌芽である。それが単なるミュージックテープでしかなく、集合知にならないのは、あくまでもミュージックテープという存在が恋人同士、あるいはロブのレコード店の内輪のやりとりでしかないからだ。しかしこれが「多対多」のやりとりになれば、集合知を介したレコメンデーションとなりうる。
そのシステムを作り出そうとしているのが、フェイバリット・ディー・ビーという会社だ。セコムの研究所で人工知能の研究をしていた三村啓氏と、日本生命で財務に携わっていた仁科公男氏が2004年に設立したベンチャーである。同社はフェイバリットDBというサイトを運営している。
構想はかなり昔からあったようだ。1990年代後半、ある日仁科氏がタワーレコードの店内で、アメリカ発のフリーペーパーを手に取ったところから企画はスタートした。フリーペーパーには、こんな特集が掲載されていた。「無人島に持って行くCDリスト」。もしあなたが無人島に行くとしたら、音楽CDは何を持って行きますか?――というのを読者投稿でセレクションしようという記事である。
仁科氏は、その中のひとりの読者のCDリストになんだかピンと来た。リストの中に自分と同じ好みのCDが含まれていたからだ。とはいえ、自分の知らないCDもリストアップされている。さっそくその未知のCDをタワレコで購入して聞いてみると、これがドンピシャリ! 自分の好みとかなり一致していたのだった。
「例えばある音楽ジャンルのライトユーザーが、ヘビーユーザーの作ったお勧めCDリストをきっかけに、ヘビーユーザーの世界へと入り込んでいく。昔だったらジャズ喫茶やロック喫茶にそういうヌシみたいなヘビーユーザーがいて、そうした人の好みを知ることによって自分の好みを深く掘り下げていくことができた。そういうことをウェブの仕組みとして作ることができないだろうかと考えたのです」
仁科氏はそう話す。検索エンジンでは、そういう仕組みは作ることができない。まだ出会っていない作品の名前やアーティスト名などの固有名詞を知らなくても、自分のほんわかとした曖昧な好みだけをキーにして、自分好みの傑作と出会えるためには――そのためには、「先達(せんだつ)」となるようなヘビーユーザーにお勧めをしてもらうのがベストプラクティスである。しかしこの先達と<わたし>が、趣味が合わなければ意味がない。趣味の合わないヘビーユーザーに「これを聞け!」としつこく進められても、冒頭に紹介したレコード店のロブのように、「ぼくの部屋は、ディックが作ってくれたテープでいっぱいだ。聞いてみたことは、ほとんどない」とウンザリしてしまう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR