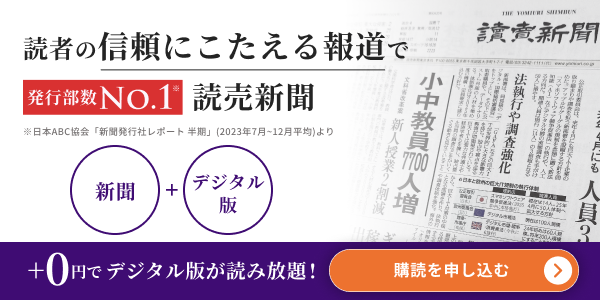グーグル・アップルと対決、動き出すかモバイル規制…政府が「事前」を検討する理由
完了しました
グーグルとアップルによる2社寡占状態のスマートフォン関連市場。その競争上の課題と対策案をまとめた政府の「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」が注目されている。対策案の柱となるのは、これまでの独占禁止法では想定されていなかった「事前規制」。デジタル市場で進む独占・寡占への特効薬となるのだろうか。(編集委員・若江雅子)
27の競争上の課題を検証
報告書は、政府のデジタル市場競争会議が昨年夏以降、関係事業者から膨大な聞き取り調査を行ってまとめた280ページにもわたる「大作」だ。グーグルとアップルが圧倒的な影響力をもつスマホのOS、ブラウザー、アプリストア、検索サービスなどの各市場における27の競争上の懸念について検証し、対策を提案している。
例えば、スマートフォンで使われているブラウザーは、アップルの提供する「サファリ」とグーグルの提供する「クローム」でほぼ100%。検索エンジンは、ほぼグーグルの1社独占だ(検索サービスとしては、一定のシェアを持つヤフーも検索エンジンはグーグルを使っている)。

報告書では、アイフォーンの場合はサファリが、アンドロイドOSのスマホならクロームが、それぞれあらかじめインストールされていて、アンインストール(削除)することもできなくなっていると指摘。アンドロイドOSのグーグル検索もアンインストールできないという。このためユーザーがスマホ購入直後から2社のサービスを使い続けている、と分析している。
この対策として、アップルとグーグルに、検索エンジンとブラウザーを選択制とし、ユーザーにわかりやすい表示を義務づけることや、自社サービスを削除できなくすることを禁じるなど複数の案を提示している。
世界は「事後」から「事前」に
このように、問題が発生する前に義務や禁止事項を定める規制は「事前規制」といわれる。今の独占禁止法が、基本的に問題が発生してから処罰する「事後規制」であることを考えると、その手法には大きな差がある。
これについて、「これまでの競争法のアプローチだけでは、デジタル市場の問題を解決するには限界がある」と説明するのは、報告書のとりまとめにあたった同会議ワーキンググループ委員でもある川浜昇・京都大教授(競争法)だ。
独禁法で違反を立証するには、調査のための時間や人手がかかる。「ビジネスの成長スピードがはやいデジタル市場の場合、事後的な介入では手遅れになる恐れがある」と川浜教授は言う。デジタル市場特有の立証の困難さもあるとされ、日本の公正取引委員会がこれまで海外プラットフォーム事業者の違法性を認定して法執行したことは一度もない。
デジタル時代の独占・寡占にどう対処すべきか。こうした悩みに、世界の競争当局は既に、対象を巨大プラットフォーム事業者に絞った上で、事前に禁止する法規制を整備し始めている(表)。

ドイツでは日本の独占禁止法にあたる競争制限禁止法を改正し、2021年1月に施行した。一定の条件を満たした企業を指定して、自社優遇や自社サービス利用の強制などを禁止する。既にグーグルを指定し、さらに現在、アップル、アマゾン、フェイスブック(現・メタ)についても対象とするかどうか調査を続けている。
EUでも今年3月、デジタル市場法案(DMA)が議会と理事会の間で暫定合意に至った。EU域内の年間売上高が75億ユーロ以上、アクティブユーザーが月間4500万人以上、3か国以上のEU加盟国でサービスを提供している、などの条件をみたす事業者に対し、自社優遇などの行為を禁じる。
実は、昨年施行された日本のデジタルプラットフォーム透明化法も事前規制の一種だ。ただ、事業者の自主性を重んじ、「取引条件等の情報開示」や「自主的な取り組み」、自己評価の報告など緩やかな規制にとどめた。当初は自社優遇などを事前に禁止する案が検討されていたが、事業者の反対で流れた経緯もある。
仮に今後、日本が欧米型の強い事前規制に
罰金100万円のみ
EUのデジタル市場法案では、違反があれば前会計年度の世界総売上高の最大10%、違反が繰り返される場合は20%の制裁金が科される。例えばグーグルの昨年の売り上げは2576億ドルなので、制裁金を科すとすれば10%でも257億ドル(約3兆3000億円)。一方、日本の透明化法の罰金は最大100万円だ。

透明化法に限らず、日本の事業者規制は「制裁力」が弱い。欧州競争法は、違反事業者の全世界での売り上げの10%を上限に違反で得た売上高に最大30%をかけた基礎額のほか、裁量での加算も可能だ。違反行為に係る期間は上限なく乗じる。これに対し、日本の独禁法は算定期間が調査開始時から過去10年間まで。算定率は最大10%で、裁量による加算もできない。
日本の「制裁水準」が低く設定されている背景には、もちろん経済界の反対もあるが、内閣提出法案の審査を行う内閣法制局の考え方も影響しているといわれる。課徴金の性格を「制裁ではなく、不当利得を
消費者の権利との関係は?
一方で、中間報告が競争上の問題を解決するために示した「案」の中には、それによってセキュリティーやプライバシーなどの消費者保護のレベルを低下させるのではないかと、不安になるものもある。
例えば、「サイドローディング禁止」の位置づけだ。サイドローディングとは、認められたストアやウェブサイト以外からアプリなどをダウンロードすること。アイフォーンでは、アプリはアップルの運営するアプリストアのみで配信され、サイドローディングを認めていない。

報告書はこれに「アプリストアへの掲載可否をアップルが握るため、高い手数料でも拒否できない」「アップルの自社アプリは手数料不要で不公平」などの懸念をあげ、「サイドローディング許容の義務化」を含めた提案をする。
これに対し、アップルは「セキュリティー保護のため必要」と反論。サイドローディングを認めているアンドロイドOS端末は、アイフォーンの最大47倍のウイルス感染が確認されたとも主張する。技術に明るくない人も含めてスマホが広く普及していることを考えれば、その主張に共感するユーザーも少なくないだろう。
プライバシー保護の観点からは…
報告は、プライバシー保護のための自主的取り組みも「競争上の懸念」とする。
ユーザーが気づかない間に広告会社などに自分の利用情報を送信してしまい、オンライン上の行動を追跡される問題を解決するため、アップルはブラウザーやOSに、ユーザーの同意なしに第三者が追跡できない仕組みを導入した。これらは、スマホの利用者情報が個人情報保護法で保護されない日本では、この問題に対するユーザーの数少ない自衛手段となっている。
だが報告書は「トラッキングにユーザーの許諾が必要になり、フェイスブック(などの広告会社)潰しになる」「アップルの広告事業を有利にする」などと指摘する。
アプリ事業者や広告事業者に不都合な取り組みを制限すれば、競争政策上の効果は期待できるかもしれないが、一方でセキュリティや消費者保護政策からみればマイナスになってしまう。競争とプライバシーなどの人権の関係はどう考えるべきなのだろうか。
EUのデジタル市場法案の場合、指定事業者に義務づけられる措置は「GDPR(一般データ保護規則)、電子通信プライバシー保護指令、サイバーセキュリティ、消費者保護及び製品の安全性に関する法制に準拠した上で実施される」とあり、セキュリティや消費者保護の確保が前提となっている。

プライバシー法制に詳しい森亮二弁護士は「日本の法規制はGDPRほど厳しいものではなく、自主的取り組みがプライバシー保護に果たす役割は大きい。公正な競争環境を重視してプラットフォーム事業者の自主的取り組みを制限するのであれば、同時に消費者保護のための規制強化も必要になるだろう」と話す。
中間報告への意見募集は10日まで行われている。EUや英国では競争評価の報告書を出すと、多い時で数千単位の意見が寄せられ、市民団体からの意見も多いという。公正な競争と消費者保護が両立する社会を築くには、市民を含む様々なステークホルダーが声を上げることが必要だ。