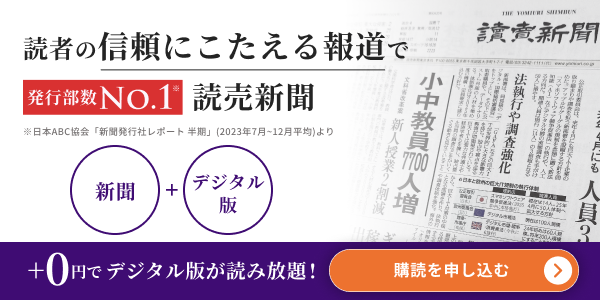[戦後80年/昭和百年]国際秩序<下>薄れる「核のタブー」
完了しました
広島、長崎での惨劇を世界中が改めてかみしめた、昨年12月の日本原水爆被害者団体協議会(被団協)へのノーベル平和賞授賞式。その翌日、ノルウェー・オスロで開かれた関連会議で、米ブラウン大の政治学者、ニナ・タネンワルド上級講師が厳しい口調で語った。

「ロシアは公然と核の脅しを繰り返している。こんなことは歴史上初めてだ」
タネンワルド氏は1990年代、核兵器を二度と使用してはならないとする「核のタブー」が、長い年月を経て規範化されたとの考えを提唱した。
戦力による抑止ではなく、惨禍を繰り返さないとする国家の自制こそが、核戦争の危機を回避させてきたと自著などで論じてきた同氏は、「核の不使用という伝統の重みを、我々は再認識すべきだ」と強調した。
1950年に起きた朝鮮戦争では核の使用が検討され、62年のキューバ危機では核戦争勃発の危機が目前に迫った。それでも、国際社会は瀬戸際で踏みとどまり、暗黙の了解とも言える国際規範を築いてきた。被団協の平和賞受賞は、被爆体験の証言活動が、そうした核のタブーの形成に大きく貢献したためとされる。
しかし、そのタブーが今、根底から揺らいでいる。
ウクライナ侵略を続けるロシアは昨年11月、核攻撃に踏み切る要件を緩和した。「どこかで核爆発を起こす必要がある」との脅しの声も政治家らから上がる。イスラエルでは閣僚が「ガザでの核使用は選択肢の一つ」と発言して物議を醸した。
欧州では冷戦後、米国の戦術核撤去を求める動きが広がったが、2022年のウクライナ侵略以降、その機運も急速にしぼんでいる。
フランスは同年11月、防衛に関する指針「国家戦略レビュー」を改定し、「強固で信頼できる核抑止力」を第一の戦略目標に掲げた。軍事的中立の立場を続けてきたフィンランドやスウェーデンは、相次いで北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、米国などの「核の傘」に入る道を選んだ。
「核を使わないことが当然という国際環境をロシアが壊し、秩序が大きく揺らいだ」と話す一橋大の秋山信将教授は、「核の脅しに対しては核による抑止が必要だと、皆が思うようになった」と指摘する。
人類滅亡まで「89秒」。米科学誌が28日に発表した「終末時計」の残り時間は過去最短となり、分析を担当した専門家グループはこう指摘した。「核兵器の使用についてのタブーが弱まっている兆候がある」
核軍縮の道、風前の灯
戦後、核兵器使用や核開発競争への懸念が強まる中、国際社会は核不拡散や核軍縮の体制を整えてきた。
1970年、核兵器の不拡散、核軍縮、原子力の平和利用を推進することを目的とした核拡散防止条約(NPT)が発効した。冷戦期の米国とソ連(現ロシア)との間では、中距離核戦力全廃条約(INF条約)や戦略兵器削減条約(START)が結ばれ、核戦力の抑制に寄与した。
しかし、長年かけて積み上げられてきた、これらの枠組みは、今や風前の
2022年のNPT再検討会議では、「核兵器は二度と使われてはならない」「核兵器数の減少傾向の維持」といった内容を含む最終文書案にロシアが反対した。会議は決裂し、NPT体制の危機が叫ばれる。
米露間で唯一残る核軍縮の枠組み、新戦略兵器削減条約(新START)を巡っても、プーチン露大統領が23年2月に条約の履行停止を表明。米国は対抗措置として、条約で定めるロシアへの核戦力データの共有を停止した。
中国の動向
中国は、2大核大国の米露を猛追すべく核戦力の増強を急激に進めている。
米国防総省の年次報告書によると、中国の核弾頭数は24年半ばに600発を超え、30年には1000発に達する可能性が高い。カナダ・クイーンズ大のジェーン・ボールデン教授は、「NPT体制などの既存の国際的枠組みでは、中国の核軍拡を制御することはもはや困難だ」と話す。
米国のトランプ大統領は今月23日、「非核化が可能かどうか確かめたい」と、核軍縮に向けロシアや中国と協議する意欲を見せ、ロシアも協議に前向きな姿勢を示した。
ただ、トランプ氏は第1次政権時にも米露中による核軍縮の枠組みを模索したが、中国が応じなかった経緯がある。中国がさらに核軍拡を進め、米露中の3大核大国となれば、新たな枠組みの構築はより困難となるだろう。
非核兵器国、特に「ならず者国家」への核拡散防止も厳しい状況にある。
ストックホルム国際平和研究所によると、NPT脱退を一方的に宣言した北朝鮮は、すでに50発の核弾頭を保有していると推定される。
高濃縮ウランの製造を進めるイランでは昨年10月、イスラエルとの攻撃の応酬を受けて、最高指導者アリ・ハメネイ師が核兵器の保有や使用を宗教令で禁じた「核ドクトリン」の変更を求める書簡を国会議員39人が連名で提出。核保有の議論が公然と進む。
生物・化学兵器
核兵器と並び、使用が「絶対的なタブー」とされてきた生物・化学兵器についても、シリア内戦を通じてそのタブーが破られた。
在英の民間団体「シリア人権ネットワーク」によると、シリアの旧アサド政権は、13年に化学兵器禁止条約(CWC)に加盟したが、その後も条約を無視して化学兵器を180回以上使用したとされる。
ロシアもウクライナで化学兵器を使用しているとされ、ウクライナ軍は2000人以上が被害を受けたと報告する。ウクライナの戦場では、クラスター弾や対人地雷といった非人道的兵器も次々と復活を遂げた。
ニューヨーク市立大大学院のトーマス・ワイス名誉教授は、「核兵器や生物・化学兵器といった『タブー兵器』の使用のハードルが下がってきている」と危機感を示し、「国際社会は国連などでタブー兵器を巡る問題に改めて焦点を当て、その監視に真剣に取り組む姿勢を示すことが重要だ」と訴える。(ジュネーブ支局・船越翔、パリ支局・梁田真樹子)

滅亡へ針進む
「終末時計」(Doomsday Clock)は、米国の科学誌「原子力科学者会報」が毎年1月下旬に、世界の終末までに残された時間として公表している。残り時間を定めるのは、核や気候変動、破壊的技術など多彩な分野の専門家らで構成する「科学安全保障委員会」。年に2回、世界情勢などについて話し合い、時計の針の位置を決める。1947年に「終末の7分前」と設定した後、針は今年を含めて26回動いている。
当初は核戦争のリスクが「残り時間」の算定要素だったが、その後は気候変動や、生命科学など新技術がもたらす危険性も考慮することにした。昨年からは生成AI(人工知能)がもたらすリスクにも言及している。