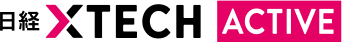インテルは2006年10月27日、報道関係者向けに最新技術動向や新製品情報を紹介する「インテル・クライアント・レギュラー・アップデート(第5回)」を開催した。
冒頭にインテルの吉田和正共同社長が登壇した。2006年11月に投入する、新型CPUの名称を「Core 2 Extreme QX6700」であると紹介した。1つのCPUの中に、4つのCPUコアを内蔵したハイエンドデスクトップパソコン向けのクワッドコアCPUだ。コアが2つの従来製品「Core 2 Extreme X6800」と比べて、最大70%の性能向上が得られるという。また、より安価なデスクトップパソコン向けのクワッドコアCPU「Core 2 Quad」を2007年第1四半期に投入すると語った。
続いて同社マーケティング本部長の阿部剛士氏が、2007年前半に発表を予定しているノートパソコン向けプラットフォーム「Centrino Duo」の次世代版「Santa Rosa(サンタローザ、開発コード名)」の構成要素について説明した。基本的な構成要素がCPU、チップセット、無線LANチップの3つであることは、従来のCentrinoやCentrino Duoと変わらない。変更点は、各構成要素の強化にある。
まず、CPUは現在のCore 2 Duoからより電力効率と性能を高めた後継製品になる。次に、チップセットも新型の「Crestline(クレストライン、開発コード名)」と呼ぶ製品を採用する。CPUとチップセットを結ぶFSB(フロントサイドバス)も667MHzから800MHzに引き上げられる。また、Crestlineには、グラフィックス機能を内蔵するものとしないものがあるが、内蔵型はグラフィックス性能を従来よりも高めるという。無線LANチップには「Kedron(ケドロン、開発コード名)」と呼ぶ製品を採用する。まだ正式な規格認証は終わっていないが、次世代の無線LAN規格「IEEE802.11n」対応製品と連携できるよう事前テストを重ねる。
PCI Express接続のフラッシュメモリーを搭載することで、アプリケーションの起動時間を短くしたり、消費電力を少なくしたりする技術「Robson(ロブソン、開発コード名)」や、高速無線通信「WiMAX」については、「次世代版Centrino Duoのロゴ取得条件ではなく、オプションで対応する予定」(阿部氏)と説明した。
2007年前半には、超小型ノート「Ultra Mobile PC(UMPC)」の第1号を発表する。2008年にはTDP(実使用上の最大消費電力)が1W以下のCPUを搭載し、「バッテリー駆動時間が最低でも8時間となることを目指す」(阿部氏)という。
デジタルホーム向けプラットフォーム「Viiv」についても説明した。Viiv対応機器のコンテンツを、Viivに対応しないノートパソコンでも視聴できる新開発のソフトウエア「メディア・シェア・ソフトウエア」を紹介。これを使えば、Viiv対応パソコンやViiv対応デジタル機器の中にある静止画や動画を視聴したり、コピーしたりできる。
メディア・シェア・ソフトウエアの対応製品はCentrino DuoおよびCentrinoノート。ソフトウエアの提供方法は、ユーザーの手によるダウンロードという形ではなく、パソコンにプリインストールすることを各メーカーに働きかける予定。2007年には搭載パソコンが登場することを期待したいとしている。
| クワッドコアCPUの「Core 2 Extreme QX6700」とハイパー・スレッディングに対応した「Pentium 4(3.2GHz)」の処理速度を比較したデモンストレーションを実施した。10枚のRAWデータ画像をJPEGデータに変換するのにかかる時間を比べている。Pentium 4(右)が2分8秒ほどかかるのに対して、Core 2 Extreme(左)は約45秒で完了する |