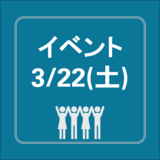”子どもたちの居場所づくり”を目指したきっかけ
ユースセンターとは、家でも学校でもない、若者たちの“第三の居場所”のこと。北海道の砂川市にある「みんなの秘密基地」もその一つです。
2022年に子どもたちのユースセンターとして活動を開始して以降、放課後や土曜日になると、近隣の子どもや若者たちが集まり、ゲームをしたり、おしゃべりをしたり、勉強をしたりと、皆、思い思いに時間を過ごしています。
代表の望月亜希子さんに、子どもや若者たちの居場所づくりをはじめたきっかけについて伺いました。
「私は元々、会社員として自然素材のコスメティックブランド「SHIRO」を展開する株式会社シロで働いていました。砂川市に本社工場があり、地域の子どもたちのために職業体験イベントや工場見学を開催していました。そこでは、楽しんでいる子どもたちがいる一方、自分の意見を決められなかったり 、自分に自信が持てず「私なんて」と嫌いになってしまっていたりする子どもたちがいることに気づきました。そして、そういった子どもたちが、自分のこと好きなまま、自己決定を繰り返しながら成長して社会に羽ばたいていってほしいという想いを抱くようになりました」
その後、望月さんは2019年に会社を退職し、2020年度から特別支援教育支援員(※)として学校に勤務することに。子どもたちに寄り添いたい、そんな想いを持って小学校、中学校で働き始めましたが、同時に教師とは違う特別支援教育支援員という立場ではできることが限られてしまう現実に、もどかしさも感じるようになっていました。
※発達障害や学習障害のある児童生徒に個別的な支援を行う支援員
まちづくりプロジェクトへの参画をきっかけに、ユースセンターの立ち上げに動き出す
ちょうどその頃、望月さんの前職の株式会社シロの代表取締役会長である今井浩恵氏から、砂川市の活性化を目的に立ち上げる「みんなのすながわプロジェクト」の構想を持ちかけられました。これはシロの本社工場の移設増床にともない、ものづくりや観光をテーマにした施設を地域の人たちと一緒につくるまちづくりプロジェクトであり、その参画メンバーとして望月さんも活動に携わることに。
「工場の新設により、シロのショップやカフェなども新工場の施設に移転することが決定したため、そのカフェの空き店舗を有効活用するなら、『ぜひ子どもたちの居場所を作りたい!』と手を挙げ、即答で承諾してもらいました。当時は学校の中で支援員として働いていましたが、学校や家庭に居場所がないような子たちも、安心してここにいていいんだと思える場所を作りたかったのです。」
こうしたきっかけから、カフェの空き店舗を活用して、学校や家庭でもない子どもたちのサードプレイスとなるようなユースセンターをつくりたいという想いが具体化していったといいます。
休眠預金活用で立ち上げることができた「みんなの秘密基地」
自分のやりたいことの方向性が見えてきた望月さんは学校での特別支援教育支援員としての業務と並行して、居場所作りの準備や仲間集めに取り掛かるも、ユースセンターはもちろん、非営利団体の運営経験はなく、何から準備をしたらいいのかわかりませんでした。そんな矢先、教育支援活動を行う認定NPO法人カタリバが休眠預金活用事業の2021年度通常枠で採択された「ユースセンター起業塾」の実行団体を募集していることを知りました。
ユースセンター起業塾とは、全国各地でユースセンターを運営する・運営したいという団体・個人への経営支援を行う事業です。実行団体に選ばれると、資金支援に加えて経営支援などの伴走支援が行われるのも大きな特徴です。
この募集要項を目にした途端、自分たちのやりたいことと合致すると確信した望月さんは、申請をし、無事に採択されたそうです。
「右も左も分からず、とにかく勢いだけで動いていた私にとって、この事業はまさに渡りに船でした。さらに、教育支援の実績が豊富なカタリバさんの支援を受けられることも心強く、毎月のミーティングや研修、経理、財務などのバックオフィスに関する相談会などもあり、常にきめ細やかにサポートしていただきました」
そこからは、カタリバによる支援を受けながら、仲間も増えていきますが、シロのショップとカフェが移転するまでには、まだ1年。その期間に借りられる場所を探すことに。
そこで、シロでも長年お世話になっている市内のお寺に相談すると、快くお堂を無償で貸してくださることになりました。こうして小学校3年生~高校生を対象にしたユースセンター「みんなの秘密基地」の活動がスタートしたのです。
2023年6月には、拠点を旧シロ砂川本店の店舗へ移し、活動をしながら気づいたことを解決しようと、午前中には「無料のフリースクール」を開始。厨房を活用した「みんなのごはん(子ども食堂)」や、20代以上の若者を対象にした「夜のユースセンター」、同じテーマで悩む大人の「つながるお茶会」なども始まり、活動の幅も広がっていきました。
そこで大きな助けになったのがユースセンター起業塾の助成金だったそうです。
「スタッフもボランティアでずっとお願いするわけにはいかないため、家賃や光熱費のほか人件費にもあてられる助成金にとても助けられました。また子ども食堂などの活動費にも使うなど、私たちの運営や活動全体を支えてくれています」

新しくオープンした拠点の外観(左)と2階で放課後を過ごす子どもたち。