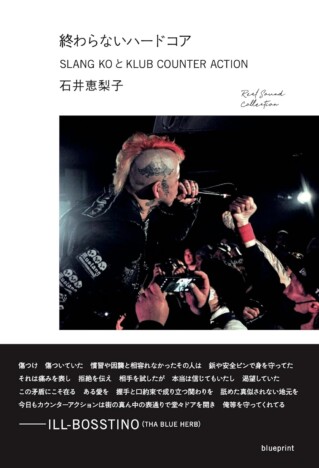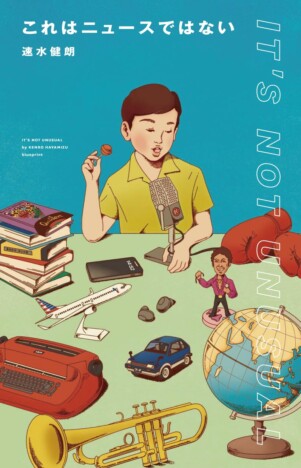松坂桃李主演『雪の花 ―ともに在りて―』が描く職業倫理 医者はなぜ“先生”と呼ばれるのか

良策が悩む「先生」の形、そこから降りて学ぶもの

医療、それは私たちが生きる上で欠かせぬ技術である。怪我や病気といった様々な理由で私たちは医者のもとを訪れ、「先生」に助けを乞う。……しかしなぜ医者は「先生」なのだろうか? 1月24日に公開された、吉村昭の同名小説を原作とする映画『雪の花 ―ともに在りて―』はそんな疑問に答えてくれる映画だ。今回は天然痘根絶に奔走した無名の医者を通して本作が見せる、本当の偉大さについて考えてみたい。
江戸時代末期、天然痘(疱瘡)は発病すれば手の施しようのない恐るべき病であった。福井藩の町医者である笠原良策(松坂桃李)は人々を救うため西洋医術(蘭方)の門を叩き、彼のもとで学ぶ日々の中で種痘という予防方法があることを知る。海外との交易が厳しく禁じられている中、良策はどうにか「種痘の苗」を取り寄せるべく力を尽くしていく……。

本作は、日本における種痘の黎明期を描いた作品である。とはいえ、主人公である笠原良策の名を聞いたことのある人はあまりいないだろう。松坂桃李演じるこの町医者はとにかく真面目な人物であり、それゆえ物語のスタート時点で大きな悩みを抱えている。それは天然痘が多くの人の命を奪う事態に対して、医師として何もできないことだ。
当時の医療水準では周囲への感染を防ぐために患者を隔離することしかできない。良策は、患者の家族に「先生」「先生どうか」と膝をついて懇願されてもどうすることもできない自分が歯がゆくてたまらず、自分に医者の資格があるのかとまで思い悩んでしまうほどだ。人を救う仕事に就きながらそれを為せない自分のどこに「先生」と呼ばれる偉さがあるのか、というジレンマに良策は苦しんでいる。
しかし面白いのは、ジレンマを解決する手段となる蘭方に対し、良策が一度は否定的な反応を示したことだ。
良策は大武了玄(吉岡秀隆)という医者と出会い蘭方の話を聞くが、漢方と大きく体系の異なるそれに当初彼は不快そうであった。けれど『解体新書』の解剖図と、実際に解剖された罪人の臓器が寸分の狂いもなかったといった話を聞くうちに彼は考えを改め、遂には京の蘭方医・日野鼎哉(役所広司)の弟子になるべく門を叩くまでに至る。
ここで注目したいのは、西洋医術の技術的変化以上に良策の意識の変化だ。彼は了玄の話を聞く中で漢方が蘭方より「偉い」という意識を取り除いていった。つまり良策が蘭方を学ぶため弟子入りすることは既存の医者=「(漢方の)先生」からの離脱を意味する。事実、鼎哉「先生」の教えは決して蘭方だけではなく、そこには一生が学びであることや医者は名誉や利益を求めるべきでないといった理念までもが含まれていた。
良策にとって鼎哉は、医術のみならず文字通り人生の師だ。彼のもとで学んだことで良策は新たな「先生」の形を見つけ、それを実践していくこととなる。