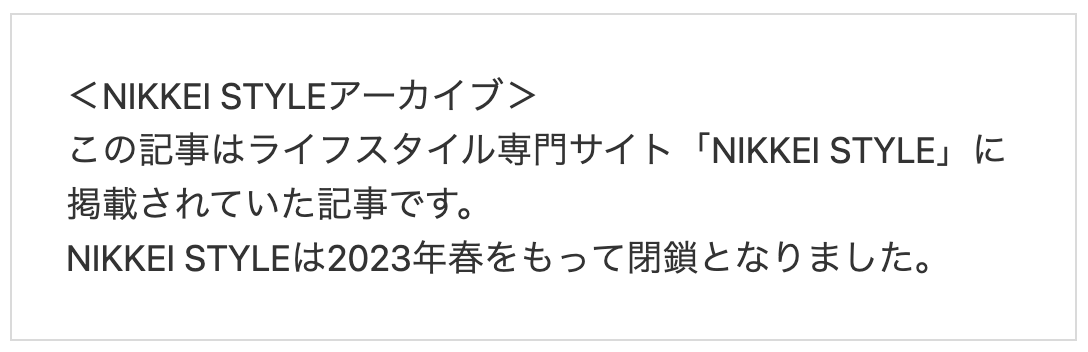はだし運転は違反? 間違いやすい交通ルール13問

あおり運転被害、6割が経験

調査では、理不尽だと思う交通ルールについても自由回答で尋ねた。目立ったのが「一時停止」と「自転車の原則車道走行」。前者は「徐行して確認すれば十分」「一時停止か否かの判断が恣意的」、後者は「現在の交通事情では危険」との意見だ。「速度違反」についても「形骸化している」「不公平感だけが残る」「制限速度を引き上げたうえで厳しく取り締まるべきだ」との声が上がった。
死亡事故にもつながる「明らかなあおり運転」の経験も調査した。59%が「受けた経験がある」と答えた。50代が71.5%と最多で、男性に限ると80%に達した。警察庁は昨年12月、車を使って暴行事件を起こすなど将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転手に対し、違反点数の累積がなくても免許停止ができる道交法規定を適用するよう全国の警察に指示している。
正答率13.8%

答えは×高齢ドライバーの重大事故が後を絶たない。運転免許の更新で「70歳以上」に高齢者講習が一律に課され、「75歳以上」は認知機能検査も加わる。混同したか、年代別の正答率は"当事者"に近い「60代以上」でも23%にとどまる。
認知機能検査を巡っては、2017年3月施行の改正道路交通法で規制が強化。「認知症の恐れ」(第1分類)と判定された場合は医師の診断が必須になった。認知症と診断されると免許取り消しや停止になる。従来は「恐れ」の判定でも交通違反がなければ診断を受ける義務はなかった。
運転には視野や反射神経など認知機能検査で測れない身体能力も影響する。高齢者には更新時に実技試験を課すべきだとの意見もある。高齢者に限らず、自分の運転技術を客観視する姿勢が大切だ。
正答率18.7%
答えは〇 道交法は左右の見通しがきかない交差点では徐行するよう定めているが、例外として「優先道路を通行している場合」「交通整理が行われている場合」を挙げている。優先道路は交差点内までセンターラインが連続していたり、道路標識で示されていたりする。交差点に差し掛かった場合、逆に優先道路でない側は特に注意が必要だ。出合い頭の衝突事故などの際は過失割合にも影響が出てくる。
警察庁によると、17年の1年間に信号機のない交差点で起きた交通事故は全国で11万4452件。うち出合い頭が7万5931件で約7割。優先道路を走る側も、制限速度の順守など安全運転を心掛けたい。
正答率20.1%
答えは〇 「自転車は原則、車道」だが例外もある。「自転車通行可」の標識がある場合のほか、70歳以上の高齢者や小学生以下の子供が運転する時だ。通行量が多いなど車道走行が危険な場合も認められる。
自転車は「軽車両」と定義されるが、数年前までは事実上、歩行者と自動車の間で中途半端な扱いだった。警察庁は11年、自転車が関係する事故やマナー違反を防ぐため、歩行者保護を柱とする自転車の総合対策を作成。歩行者との接触を防ぐため、自転車が通行できる歩道の幅員の目安を原則「2メートル以上」から「3メートル以上」に改めた経緯もある。自転車で歩道を走る場合は歩行者に注意したい。
正答率22.7%
答えは× 居眠り運転などによる重大事故を招く「過労運転」。交通違反の点数でみれば無免許運転と同じ25点だ。道交法では「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定めている。
12年に関越自動車道で乗客7人が死亡した高速ツアーバス事故や、16年の長野県軽井沢町のスキーバス転落事故などで、過労運転の危険性は再三指摘されている。国は運送会社などを中心に対策を強化。事業者に対し安全確保を怠った場合の罰金の上限を1億円に引き上げたり、運行管理者の必要人数を増やすなどしている。
正答率24.6%
答えは〇 バス専用通行帯(バスレーン)については知識があやふやな人も多いのではないか。公共交通機関の利用促進や交通渋滞緩和のための制度だが、交通法規上、原付きバイクは規制の対象外だ。警察がバスレーン走行を理由に取り締まり、指摘を受けて処分を取り消したケースもある。
大半のバスレーンは一番左側の第1車線に設定されているが、普通車なども左折時は交差点の手前でバスレーンに車線変更することが認められている。過去には「バスレーンを走ってはいけないと思った」という運転手が第2車線から一気に横切って左折を試みた結果、路線バスとぶつかる事故も起きている。
正答率29.5%
答えは〇 車の定員を数える時、法律上は12歳未満の子供3人で大人2人と扱われる。結果的に座席数以上の人数が乗れることになり、定員を守ってもシートベルトが足りない事態が起こり得る。その際、ベルト着用が法律上は免除されることがあるが、安全面からは極力避けたいところだ。後部座席でも、ベルトをしないと事故の際の死亡の危険が3倍以上に高まるとの調査もある。
シートベルトは道路交通法上、運転手が同乗者に着用させる義務を負う。2008年には後部座席の着用も義務化されたが、警察庁と日本自動車連盟(JAF)の17年調査では、一般道を走る車の後部座席の着用率は36.4%にとどまる。
正答率30.2%
答えは× 急ぐ時もあるだろうが、追い越しが法律で禁止されている場所は確認しておきたい。「勾配の急な上り坂」は禁止場所ではないが、坂の頂上付近での追い越しは禁止なので注意が必要だ。「追い越し禁止」標識がある場所のほか、トンネルや曲がり角付近、交差点や横断歩道、踏切なども同様だ。認められている場所でも、見通しが悪いと感じたら無理は禁物。追い越そうとする車の前の車両の動きなど、状況の冷静な見極めが大切だ。
「追い越し方」にもルールがある。原則は右からだが、路面電車や追い越そうとする車が右側に寄っている場合は、左側から追い抜かなければならないこともある。
正答率36.0%
答えは× げたやサンダルなどを例示して「安全な運転に支障のあるもの」を履いた運転を禁止する自治体はあるが、はだしでの運転自体は直ちに違反とはならない。ただ道路交通法は「ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めており、はだしでの運転が危険な状態と判断されれば違反に問われる可能性もある。性別・年代別の正答率は50代女性が27%と最も低かったのに対し、その娘世代にあたる18歳~20代女性は最高の49%だった。
正答率36.7%
答えは× 中央自動車道や山陽自動車道などの「高速自動車国道(高速道路)」は、最高速度だけでなく最低速度も決められている。法令上は「時速50キロ以上」で、標識などで別途定められた区間や豪雨などの災害時を除く。もちろん、危険回避などのために徐行するのは認められている。
首都高速や阪神高速などの「自動車専用道路」は、標識などで個別に指定されている場合もあるが、法令上一律に定められた最低速度はない。高速なのにのんびり走っている車を見掛けることがあるが、必ずしも違反ではない。
正答率40.3%

答えは〇「一時停止」「窓を開けて音を聞いて」「前の車が通過してから」。教習所の小さな踏切で繰り返した経験が習慣になっている人も多いだろう。踏切内への進入事故などを防ぐためだが、道路側に信号機がついている場合は信号に従えばいい。路面電車が幹線道路を横切る場所などにあるが、大都市では特に"レア物"だ。
正答率40.8%
答えは× 「客待ち」「荷待ち」は法規上「駐車」に含まれる。「荷物の積み下ろし」も5分以内は例外とされるが、ドライバーが車を離れていて、すぐに運転できなければ、駐車と判断されることもある。
調査では「駐車違反の判断はもう少し融通を利かせてほしい」との声もあったが、駐車違反は渋滞の原因になるばかりか、駐車車両を避けようとして事故を誘発したり、緊急車両の通行を妨げたりする危険もある。周囲への影響を常に考えたい。
正答率44.5%

答えは×高速道路で渋滞に出くわした時、最後尾の車が順番にハザードランプで注意を促す光景は行楽シーズンの風物詩だ。カーブの先の渋滞などでは衝突回避のためにも必須に思えるが、励行する自治体警察はあっても、法令上の義務はない。
正答率48.9%
答えは× 信号の右折矢印を巡っては12年から、以前は禁止されていたUターンが可能になった。右折レーンの渋滞緩和や対向の直進車との事故防止が狙いだ。ただ、道幅が狭く何度も切り返す必要がある場所などでは逆に渋滞が増える可能性もあり、交差点自体がUターン禁止のこともあるので要注意。30代男性の正答率が60%に達したのに対し、60代女性の62%は「禁止」だと思っていた。ルール改正を知らなかったのか定かではないが、交通ルールが見直されることは少なくないので、ドライバーは特に気を付けたい。
◇ ◇ ◇

「分かっているけど違反」もNO
「分かっているけど、やめられない」。何かの誘惑に負けた時、自分に言い聞かせがちなセリフだが、交通ルールでも同様のことがあるようだ。象徴的なのが、自転車絡みの違反。今回の調査では「ヘッドホンをつけて走行すると、違反で罰金をとられることもある」「急な降雨であっても、自転車に乗りながら傘を差せば違反になる」(いずれも正解)の正答率が90%を超えたが、それにもかかわらず街なかではよく見掛ける光景だ。規制そのものの是非には議論があっても、現行では違反であることに変わりはない。自転車だけなら免許は不要なため、必要に応じて幅広くルールを周知させる機会も大切だろう。
◇ ◇ ◇
ランキングの見方 冒頭の文章は問題文。順位下の数字は正答率。
調査の方法 運転に関するルールについて○×式で答える問題を30問作成。5月中旬にネット調査会社のマイボイスコム(東京・千代田)を通じ、運転頻度が「月1回程度」以上の18~20代、60代、40代、50代、60代の男女1000人(各世代とも男女同数)に調査を実施。問題文の正誤を正しく回答した人の割合が低い(間違えた人が多い)順に、正答率が50%を切ったものをランキングした。
[NIKKEIプラス1 2018年6月16日付]
NIKKEIプラス1の「何でもランキング」は毎週日曜日に掲載します。これまでの記事は、こちらからご覧下さい。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。