「JALの不祥事続発」、元社外役員が根本原因を問う 「パイロットの飲酒」など問題はなぜ繰り返される?

「日本航空(JAL)がこれまでパイロットの飲酒トラブルなど問題の起きるたびに講じてきた対策には、全社的に魂が入っておらず実効性がなかった」
青山学院大学名誉教授の八田進二氏は、「なぜJALで安全トラブルが繰り返し起きるのか」という問いにこう答える。八田氏は、JALが経営破綻後に再建を果たし再上場した2012年から2020年まで社外監査役を務めた。2018〜2019年に起きたパイロットの飲酒問題を目の当たりにしてきた。
昨年12月、オーストラリア・メルボルン発成田行き774便の機長と副機長(ともに解雇処分済み)が過度な飲酒をしたにもかかわらず、飲酒量を伏せて運航を強行した。JALは国土交通省への報告が遅れたことなども受け、業務改善勧告を受けた。
年が変わって2月4日、JALは四半期決算と併せて役員らの処分を発表した。赤坂祐二会長は安全管理の責任者である安全統括管理者から解任。2月5日から新しく安全推進本部長となった中川由起夫氏が安全統括管理者を務める。
赤坂会長と鳥取三津子社長は2カ月間、報酬を30%減額とする。ほかにも問題に大きく関わった運航本部長らは、執行役員の解任や降任といった処分がなされた。
2019年とほぼ同じ再発防止策
処分と併せてJALは、国交省へ再発防止策を提出した。①禁酒の実施、②パイロットの飲酒傾向の管理強化、③組織改革として安全意識・規定順守に向けた教育、④飲酒やアルコール検査に関わる理解度を定期審査へ反映させる――ことなどを行っていく。
注目すべきは、2019年の飲酒問題時に公表した再発防止策とほぼ同じ内容である点だ。当時JALは、①教育方法の見直しとパイロットの意識改革、②飲酒傾向の管理強化、③当時社長だった赤坂氏が安全統括管理者を兼任――などの措置を取った。
「対策に実効性がない」という八田氏の指摘もうなずける。また2019年のときも役員報酬を減額したが、八田氏は「当局への報告もあるだろうが、単に自己満足になってはいないか」と疑問を投げかける。














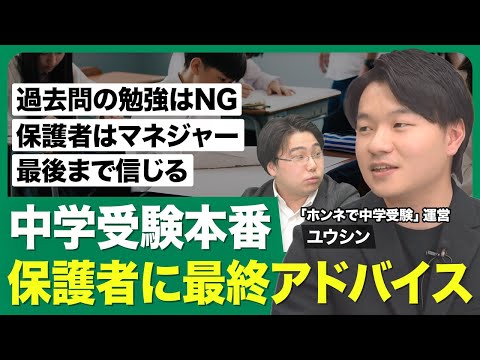



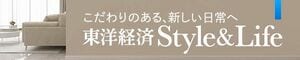
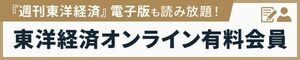











無料会員登録はこちら
ログインはこちら