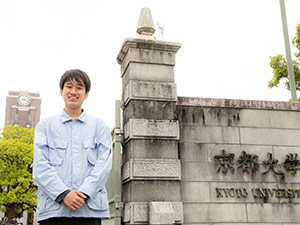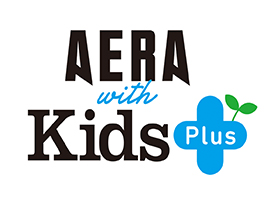文系、理系の壁
ベネッセ・木村治生さん「文系、理系の意識は小学校時代にできあがる」
2021.09.30

日本は高校の文理選択で文系、理系に分かれ、大学でも文理が交わることが少なく、社会人になっても文系、理系の意識を持ち続ける人が少なくないといわれます。しかし、現代的な課題を解決するには、学問の枠を超えた文理融合の知識や考え方が必要です。文系、理系の意識はどのように生まれるのでしょうか。各教科の好き嫌いについて学年別の変化を調査したベネッセ教育総合研究所の木村治生・主席研究員(東大客員教授)に聞きました。(写真は、宮崎大で開かれた高校生のサイエンス体験)
(きむら・はるお)2000年、ベネッセコーポレーション入社。子ども(乳幼児~大学生)、保護者、教員を対象とした意識や実態の調査研究、学習のあり方についての研究などを担当。文部科学省や経済産業省、総務省から委託を受けた調査研究にも数多く携わる。専門は社会調査、教育社会学。
算数・数学の好き嫌いが最も影響
――文系、理系を考えるにあたって、小学校高学年から高校にかけて、各教科の好き嫌いがどう変化しているかの調査が興味深いです。
東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所の「子どもの生活と学びに関する親子調査」の2018年のデータを用いて、国語、算数・数学、理科、社会、英語の好き嫌いが学年別にどう変化するのかを分析しました(調査対象1万1454人。小学4~6年生4928人、中学生3616人、高校生2910人)=下のグラフ。
全体にどの教科も学年が上がるにつれて、「とても好き」「まあ好き」が減り、「あまり好きではない」「まったく好きではない」が増えています。その傾向が特に顕著なのが、算数・数学で、理科も同様の傾向があります。国語、社会、英語も中学や高校で「嫌い」が増えますが、算数・数学や理科ほど強くはありません。
――算数・数学の「嫌い」が増えるのはなぜでしょうか。
教科の特徴だと思います。ベネッセ教育総合研究所の別の調査で、公立小学校15校の小学生を対象に子どもたちの教科観を調べたことがあります。小学3~6年生の回答を見ると、算数は「難しい問題が解けると、うれしい教科」では断トツで、「テストで良い点を取れると、うれしい教科」「いろいろな考え方ができて、おもしろい教科」「普段の生活に役立っていると思う教科」「大人になったときに役に立つと思う教科」でもトップでした。算数は子どもたちにとって特別な教科なのです。