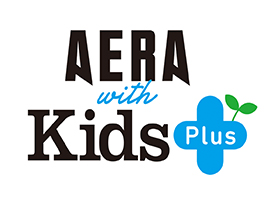文系、理系の壁
中央大・武石智香子副学長「AI・データサイエンス科目に文系学生が殺到」
2021.10.21

日本は高校の文理選択で文系、理系に分かれ、大学でも文理が交わることが少なく、社会人になっても文系、理系の意識を持ち続ける人が少なくないといわれます。そうした中で、文系学生にもAIやデータサイエンスを学ばせようという動きが広がっています。今年度から全学部生を対象に「AI・データサイエンス全学プログラム」を始めた中央大学の武石智香子副学長に、導入の経緯や学生の反応などを聞きました。(写真は、AI・データサイエンス教育に力を入れる中央大の授業の様子=同大提供)
(たけいし・ちかこ)早稲田大学第一文学部心理学専攻卒、ハーバード大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士。2001年中央大学商学部専任講師、13年商学部教授。19年から全学連携教育機構長となり、副学長も務める。専門は社会学、医療社会学。
入門編ツールに定員の7倍以上が応募
――2021年度から全学部生を対象に「AI・データサイエンス全学プログラム」を始めました。中央大学は文系の学生が多い大学ですが、どのような理由や経緯があったのですか。
中央大学は約2万5000人の学部学生のうち、理工学部の約4000人を除き、学生の84%が文系学部に所属しています。理工学部は後楽園キャンパス、文系学部の大半は多摩キャンパスにありますが、法学部が23年に茗荷谷キャンパスに移転することをきっかけに、文理融合教育の検討が加速しました。25年度までの中長期事業計画の中にAI・データサイエンス教育が盛り込まれ、20年にAI・データサイエンスセンターができました。
センターには教育部会と研究・社会連携部会があり、教育部会には全学部から教員が参加して教育プログラムをつくっています。
――文系が多い大学なので、受講するのも文系の学生が中心になりますね。
全学的にAI・データサイエンスはある程度知っておかなければいけない、リテラシーみたいなものだと考えています。AI・データサイエンス関連の教育は各学部でも行われていますが、どの専門にも資するような共通部分を全学プログラムとして新規に開講しました。
私は全学連携教育機構の機構長もしています。AI・データサイエンス教育の方向性をセンターが決め、それに基づいて授業の定員や講師の選任など授業の運営は機構が行っています。機構は多摩キャンパス、センターは理工学部のある後楽園キャンパスにあり、毎日のように連絡を取り合っています。
――全学プログラムの内容を教えてください。
リテラシー(入門)レベルの「AI・データサイエンスと現代社会」と「AI・データサイエンス総合」、応用基礎レベルの「AI・データサイエンス ツール」の三つで構成しています。「現代社会」は、社会で起きている変化や機械学習の基礎、セキュリティー、匿名加工情報などを学びます。「総合」はビジネス界と連携し、LINEなど大手SNSの社員などを講師に議論します。
ツールはⅠ~Ⅳまであり、エクセル、BIツール、プログラミング言語のPython、R、Rubyなどを学びます。来年度からは「AI・データサイエンス演習」が始まり、実データを使って実践的な学習をします。
――初年度の学生の履修状況はどうですか。
リテラシー科目の「現代社会」は、定員を設けておらず、前期、後期合わせて1087人の履修者がいます。予想していた履修者数が600~700人だったので、1年目で目標値を突破しました。学部別では総合政策学部や理工学部が多いです。いずれ全学生の必修科目にできればと希望しています。
「総合」と「ツールⅠ~Ⅳ」は、定員がありますが、いずれも定員を大幅に上回る応募がありました。中でも、エクセルやSPSS(統計解析ソフト)の使い方などを学ぶ入門編のツールⅠは、前期の定員100人に対して721人の応募がありました。倍率が7倍以上になったので、急きょ、後期も開講することにしました。文系向けと銘打っているツールⅠでも、これだけの応募者がいました。
ツールⅢも定員100人に対して345人の応募があり、こちらも急きょ、今年度は後期も開講することにしました。
初年度である今年は、学生のレベルを把握できておらず、どれくらいの学生がどの科目を希望するのかわからずに、応募者が定員を上回る結果になりました。今年は抽選で絞りましたが、来年度からは選考する予定です。