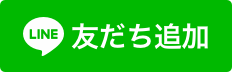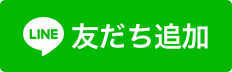自賠責保険は、事故の被害者救済を目的とした保険で、すべての車やバイクが加入しなければなりません。万が一、事故の被害者になって加入者が任意保険未加入だった場合、自賠責保険の適用を受けることができますが、どのように行えばいいのでしょうか。手続きの流れとともに、申請にはたくさんの書類が必要となるので、把握しておきたいところです。
この記事では、自賠責保険で被害者請求する方法と必要書類のほか、自賠責保険の被害者請求を行ったほうがいいケースと支払いまでの流れについて解説します。
もくじ
自賠責保険の被害者請求は、事故被害者が直接保険会社に請求する仕組み
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)とは、すべての⾞やバイクに対して加入が義務付けられた保険で、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は交通事故の被害者を救済するため、最低限の対人賠償を担っています。支払限度額は、下記のとおりです。
<自賠責保険における対人賠償の支払限度額>
- 死亡:3,000万円まで
- ケガ:120万円まで
- 後遺障害:4,000万円まで
自賠責保険の被害者請求とは、事故の被害者が自動車損害賠償保障法第16条にもとづき、加害者の加入する自賠責保険会社(または共済組合)に直接、治療費や休業損害に対する賠償金を請求する手続きです。
被害者は被害者請求を行うことで、示談成立前でも損害賠償金を受け取れます。
加害者請求との違い
自賠責保険の加害者請求は、自動車損害賠償保障法第15条にもとづいて、事故の加害者が被害者に損害賠償金を支払い、その後に自賠責保険金を自賠責保険会社(または共済組合)に請求する仕組みです。
被害者請求とは、保険会社に対する請求者が異なります。通常、事故による自賠責保険の請求は、加害者請求で行われます。
自賠責保険の被害者請求のメリット
自賠責保険の被害者請求を行うことで、何を得られるのでしょうか。ここでは、自賠責保険における被害者請求のメリットについて解説します。
加害者の対応にかかわらず補償を受けられる
自賠責保険の被害者請求を行うメリットとして、加害者の対応状況にかかわらず、加害者の加入保険会社から、直接損害賠償金を受け取れることが挙げられます。
これによって、加害者が示談になかなか応じなかったり、任意保険に未加入だったりした場合でも、被害者は治療や休業損害などに対して必要な補償を得ることができるでしょう。
審査や示談成立前に補償を受けることができる
自賠責保険の被害者請求を活用するメリットに、本請求の審査完了や示談成立の前でも、自賠責保険からの補償を受けられることも挙げられるでしょう。
これは、自動車損害賠償保障法第17条にもとづく「仮渡金」という制度によるもので、事故によるケガの治療費など、当座の支払いが必要な場合に有効です。ただし、仮渡金の受け取りには、一定の条件があります。
後遺障害等級の申請過程と認定結果に透明性と納得感がある
事故で後遺障害を負った場合、後遺障害等級認定の際の提出書類を用意する方法には、被害者自身で準備する自賠責保険の「被害者請求」と、加害者の加入する任意保険の保険会社に手続きを委ねる「事前認定」の2つがあります。
自賠責保険の被害者請求で提出書類を用意する場合、自分で行う分、透明性と認定結果に対する納得感が高くなるのはメリットといえるでしょう。
自賠責保険の被害者請求を行ったほうがいいケース
自賠責保険の被害者請求は、どのような状況で行うべきなのでしょうか。ここでは、自賠責保険の被害者請求を行ったほうがいいケースについてご紹介します。
加害者が任意保険に未加入のケース
事故が発生した場合、任意保険に加入していれば、通常は加害者の加入保険会社があいだに立ち、保険会社が自賠責保険分もまとめて賠償金を支払う「一括払い」を行います。
しかし、加害者が任意保険に未加入で、なおかつ手持ちのお金に乏しかったり、自賠責保険の加害者請求に応じなかったりする場合もあります。
そのようなケースでは、自賠責保険の被害者請求を行ったほうがいいでしょう。被害者側からの手続きにより、保険会社から自賠責保険の損害賠償金を受け取ることができます。
被害者の過失割合が大きいケース
自賠責保険の被害者請求を行ったほうがよいケースとして挙げられるのは、事故において被害者の「過失割合」が大きいケースです。
過失割合とは、事故における責任の割合を指すものです。通常、被害者の過失割合が大きければ、その分だけ受け取れる損害賠償額は減額されます。
しかし、被害者救済を目的とする自賠責保険では、被害者側に重大な過失がある場合を除き、過失割合によって減額されません。この場合の重大な過失は、「7割以上」となります。このため、被害者の過失が大きいケースでは、被害者請求で相手の自賠責保険から損害賠償金を受け取った方がよい場合があります。
| 被害者の過失割合 | 後遺障害または死亡 | 傷害 |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 |
示談交渉が長引くケース
加害者との示談交渉が長引いた場合、自賠責保険の被害者請求を行ったほうがメリットは大きいといえます。というのも、示談がまとまらなければ損害補償金の確定が遅れるため、先んじて必要となる治療費の支払いなどに影響が出るからです。
自賠責保険の被害者請求を行うことで、示談成立を待たずに損害補償金を受け取ることができます。
後遺障害等級認定の申請が必要なケース
後遺障害等級認定の申請が必要な場合で、仮に不認定となった場合に保険会社に対して不満や不信感を抱きそうだという場合、自身の気持ちの面で被害者請求を行うメリットがあります。相手の保険会社に手続きを任せる事前認定は手間を省けますが、書類の提出を相手に任せることで審査の不透明さや認定結果に対する不満が残る可能性があるからです。
もちろん、提出する書類が同じであれば事前認定でも被害者請求でも結果は変わらないのですが、被害者請求では、被害者自身が申請書類を準備・提出するため、認定結果に納得しやすくなります。
自賠責保険の被害者請求に必要な書類
事故の被害者が、自賠責保険の被害者請求を行う際には、たくさんの書類が必要となります。仮に、事故でケガをした場合の主な必要書類と入手先は、下記のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 委任状・委任者の印鑑証明 (第三者に委託する場合のみ) | 被害者から委任されたことを証明する書類 | 印鑑登録している市区町村 |
| 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 被害者が保険会社に対して損害賠償を求める書類 | 自賠責保険会社 |
| 交通事故証明書 | 事故事実を公的に証明する書類 | 自動車安全運転センター |
| 事故発生状況報告書 | 事故発生当時の状況を詳しく記載した書類 | 自賠責保険会社 |
| 診断書・診療報酬明細書 | ケガの内容や治療の詳細を記載した書類 | 医療機関 |
| 施術証明書 | 整骨院などで施術を受けたことを証明する書類 | 整骨院・接骨院 |
| 通院交通費明細書 | 通院にかかった交通費を証明するための書類 | 自賠責保険会社 |
| 付添看護自認書・看護料領収書 | 入退院の付き添いを受けた日数や期間を証明する書類 | 自賠責保険会社 |
| 休業損害証明書(給与所得者) 納税証明書、課税証明書、確定申告書など(自由業者、自営業者、農林漁業者) | 休業による減収の損害を証明する書類 | 休業侵害証明書:勤務先 納税証明書、課税証明書等:税務署または市区町村 |
| 印鑑証明書 | 損害賠償の受領者が被害者本人であることを証明する書類 被害者が未成年者でその親権者が請求する場合、印鑑証明のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要 | 住民登録している市区町村 戸籍抄本は本籍のある市区町村 |
| 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(後遺障害診断書) | 後遺障害の認定手続きに必要となる書類 | 医療機関 |
| レントゲン(X線)写真など | ケガの内容の詳細を証明する資料 | 医療機関 |
参照:自賠責保険・共済ポータルサイト「支払までの流れと請求方法」
このうち、「印鑑証登録証明書」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「診断書・診療報酬明細書」「保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書」は、ケガや死亡、後遺障害にかかわらず必要な書類となっています。
自賠責保険の被害者請求の手続きの流れ
自賠責保険の被害者請求を手続きするにはどのような手順を踏んだらいいのか、わからない人もいることでしょう。ここでは、自賠責保険の被害者請求の手続きの流れを解説します。
1.加害者の自賠責保険会社を特定し、書類を提出する
まず、加害者が加入している自賠責保険会社から書式を取り寄せ、必要書類を提出して被害者請求を行います。自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書に、事故当事者が加入する自賠責保険会社名や証明書番号といった情報が記載されているため、その情報を参考に特定しましょう。
2.審査機関にて損害調査を行う
加害者の自賠責保険会社へ提出された書類は、審査機関である損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へと送られ、損害調査が行われます。この過程では、事故の発生状況や支払いの的確性などが公正中立な立場で確認され、場合によっては当事者や医療機関への照会も行われます。
3.自賠責保険会社に審査結果が伝えられる
損害保険料率算出機構の審査が完了すると、その結果は自賠責保険会社に通知されます。審査結果の通知までには、1~3ヵ月程度の期間を要するので注意が必要です。
4.自賠責保険会社から損害賠償金が支払われる
審査結果を受け取った自賠責保険会社は、法律で定められた「支払基準」をもとにした損害賠償金を被害者に支払います。支払いは、指定口座に振り込まれる形式が一般的です。振込が完了した時点で、被害者請求は完了です。
自賠責保険の被害者請求の注意点
自賠責保険の被害者請求を行う際には、いくつか気をつけたいことがあります。ここでは、自賠責保険の被害者請求における注意点について解説します。
手続きに時間や手間、費用がかかる
自賠責保険の被害者請求に関する手続きには、時間と手間、費用などの負担が生じます。その理由として、交通事故証明書や後遺障害等級認定のための書類など、たくさんの書類を自力で用意しなければならないからです。診断書や公的書類は、発行にお金もかかります。
時間に余裕がなかったり、自分で行うことに不安があったりする場合は、任意保険の弁護士費用特約を使って、被害者請求の手続きを弁護士に依頼するのがおすすめです。
請求には3年間の期限が定められている
自賠責保険の被害者請求は、起算日から3年以内に行うという請求期限が定められています。この期限を過ぎてしまうと時効となり、損害賠償の請求権を失ってしまうことになるのです。
なお、事故の請求区分によって起算日は異なります。具体的には下記のとおりです。
<自賠責保険の被害者請求における請求区分別の起算日>
- ケガ:事故発生翌日
- 後遺障害:症状固定翌日
- 死亡:死亡翌日
事故によるケガや後遺障害の治療が長引いた場合、被害者請求を後回しにしたことで時効になるリスクがあるので注意しましょう。
自賠責保険の被害者請求に備えて、任意保険に弁護士費用特約を付帯しておこう
自賠責保険の被害者請求は、事故の被害者が加害者の自賠責保険会社に損害賠償金を直接請求するものです。示談成立を待たずに損害賠償金を受け取れるメリットがあり、当座の治療費を支払うのに役立ちます。
ただし、提出書類の入手や準備には、手間も時間もかかります。被害者請求の書類提出や、後遺障害等級認定の申請などは弁護士が代わりに行ってくれるため、万が一の際のために、任意保険に弁護士費用特約を付帯しておくと安心です。
ちなみに、保険会社によって、自動車保険の保険料や弁護士費用特約の内容は異なります。自分に合った自動車保険を探すには、複数の保険会社に確認する必要があります。加入や更新の際には複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。
難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もり依頼をしましょう。
自動車保険の保険料を複数の保険会社で比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。複数社の見積もりが一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。
ぜひ、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。