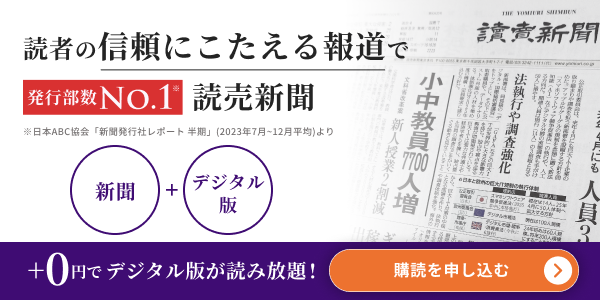富山県富山市「山家食堂」 3姉妹 母の店守り続けて
完了しました

連係プレー
富山県東部を走る富山地方鉄道の栄町駅を降りると、雪化粧した雄大な立山連峰が目に飛び込んできた。歩いて5分ほどで見える、小豆色のくすんだのれんが「山家食堂」の目印だ。目立たない店構えだが、8席の客席はすぐに埋まってしまった。

「今日はブリカマの良いのが入ってますよ」

入り口近くで調理に励む浦畑信子さん(71)が富山市内の漁港で上がったブリを使った焼き魚定食(1000円)を薦めてくれた。焼き上がると皿に盛り付けて、横にいる姉の鍋島貴美子さん(74)にパス。貴美子さんが小鉢を並べたお盆を、妹の工藤恵美子さん(69)が「おまちどうさま」とテーブルまで運ぶ。3姉妹の流れるような連係プレーだ。冬に旬を迎える、脂がのった塩ブリを大根おろしと一緒に食べると、口いっぱいに香ばしさが広がった。
味に妥協せず
店は3人の母・山口静子さんが1967年に開いた。店から望める立山連峰から、店名は「山家(やまや)」に。次女・信子さんは開店当初から母を手伝い、高校卒業後に本格的に店で働き始めた。長女・貴美子さんは40年ほど前、静子さんがくも膜下出血で倒れたのを機に帰郷。この後は2人で切り盛りした。

三女の恵美子さんが加わったのは9年前。きっかけは、千葉に単身赴任していた夫のくも膜下出血による急死だった。「何も手に着かなかった」という妹に手をさしのべたのが2人の姉だった。「ご飯でも食べにおいで」。妹を気遣う姉たちの一言で店を訪れるようになった恵美子さんも加わって、母が残した場所で「三人四脚」が続いている。
ランチタイムは午前11時半開店。午前9時頃、一番早い恵美子さんが店に入り、姉2人が深夜1時頃まで仕込んだ食材を火にかけたり、食器を並べたりして準備に励む。

市内の個人商店などから魚を仕入れるのは貴美子さんの担当だ。メニューは仕入れ状況を見ながら前日に3人の相談で決める。原価割れすることもあるが、味に妥協はしたくない。大抵の姉妹げんかは、味と値段のバランスを巡って勃発するという。
つややかで甘みのあるお米は立山町の農家・松井和夫さん(66)から直接仕入れる。自ら精米する貴美子さんは「顔の見える人から買っているのでおいしさは保証しますよ」と自信たっぷりだ。
ケセラセラ
店は常に順風満帆だったわけではない。約30年前には向かいにある県立病院の建て替えに伴う道路拡張工事で、一時移転を迫られた。「やめ時だよ」「もう少しやろうよ」。当時、店で働く2人の姉は、決心できなかった。
仮設店舗で営業を続けると、変わらず訪れる常連客に「まだできるよ」と励まされ、「やめる」と言えなくなった。工事終了後、それまでは借りていた店の土地を購入し、続けることになったという。

1日の能登半島地震でも棚から皿が落ちる被害があった。4日の予定だった今年の営業開始を9日に延ばした。
明るい声を響かせる3人だが、信子さんも夫を、貴美子さんも息子を亡くしたつらい思い出がある。「この店と仕事があるから、何とかやっていけている」と恵美子さんが振り返るように、母が残した食堂は3人が「帰る場所」だ。
カウンターの後ろにあるふすまを開けると、亡き母の写真が置かれ、今も店を見守る。「お母さん、今日もよろしくね」。開店直前、写真に向かって手を合わせるのが信子さんの習慣だ。
東京大空襲を経験し、家族と離ればなれになった経験のある母は「ケセラセラ(なるようになるさ)」が口癖だった。「結局私たちはお母さんのこの店に集まってきちゃうのよ」と信子さん。「後ろを向かない人だった」という母から託された店で、3姉妹はこれからも客の心と胃袋を温め続ける。(富山支局 川尻岳宏)