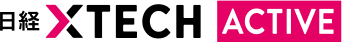水害や地震,火災で損傷したハードディスク・ドライブ(HDD)からデータを復旧できるか検証した。水道水に沈めたHDDからデータが復旧できた割合は67%。水から引き上げた後に乾燥しないよう濡れたタオルでHDDをくるんでおくとデータの復旧率は向上した。
水害,地震,火災──。災害は忘れた頃にやってくる。災害でダメージを受けたハードディスク・ドライブ(HDD)からデータを復旧できるのか。「水害」「地震」「火災」の3種類の災害を想定してHDDを損傷させ,そこからデータを復旧できるか検証した(図1)。
 |
| 図1●「水害」「地震」「火災」で損傷したハードディスク・ドライブ(HDD)からデータが復旧できた割合 HDDに保存されている全データ容量を100%とした場合,水没後に乾燥したHDDからは約67%のデータが,落下したHDDからはすべてのデータが復旧できた。一方,200℃で30分間加熱したHDDからはデータが復旧できなかった [画像のクリックで拡大表示] |
その結果,水に濡らした後に2日以上乾燥させたHDDからは,総ファイル容量の約67%を救出できた。100cmの高さから落下したHDDからはすべてのデータを復旧できた。200℃で30分間加熱したHDDからは,1バイトのデータも復旧できなかった。
検証に利用したHDDは,米Seagate TechnologyのUltra ATA対応HDDの中古品で,容量は40Gバイト。これは3年ほど前のエントリ・サーバーに搭載されていたHDDと同等のスペックである。HDD内に画像(JPEGファイル)およびPDFファイルを計4475個(768Mバイト)保存して,復旧対象のデータとした。
HDDは「プラッタ」「磁気ヘッド」「軸受け」「制御基盤」など複数の精密部品で構成されている(図2)。HDDが被災すると,これらの精密部品が損傷する。被災したHDDからデータを復旧するには,損傷した個所を特定し,交換/修理する作業が伴うため,一般的には復旧サービスを提供している専門会社に依頼することになる。
 |
| 図2●実験で利用したハードディスクの内部構造 米Seagate TechnologyのUltra ATA対応HDD(容量は40Gバイト)。3年ほど前のエントリ・サーバーで採用されていたHDDと同等のスペックである |
復旧作業は,HDDが被ったダメージの大小により内容や工数が異なる。半日程度で済む場合もあれば,3カ月以上かかることもある。「破損がひどくても,時間を多くかけるほど復旧できる容量は増える」(検証作業を実施したアドバンスドテクノロジーの金田龍介氏)。今回の検証では,作業日数を最大3日間と定め,その期間内で復旧できるデータの割合を調べた。
アドバンスドテクノロジーの場合,復旧にかかる料金は「HDDの損傷状態」と「復旧対象のファイル容量」により決まる。水道水に水没させた実験ではHDDの損傷が比較的小さかったため,復旧料金は12万7600円で済む。一方,食塩水に水没させた実験は,HDDの損傷が激しく複雑な作業工程が必要だったため,復旧料金は38万3000円となる。
専門会社に復旧作業を依頼するにしても,被災現場でユーザーがやっておくべきことや,やってはいけないことはある。次回以降,検証から分かった「HDDにダメージを与えると何が壊れるのか?」「ファイルの復旧率や復旧にかかる期間はどうか?」「現場で注意すべき点は何か?」を災害別に解説する。
|