ストレージは「仮想化」と親和性が高い。サーバー機などが個々のコンピュータとして扱われてきたのとは異なり,ストレージはそもそもがコンピュータから「論理的なビュー」として扱われてきた。現実の製品実装において,ストレージとはディスク・ドライブの集合体であり,ユーザーやOS/アプリケーションから見たストレージ領域(ボリューム容量)は,「使っているディスク・ドライブは何か?」「そのディスク・ドライブの中の,どの記憶領域を使っているのか?」といった物理的な構成とは独立している。
このようにストレージは,歴史的に見て古くから「論理ビュー」と「物理実装」を分離する仮想化の考え方を採用してきた製品分野である。物理実装はブラックボックスであり,論理ビュー,すなわちボリュームだけを見ていれば,それでよかった。エンタープライズ向けストレージ技術としてよく知られるRAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)も,性能や可用性の向上を目的に,複数のディスク・ドライブを論理的に1個のボリュームとして使えるようにしたものだ。
こうしたストレージの仮想化をさらに一歩進めるアイデア/技術として注目され,最新トレンドとなっているのが,ストレージ・ベンダー各社がこぞって実装を進める「シン・プロビジョニング」(Thin Provisioning)である。この仮想化機能を使うと,ストレージを構成する物理実装であるディスク・ドライブの数を,大幅に減らせる。ディスク・ドライブの数が減るのに伴い,消費電力や設置コストも削減できる。
“容量”を仮想化して稼働率を向上
シン・プロビジョニングとは,ボリュームの“容量”を仮想化して,キャパシティ・プランニング(容量設計)を不要とする技術である(図1)。例えば,実際には全体で容量1Tバイト分のディスク・ドライブしか用意していなくても,それとは無関係に,10Tバイトのボリュームを設定して運用することができるようになる。OS/アプリケーションからも,当然ながら10Tバイトのボリュームとして認識される。これは,シン・プロビジョニングが登場する以前には,無かった考え方である。
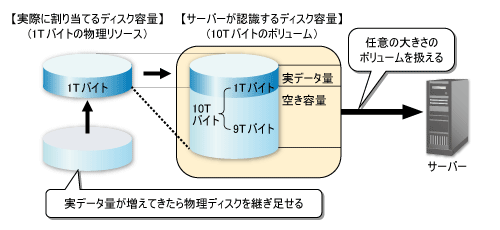
まずはボリュームについて,基本的なことを押さえておこう。ボリュームとは,いわば仮想化された論理ビューである。ボリュームにアクセスするOSやアプリケーションは,そのボリュームに,どのようなディスクが割り当てられているのかを知る必要はない。一方で,物理ディスクは,この論理ビューに対して実際のデータ記憶領域を提供するリソース(資源)となる。物理ディスクの集合体がリソース・プールとなり,このリソース・プールから個々のボリュームに,「ディスク・ドライブ」という単位よりも,さらに細かい単位で,データ記憶領域が割り当てられる。
このように,論理的な存在である「ボリューム」と,「ディスク」という物理実装は,互いに独立している。1台のディスクに複数のボリュームを設定することもできるし,複数のディスクを1つのボリュームとして使うこともできる。複数のディスクを複数のボリュームとして使う場合において,どのディスクのどの記憶領域が,どのボリュームに割り当てられているのか,という細かい物理実装を,全く意識する必要がない。ただ単に,ボリュームという単位でのみ,管理していればよいのである。
ただし,RAIDという従来の仮想化手法において,物理リソースの構成とボリュームは独立していたものの,「ボリューム容量」に関しては,完全に物理構成に依存していた。つまり,RAIDの種類と,ボリュームを構成する物理リソースの容量に応じて定まっていた。例えば,1Tバイトのディスクを2台のディスクでストライピングしたセットをさらにミラーリングしたRAID1+0構成では,使っているディスク4台の物理容量の合計が4Tバイトに対して,ボリューム容量は最大2Tバイトとなる。この物理容量を超えたサイズのボリュームを定義することはできず,容量10Tバイトといった仮想的なボリュームが得られるわけではなかったのである。












































