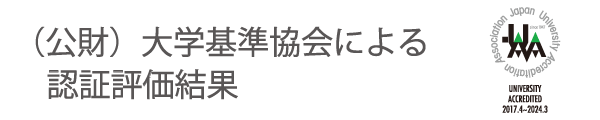吉田 章人 (ヨシダ アキヒト)
吉田 章人(ヨシダ アキヒト)
〔専門分野〕中国古代史
〔研究課題〕春秋時代の世族政治とその権力構造について
〔最終学歴〕東海大学大学院文学研究科史学専攻博士課程後期修了
〔取得学位〕博士(文学)
〔研究業績〕
〈共著書〉
『雲南大理白族の白文用例集―大本曲『黄氏女対金剛経』を例に―』(立石謙次編著・吉田章人著、東海大学文化社会学部アジア学科、2020年3月)
『大本曲『黄氏女対金剛経』の研究―雲南大理白族の白文の分析―』
(立石謙次・吉田章人著、東京外語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2017年1月)
〔研究課題〕春秋時代の世族政治とその権力構造について
〔最終学歴〕東海大学大学院文学研究科史学専攻博士課程後期修了
〔取得学位〕博士(文学)
〔研究業績〕
〈共著書〉
『雲南大理白族の白文用例集―大本曲『黄氏女対金剛経』を例に―』(立石謙次編著・吉田章人著、東海大学文化社会学部アジア学科、2020年3月)
『大本曲『黄氏女対金剛経』の研究―雲南大理白族の白文の分析―』
(立石謙次・吉田章人著、東京外語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、2017年1月)
〈論文〉
「本子曲『黄氏女対金剛経』語彙集-雲南省白族の白文に関する基礎的研究-」
(『150回例会記念 学術研究論文集』(中国語文学会)、中國語文學會、2018年11月)
「東洋文庫におけるIOM RAS所蔵非佛教漢語文書の整理と考察」
(土肥義和・氣賀澤保規編『敦煌・吐魯番文書の世界とその時代』、公益財団法人東洋文庫、2017年3月)
「平丘の盟から見た魯・晋関係」
(『史学』文学部創設125年記念号第1分冊(第84巻第1-4号)、391-413頁、2015年4月)
「サンクトペテルブルク東洋学研究所蔵 ソグド・ウイグル文献中の非仏教漢語史料管見」
(土肥義和代表『内陸アジア出土4~12世紀の漢語・胡語文献の整理と研究』、東洋文庫、30-34頁、2013年3月)
「春秋時代における魯国の世族政治―外交・国際情勢との関連の視点から―」(博士論文、2013年3月)
「「堕三都」から見る魯の三桓氏の権力構造」
(『東海大学紀要文学部』第93号、45-68頁、2010年9月)
「魯・斉関係における婚姻と夫人」
(『史学』第78巻第3号、35-72頁、2009年10月)
「日本における近年の春秋史研究の現状と課題」
(『歴史学研究』第830号、35-43頁、2007年8月)
「魯の三桓氏の世族化と権力掌握について」
(『東海史学』第40号、17-40頁、2006年3月)
〈共著〉
「『穆天子伝』訳注稿〔四〕」
(『史学』第86巻第4号、85-126頁(担当:85-91頁)、2017年3月)
「『穆天子伝』訳注稿〔三〕」
(『史学』第83巻第2・3号、139-165頁(担当:158-163頁)、2014年7月)
「『穆天子伝』訳注稿〔二〕」
(『史学』第82巻第1・2号、129-198頁(担当:162-170頁)、2013年4月)
「『穆天子伝』訳注稿〔一〕」
(『史学』第80巻第4号、101-161頁(担当:134-146頁)、2011年12月)
「1999年中国考古学関連文献目録」
(『日本中国考古学会会報』第10号、152-158頁、2000年10月)
〔最近の動向〕
「平丘の盟から見た魯・晋関係」
(『史学』文学部創設125年記念号第1分冊(第84巻第1-4号)、391-413頁、2015年4月)
「サンクトペテルブルク東洋学研究所蔵 ソグド・ウイグル文献中の非仏教漢語史料管見」
(土肥義和代表『内陸アジア出土4~12世紀の漢語・胡語文献の整理と研究』、東洋文庫、30-34頁、2013年3月)
「春秋時代における魯国の世族政治―外交・国際情勢との関連の視点から―」(博士論文、2013年3月)
「「堕三都」から見る魯の三桓氏の権力構造」
(『東海大学紀要文学部』第93号、45-68頁、2010年9月)
「魯・斉関係における婚姻と夫人」
(『史学』第78巻第3号、35-72頁、2009年10月)
「日本における近年の春秋史研究の現状と課題」
(『歴史学研究』第830号、35-43頁、2007年8月)
「魯の三桓氏の世族化と権力掌握について」
(『東海史学』第40号、17-40頁、2006年3月)
〈共著〉
「『穆天子伝』訳注稿〔四〕」
(『史学』第86巻第4号、85-126頁(担当:85-91頁)、2017年3月)
「『穆天子伝』訳注稿〔三〕」
(『史学』第83巻第2・3号、139-165頁(担当:158-163頁)、2014年7月)
「『穆天子伝』訳注稿〔二〕」
(『史学』第82巻第1・2号、129-198頁(担当:162-170頁)、2013年4月)
「『穆天子伝』訳注稿〔一〕」
(『史学』第80巻第4号、101-161頁(担当:134-146頁)、2011年12月)
「1999年中国考古学関連文献目録」
(『日本中国考古学会会報』第10号、152-158頁、2000年10月)
〔最近の動向〕
春秋時代の政治史、特に魯国を対象として、その政治体制と対外政策について研究しています。春秋時代の基本的史料である『春秋左氏伝』や新出史料を用いて、春秋時代における諸侯国の対外政策および春秋時代に台頭する世族と呼ばれる勢力の動向について検討していくことが、私の研究課題です。こうした視点を軸として、『歴史からみた経済と社会』(日本経済史研究所開所90周年記念論文集)に「春秋時代の晋・斉関係について-『左伝』における襄公期を対象として-」を発表しました。
また、近年は中国少数民族である白族(ペー族)の白語・白文資料の研究にも研究分担者として関わっています。白語は文字を持たない言語とされていますが、民間芸能などでは漢字を用いた表記方法があり、こうした漢字表記による白文資料の分析と白語語彙の収集に努めています。現在は白族の民間芸能である大本曲のテキストの翻訳作業を進めており、その成果として「大理白族の大本曲『斬龍頭』研究序説 (2) 」(共著、『環日本海研究年報』第29号)を発表することができました。
(2024年5月)